
かつて「Made in Japan」といえば、世界中で信頼と品質の象徴として名を馳せていました。家電、自動車、カメラ、時計、電子機器――そのどれもが「日本製だからこそ安心できる」「長く使える」と評価され、プレミアムな選択肢として認知されていた時代が確かに存在しました。
しかし、近年のヨーロッパ市場、特にイギリスにおいて、その神話は徐々に崩れ始めているようです。今、イギリスの消費者が熱視線を送っているのは「韓国製」。SamsungやLG、HyundaiやKiaといった韓国メーカーが存在感を強める中、日本企業の影は薄れつつあるのが現実です。
ではなぜ、かつて世界を席巻した日本ブランドがこのような状況に陥ってしまったのでしょうか? そして、日本企業が再び国際的な競争力を取り戻すには、何が必要なのでしょうか?
本稿では、イギリス市場の実情をもとに、韓国企業の成功要因を分析しながら、日本企業が進むべき道について具体的なアドバイスを提示していきます。
1. 「韓国製」躍進のリアル:イギリスで何が起きているのか?
ロンドン市内の家電量販店に足を運ぶと、その風景は一昔前とは様変わりしています。テレビ売り場の目立つ位置にはSamsungやLGの最新モデルが並び、スマートフォンはGalaxyシリーズが若年層に人気。冷蔵庫や洗濯機も韓国ブランドが多く、まるで「韓国一色」といった印象すら受けます。
自動車業界でも同様の現象が起きています。HyundaiやKiaは、欧州市場向けにデザインを最適化し、「スタイリッシュかつコスパが高い」として幅広い層から支持を獲得しています。一方、日本車は「信頼できるが地味」というイメージが強く、購入動機としての魅力を失いつつあるのです。
2. 日本ブランドはなぜ力を失ったのか?4つの主要要因
(1) グローバルマーケティング力の差
韓国企業の特徴の一つは、グローバル市場への積極的な「情報投資」です。Samsungはイギリス国内でサッカーイベントのスポンサーを務め、音楽フェスに出資し、若年層のライフスタイルの一部として自然に浸透しています。
一方、日本企業は海外市場において保守的なマーケティング姿勢が目立ちます。優れた製品を作れば売れるという「製品志向」が根強く、消費者の心をつかむ「ブランド体験」の設計が後回しになってしまっているのです。
(2) デザインとUXへの意識差
イギリスの消費者は、機能性だけでなく「使っていて楽しい」「持っていてカッコいい」といった感性も重視します。韓国製品はこの点において非常に敏感で、デザイン部門に大胆な投資を行い、世界的に有名なデザイナーとのコラボも積極的です。
日本製品はどうでしょうか。高機能で耐久性は抜群でも、「無難」「昔っぽい」と評価されることが多く、特にZ世代・ミレニアル世代にとっては選択肢の外に置かれがちです。
(3) 価格競争力の戦略性
同等のスペックで比較したとき、韓国製品の方が「価格に見合った価値」を提示するのが上手です。単なる安さではなく、「合理的な価格で満足できる」という感覚に訴えかけています。
日本製品は「高品質=高価格」という公式に頼りすぎており、結果として「コスパが悪い」という評価につながってしまっています。
(4) イメージの陳腐化と進化の停滞
「日本製=昭和・平成の技術大国」という過去の栄光が、今や逆に「古い国」「アップデートされていないブランド」という印象につながっていることもあります。先進性を見せる努力を怠れば、たとえ実際に革新的な技術を開発していても、市場には届きません。
3. 韓国企業に学ぶ成功モデル
韓国企業は単に「安くて便利」な製品を作っているわけではありません。彼らが成功した本質的な理由は、以下の3つに集約されます:
- ストーリーテリング力:「この商品を持つことでどんなライフスタイルが実現できるか」を語る力。
- グローバル対応の即応性:市場ごとのニーズに合わせて商品・広告・価格を柔軟に調整。
- ブランド体験への投資:製品を超えた「ブランドとの出会い」をデザインする感性。
これらの要素は、いずれも単なる製品開発や広告戦略の枠を超えた、企業文化の変革に関わるものです。
4. 日本企業が今すぐ取り組むべき戦略とは?
では、日本企業が「Made in Japan」の価値を再び高め、世界市場での競争力を取り戻すためには、どのような戦略をとるべきなのでしょうか。以下に具体的な提言を示します。
(1) マーケティング人材の国際化と権限強化
海外市場におけるマーケティング責任者に、もっと裁量を与えるべきです。日本本社からの一律の戦略指示では、現地のニーズや感覚に即応することはできません。現地で意思決定できる仕組みと、その国の文化・消費者を理解した人材登用が鍵となります。
(2) デザインシフト:機能美から感性美へ
「壊れにくい」「正確である」だけでは消費者の心は動きません。韓国企業のように、視覚的魅力や感性に訴える要素を製品に組み込むこと。デザイン部門の地位向上と、外部との協業も視野に入れるべきです。
(3) 「物語性のある商品開発」とブランディング
たとえば、環境配慮・職人技・サステナビリティなど、日本の強みを生かしたストーリーを明確に伝える努力が求められます。ただ「良い製品です」と言うのではなく、「なぜそれが生まれたのか」「誰が、どのような哲学で作っているのか」を世界に発信すべきです。
(4) Z世代・ミレニアル世代へのアプローチ強化
これからの市場を担う若い世代は、「スマートで手軽で、かつ自分の価値観に合っているか」で商品を選びます。SNS戦略の強化、インフルエンサーとの連携、ポップカルチャーへの積極的な関与が求められます。
5. 「高品質」だけでは生き残れない時代へ
日本製品が劣っているわけでは決してありません。むしろ、その精密さや耐久性、信頼性は今でも世界トップレベルです。しかし、「品質の良さ」だけでは、もはやブランドとしての価値を生み出す時代ではありません。
ブランドとは、「意味」と「感情」で選ばれる存在です。そこには「誰に、何を、どう伝えるか」というマーケティングの力と、「時代に合った価値」を体現する感性が不可欠です。
6. おわりに:再び「憧れの日本」へ
世界がかつて憧れた「Made in Japan」を復活させるためには、過去の成功体験にとらわれず、新たな価値観で企業活動を見直す必要があります。
韓国企業がそれを実現できたのは、「どうすれば世界に選ばれるか」という問いに真剣に向き合い続けてきたからに他なりません。
日本企業にとって今こそが、「変わる」べきタイミングなのです。




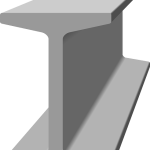





Comments