
イギリスの報道が決して触れない“王室の壁”とは?
「報道の自由の国」として知られるイギリス。しかし、そこにはメディアが決して越えられない一線が存在します。 それが――王室に関する報道の“沈黙の壁”。 BBCをはじめとする主要メディアが、国民の関心が高いにもかかわらず、あえて触れない王室の領域があるのです。 この“見えない検閲”の背景には、英国社会の長い歴史と、政治・経済・王室が絡み合う複雑な構造が隠されています。
① 英国報道の自由と王室の「特別扱い」
イギリスは世界でもっとも古い報道文化を持つ国のひとつであり、法的にもメディアの独立性は保障されています。 しかし実際には、王室関連のニュースに対しては「編集上の自己規制」が長年行われてきました。 これは明文化された法律ではなく、「尊敬と敬意の文化(culture of deference)」として根付いています。
BBCやThe Timesなどの老舗メディアは、王室報道については“事実の確認が困難な内容は報じない”という原則を持ち、 王室関係者の私生活や内部の発言に関しては極めて慎重な姿勢をとります。 一方で、海外メディアやソーシャルメディアでは、同じ内容が自由に議論されているというギャップも存在します。
② BBCと王室――長い沈黙の共存関係
BBC(英国放送協会)は公共放送として、王室の公式行事を最も多くカバーするメディアです。 しかし、BBCは王室の「報道パートナー」であると同時に、「沈黙の守護者」でもあります。 放送免許(Royal Charter)は国王の名で発行されるため、BBCの存在そのものが王室制度に支えられているのです。
そのため、BBCは王室に関する批判的報道を行う場合、「公共の利益に明確に資する場合のみ」という厳しい内部基準を設けています。 たとえば、1995年に放送された「ダイアナ妃インタビュー」は大きな反響を呼びましたが、 その後BBCが取材手法に問題を抱えていたことが発覚し、王室からの信頼を大きく失う結果となりました。 以来、BBCは王室関連報道において極端に慎重な姿勢を保っています。
③ 英国メディアの「見えない検閲」構造
表現の自由が保障されているにもかかわらず、イギリスの大手メディアは王室報道で自主的な制約を設けています。 これを、ジャーナリズム研究者たちは「soft censorship(ソフトな検閲)」と呼びます。 法的圧力ではなく、文化的圧力――つまり「触れてはいけない」という社会的合意が存在するのです。
この現象は、王室に対する国民の敬意だけでなく、メディア側の経済的依存にも起因しています。 王室行事の中継・特番・視聴率効果はBBCやITVにとって重要な収入源であり、 批判的報道は「視聴者の感情」だけでなく「放送関係者の立場」も揺るがすリスクを伴います。
④ 報じられなかった“内部スキャンダル”の数々
海外メディアでは王室の個人関係や財務問題が話題になることがありますが、 イギリス国内の報道機関は、確認できない限り「沈黙」を保つのが慣例です。 これには倫理的理由もありますが、同時に「国民統合の象徴としての王室を守る」という政治的・文化的判断も働いています。
こうした構造により、英国民の多くが「報道されない王室の現実」を知りながらも、 それを“公に議論しないこと”を社会的なマナーとして受け入れているのです。 この沈黙の文化こそ、現代のイギリスにおける最大の“言葉にされないタブー”と言えるでしょう。
⑤ SNS時代が突きつける王室報道の新たな課題
近年、X(旧Twitter)やTikTokなどのSNSでは、王室に関する“裏の話題”が拡散するケースが増えています。 もはや伝統メディアだけが情報を制御できる時代ではありません。 BBCや主要紙も、「沈黙を続けるべきか、透明性を取るべきか」という選択を迫られています。
2020年代に入り、イギリス社会では「敬意」と「透明性」のバランスをどう取るかが大きな議題となっています。 王室を守る沈黙の伝統が、情報社会の中でどこまで通用するのか――今、英国ジャーナリズムの本質が問われています。
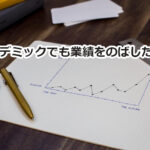






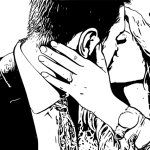


Comments