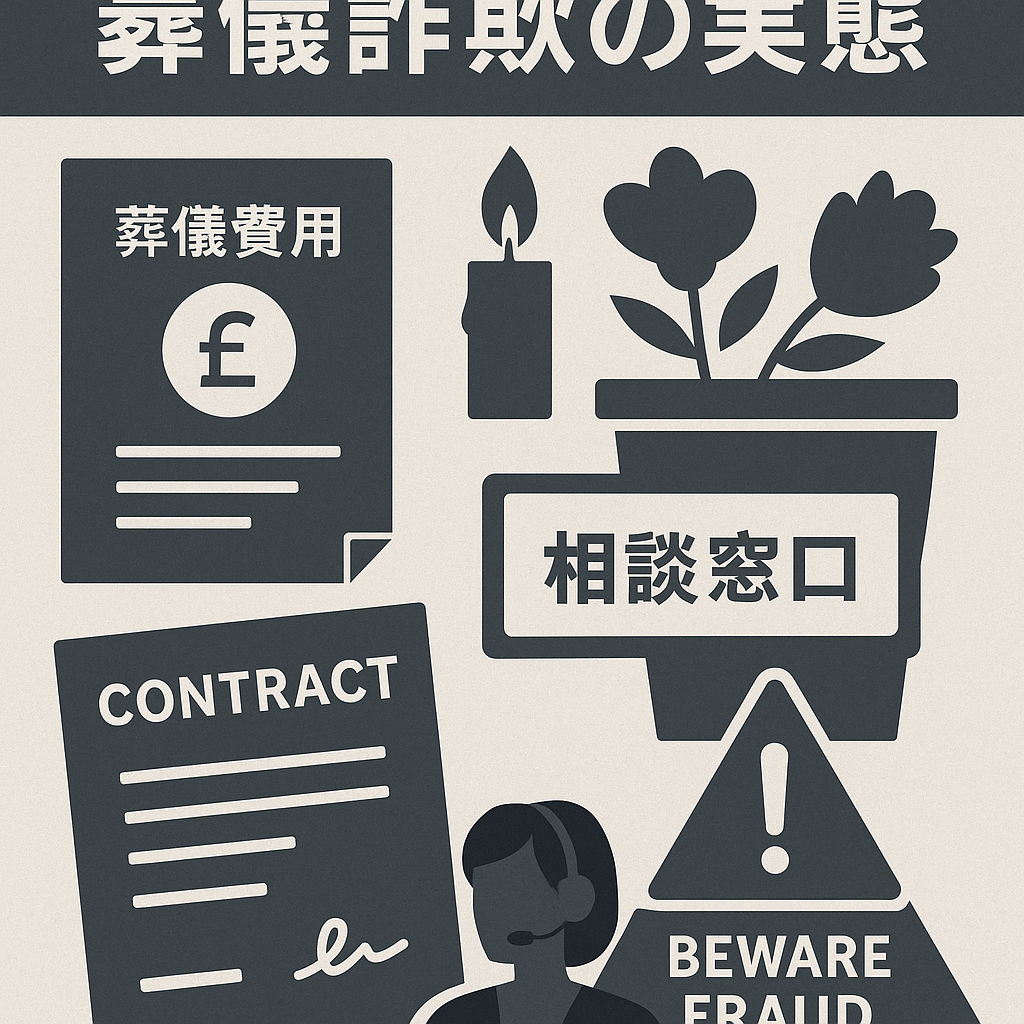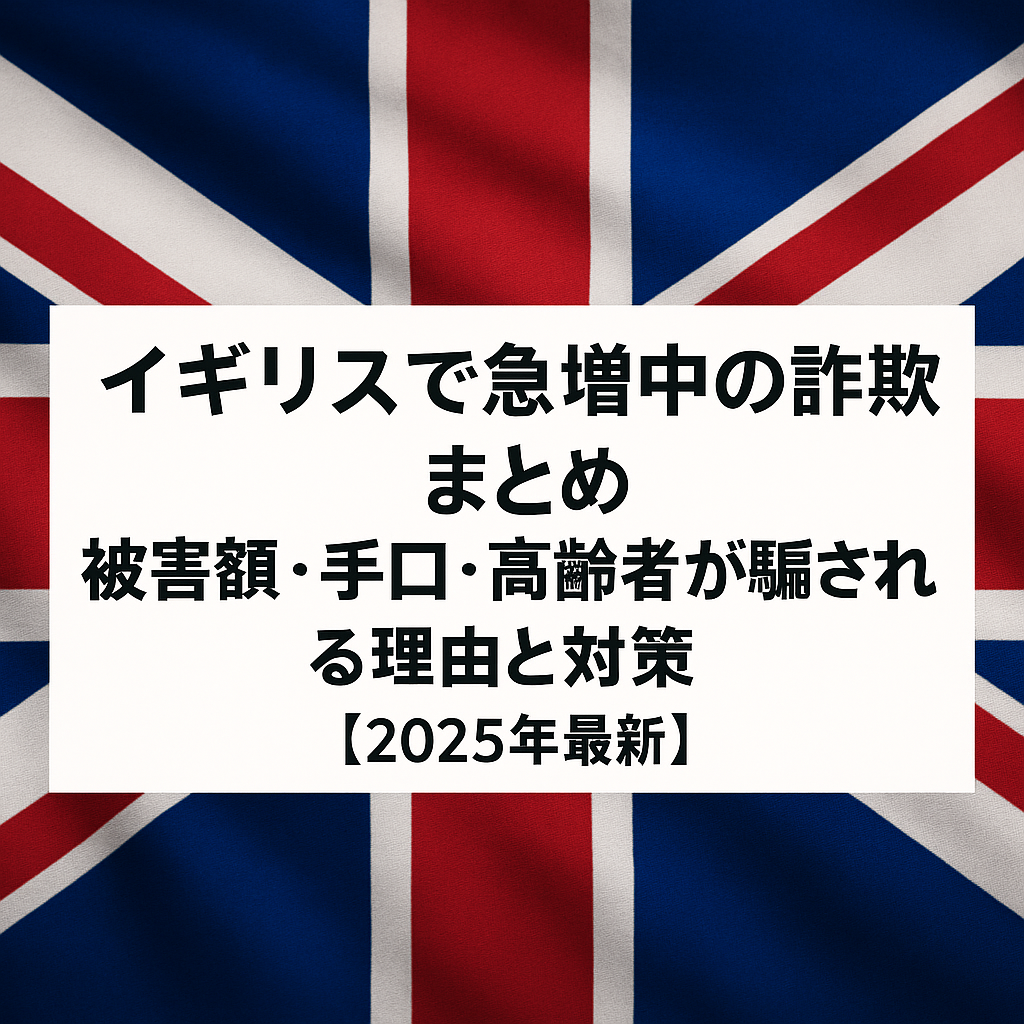…
詐欺
イギリスでの葬儀詐欺の実態|悪質な葬儀業者の手口と被害防止策を徹底解説
…
【トルコ・アンタルヤ】英国人女性が詐欺被害に遭う|SNSで広がる恋愛詐欺・投資トラブル【2025年最新版】
…
イギリスで急増中の詐欺まとめ|被害額・手口・高齢者が騙される理由と対策【2025年最新】
…
日本で学歴詐称が後を絶たない理由 —— イギリスでは「あり得ない」その違いとは
…
イギリスの学歴詐称事情|英国で履歴書に嘘を書くリスクと企業のチェック体制
…
ビザをエサにした「偽りの恋」:ロンドンで広がる新たな恋愛詐欺の実態
…
英国で急増するロマンス詐欺の実態──甘い言葉の裏に潜む罠
…
【注意喚起】イギリスは個人情報保護の無法地帯?実際に被害に遭った私の体験談と具体的なリスク
…
イギリスで急増する「見覚えのない違反金催促の手紙」:届いたときの対処法と防衛策
…