
はじめに
イギリス、とりわけイングランドにおいて「セント・ジョージ・クロス(St. George’s Cross)」――白地に赤の十字のイングランド国旗――を家の外に大きく掲げている家を見ると、「この人はレイシストに違いない」という反応を抱く人が少なくない。特に都市部の多文化的なコミュニティにおいては、このような国旗掲揚が一種の警告サインのように受け取られることすらある。
この現象はどこから来て、なぜそのような認識が広がっているのか。そして、その認識は正当なものなのか、それとも過剰な偏見なのか。本稿では、イングランドの国旗が背負わされてきた政治的・文化的な意味をひも解きながら、「イングランド国旗=レイシズム」という図式がどのように形成されてきたのかを考察していく。
セント・ジョージ・クロスの歴史的背景
イングランドの国旗であるセント・ジョージ・クロスは、中世の十字軍時代にまでさかのぼる。イングランドの守護聖人である聖ジョージにちなんでおり、13世紀から軍旗として使用されていた。その後、王権と国家を象徴する旗として定着した。
歴史的にはこの旗は王室や国家行事で用いられるものであり、特定のイデオロギーと直結していたわけではない。しかし、現代においてはその使用がしばしば政治的な文脈に包まれるようになった。
ナショナリズムと極右の利用
20世紀後半から21世紀初頭にかけて、イングランドでは移民政策や多文化主義への反発としてナショナリズムが再び力を持ち始めた。この文脈の中で、極右団体やレイシストのグループがセント・ジョージ・クロスを象徴的に用いるようになる。
特に有名なのが、British National Party(BNP)やEnglish Defence League(EDL)といった団体である。これらは、移民排斥やイスラム教徒への敵対心を掲げ、「イングランド人のアイデンティティを守る」という名目で活動し、国旗をその象徴として掲げた。
これにより、「大きなイングランド国旗=極右・レイシズム」というイメージが、社会に広がっていったのは否定できない。
フットボール文化と国旗の「日常化」
一方で、セント・ジョージ・クロスはフットボール(サッカー)の応援にも広く使われている。とりわけワールドカップやEUROといった国際大会の時期になると、全国で国旗を掲げる光景は一般的だ。
このような時期に限って言えば、国旗の掲揚はナショナリズムというより愛国心の表現であり、レイシズムとは直結しない。しかし、問題は日常的に、しかも「特大サイズ」で家や車に国旗を掲げ続けている場合だ。そのような行為は、多くの人にとって“普通の応援”以上の意味を持ってしまう。
マイノリティの視点から見た国旗
イギリスに暮らす多くの移民やマイノリティにとって、大きなイングランド国旗は「ここは俺たちの国だ、お前たちは余所者だ」というメッセージとして受け取られることがある。実際、「国旗を掲げている家の近くで嫌がらせを受けた」「肌の色を理由に警戒された」といった証言は少なくない。
特に、ブレグジット(イギリスのEU離脱)をめぐる国論が二分された時期には、セント・ジョージ・クロスが「排外主義」の象徴として利用される場面が頻繁に見られた。これにより、国旗のイメージがさらに悪化し、「国旗を掲げている人=排他的な思想を持つ人」と捉えられやすくなったのである。
偏見と現実のあいだ
とはいえ、「大きな国旗を掲げている=レイシストである」と断定することは危険だ。なぜなら、人々が国旗を掲げる理由は多様であり、すべてが政治的・差別的な意図に基づいているとは限らないからである。
たとえば地方の保守的なコミュニティでは、単純に地域の伝統やイングランドへの誇りから国旗を掲げている家もある。また、軍関係者や退役軍人の中には、国旗を尊重する意味で掲げている人もいる。そこにレイシズムの意図はない。
しかし、意図がどうあれ、それがどう「受け取られるか」が社会的な問題となる。意図と印象が乖離している限り、誤解と対立は生まれ続けるだろう。
メディアの役割とイメージの強化
この「イングランド国旗=レイシズム」の図式を強化してきたのが、大衆メディアやSNSである。新聞やテレビは、極右のデモやヘイトクライムに関する報道でしばしば国旗を映し出し、「国旗を掲げる者は危険だ」という印象を強めてきた。
SNSでは、特定の投稿が拡散され、文脈を無視して「この家もレイシストだ」と断定されることもある。これは、個人を危険にさらすと同時に、社会全体に「国旗を掲げてはいけない」という空気を生む。
一方で、リベラル層やマイノリティの一部からは、「なぜイギリスでイギリス国旗を掲げることが、ここまで問題視されなければならないのか?」という疑問の声も出ている。これはナショナル・アイデンティティをめぐる深いジレンマである。
旗の意味を取り戻す試み
最近では、イングランドの国旗をネガティブな文脈から解放しようとする動きもある。たとえば、移民出身の市民があえて国旗を掲げ、「自分たちもイングランドの一部だ」というメッセージを発信する例も増えてきた。
また、サッカー代表チーム自体が人種的に多様であることも、国旗のイメージを変える要因となっている。ラヒーム・スターリングやマーカス・ラッシュフォードのような黒人選手が国を代表する姿は、「イングランド=白人」という固定観念を揺さぶる存在だ。
結論:「レイシストに違いない」という断定の危険性
「大きなイングランドの国旗を掲げている家の人は、間違いなくレイシストである」という説には、確かに一部の歴史的・社会的背景がある。極右の象徴として国旗が用いられてきた事実は否定できない。
しかし、その説を「絶対的な真実」として信じることには、大きな問題がある。それは他者に対する根拠なき決めつけであり、結果として分断を深めるだけである。イングランドの国旗をめぐる議論は、レイシズムやナショナリズムだけでなく、「共存とは何か」を問い直す機会でもある。
旗は無言だが、その意味は社会がどう語るかによって形づくられる。レイシズムと戦うためにも、私たちは安易なラベリングに頼るのではなく、背景と文脈を深く理解しようとする姿勢を持つべきである。





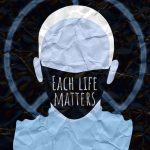




Comments