
序章:「本音で語る」ことは本当に文化の違いなのか?
イギリス人は「本音をなかなか語らない」とよく言われる。これは、彼らが礼儀や距離感を大切にする文化に根ざしているという説明が一般的だ。「遠回しな表現」「皮肉」「間接的な否定」など、イギリス特有のコミュニケーションスタイルが、それを如実に物語っている。
しかし筆者は最近、ある疑問を抱くようになった。それは、「イギリス人が本音を語らないのは、本当に文化的な特徴なのか?」という問いである。付き合いが長くなっても、なお距離を感じる場合、それは単に国民性や文化の違いのせいではなく、「外国人相手」だからこそ生じている可能性があるのではないか?
この問いは、外国人として日本に住んでいる人々の間でも共鳴するはずだ。私たちが日本人と深く付き合い、本音を聞くことができるまでには、多大な時間と努力が必要だった。では、逆に日本にいる外国人同士はどうか? 本音で悩みを語り合う関係に至るケースは、実はそう多くないのではないか?
このような疑問から、「背景と歴史を共有しない他者」と本音で語ることの難しさについて、この記事では掘り下げていく。
第一章:文化か、相互理解のハードルか?
異文化コミュニケーション論では、よく「高文脈文化」と「低文脈文化」という区分が使われる。日本は「高文脈文化」に分類され、言葉に出さずとも察することが求められる。一方、アメリカやドイツなどは「低文脈文化」とされ、明確な言語化が重視される。
この理論に当てはめれば、イギリスは中間、もしくはやや高文脈寄りの文化に属するだろう。皮肉やユーモアを駆使して、本心を婉曲に伝えるのが彼らの流儀である。
だが、たとえ言語化のスタイルが違っても、母国同士の関係性の中では、本音がふと漏れる瞬間がある。親しい友人、家族、長年の同僚といった「文脈を共有している」関係性の中では、文化的な壁を越えて人は本音を語る。
つまり、「本音を語らない文化」というよりも、「本音を語るに足るだけの文脈を持ちづらい関係」が問題なのではないか。文化というより、共有される歴史の有無が、本音を語る・語らないの大きな要因なのだ。
第二章:「悩みを語る相手がいない」外国人の孤独
日本に住む外国人、とりわけ長期滞在者の多くは、意外なほど「誰にも悩みを話せない」と語る。職場の人間関係、家族との葛藤、日本社会への適応に伴うストレス──こうした悩みを抱えながらも、それを共有できる相手が見つからないという。
なぜなら、同じ国の出身者とですら「バックグラウンド」が違ってしまっているからだ。ある人はエリート企業に勤めているかもしれないし、別の人は言語学校の講師をしている。家族を持っている人もいれば、独身で気ままに暮らす人もいる。出身国が同じでも、人生の選択や価値観が全く異なれば、「共感の前提」が崩れてしまう。
つまり、悩みを語るには「言語」だけでは足りないのだ。言語以上に、「過去を共有している感覚」「似たような体験を経てきた共通認識」がなければ、悩みはただの説明に終わってしまう。相手に理解されていないという感覚が、心の壁をさらに厚くしていく。
第三章:「共有の歴史」がないことで生じる断絶
人は誰かと深く繋がるとき、ただ言葉を交わすだけではない。「あのとき、あの場所で、こんなことがあったよね」と語れる「歴史」が、その人間関係を土台から支える。
しかし、異国で出会った相手とは、当然ながらそうした共有の過去がない。だからこそ、「今ここ」だけで関係を築かなければならない。これは思った以上に大きなハンデである。
たとえば、日本人同士ならば、学生時代の話、地元の話、テレビ番組や流行の話など、自然と共通項が生まれる。そうした「無意識の共感ポイント」が、関係の潤滑油となっている。一方、外国人同士では、まず共通点を探すことから始まるため、関係構築に必要なエネルギーが格段に大きくなる。
これは、イギリス人が外国人に対してなかなか本音を語らない理由のひとつとも言えるだろう。相手に自分の背景を説明するのが面倒、どうせ共感されない、という諦めが、無意識に心を閉ざさせてしまうのだ。
第四章:「信頼」は時間と共通体験の蓄積で生まれる
本音を語るために必要なのは、やはり「信頼関係」である。しかし、その信頼とは、単なる「人柄がいい」というものではない。むしろ、何を共に経験してきたか、どれほど長く寄り添ってきたか、という「歴史の厚み」が信頼の本質を形作る。
だからこそ、外国人が外国人同士で信頼関係を築くには、意識的な努力が求められる。日々の何気ないやり取り、小さな助け合い、共に過ごす時間──それらが積み重なって初めて、腹を割って話せる関係に到達する。
それは日本人同士でも同じことだが、文化や言語の違いがない分、圧倒的に「近道」が多い。異文化間では、その近道がない。だからこそ、たとえ付き合いが長くても「まだ距離がある」と感じるのは、文化のせいではなく、共有される文脈の欠如ゆえなのだ。
結論:本音で語るには「背景の翻訳」と「共通体験」が不可欠
イギリス人が本音を語らないのは、単なる国民性の問題ではない。日本にいる外国人同士が悩みを語り合うことが難しいのも、文化の壁だけではない。
本音で語るには、「翻訳可能な背景」と「積み上げた時間」が必要なのだ。背景の違いを乗り越えるには、自分の文脈を相手に丁寧に説明し、相手の文脈を理解する努力が求められる。そして、日々の中で少しずつ「共通の歴史」を築いていくことでしか、心の扉は開かれない。
現代社会はグローバル化が進み、人種や国籍を超えた交流が日常となった。しかし、その一方で、「他者と深くつながることの難しさ」は、むしろ増しているとも言える。多様性の中で生きる私たちにとって、「本音で語り合う」ことは、常に意識的な行為であり、容易には得られない関係性のゴールなのだ。
だからこそ、私たちは問い続けるべきだ。「本音を語れる相手」とは誰なのか。自分がその相手になるために、どんな努力を重ねていけるのかを──。

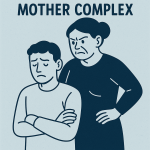








Comments