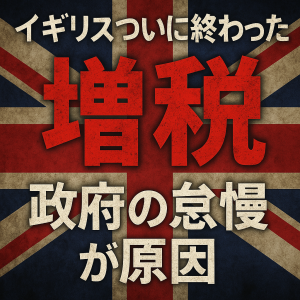
過去50年で最大級の増税は、政府の怠慢が招いた“必然の破綻”
2025年、イギリスは国民にとって極めて重い現実と向き合うことになった。
政府は、所得税の控除枠凍結、富裕層や投資収益への課税強化、不動産への新税など、「過去50年で最大規模」とも言われる増税パッケージを発表。これにより、英国の税負担率はほぼ歴史的な最高水準へ到達する。
国民の間で「イギリスはもう終わった」「政治のツケが回ってきた」という声が上がるのは当然だ。
なぜここまで追い込まれたのか。なぜ増税を避けられないところまで放置してきたのか。
■ なぜ“今さら”増税なのか
結論から言えば、イギリスの増税は一夜にして起きた災害ではない。
むしろ、数十年にわたる政治の怠慢、構造的な問題の放置の帰結である。
1. 膨張し続けた財政赤字
イギリス政府の支出は膨らみ続け、特にコロナ禍・エネルギー危機・高インフレで国債発行が急増。
その一方で、歳出の抜本的見直しや構造改革は後回しにされてきた。
「痛みを伴う改革」を避け続けた結果、借金を積み上げて“将来にツケを回す”政治が定着。
今になってその返済と利払いが重くのしかかり、増税は避けられない状況となった。
2. 経済成長率の低迷
イギリスは長年、生産性の伸びが低く、先進国の中でも成長が鈍い。
生産性が伸びない国は税収も伸びない。
にもかかわらず、歴代政府はこの問題を本気で改善してこなかった。
教育投資・技術投資・規制改革などの「長期的に効く政策」を後回しにした結果、
経済は停滞し、税収は不足し、結局は増税に頼らざるを得ない。
3. インフレと金利上昇で“借金の維持すら苦しい”
インフレと金利の高止まりによって、
政府の国債利払い費は急増している。
赤字を国債で埋める「先送り財政」は、金利が低い時代だからこそ成立した。
しかし今は、借金を維持するだけでも巨額のコストがかかる。
これも増税を招いた大きな理由のひとつ。
4. 過去の“人気取り減税”が完全に裏目に
これまでの政府は、税負担を上げることを避け、逆に減税を行って支持を回復することも多かった。
しかし、その財源は国債、つまり借金で賄った。
減税で「国民に優しい顔」をしながら、
実際は未来の国民の財布から金を抜き続けていたようなものだ。
これが、今まさに跳ね返ってきている。
■ すべて政府の怠慢だったのか?
厳密に言えば「すべて」ではないが、大部分は政治の責任といえる。
- 生産性低迷を何十年も放置
- 財政健全化の先送り
- 人気取りの短期政策を優先
- 社会保障改革を先延ばし
- 高齢化への備え不足
- 税金の使い方の透明性・効率性を改善しなかった
これらはすべて“避けることのできた未来”だった。
つまり、今回の大増税は「不可避の運命」ではなく、
政治が選んできた道の“最終結果”だと言える。
■ 「イギリスついに終わった」という言葉の背景
国民が「終わった」と嘆くのは、増税そのものよりも、
見通しが立たない不安によるものだ。
- これからも増税が続くのでは?
- 生活費はさらに上がるのでは?
- 経済は回復するのか?
- 賃金は追いつくのか?
そして何より、
“これまでの怠慢を繰り返す政治に未来を任せられるのか”
という深い不信感が広がっている。
■ 終わらせないために必要なのは「増税以外の改革」
増税は対症療法にすぎない。
本当に必要なのは、これまで避けてきた構造改革だ。
- 成長力を高める教育・技術・産業投資
- 生産性向上につながる規制改革
- 公共部門の効率化
- 社会保障制度の長期的な見直し
- 税金の無駄遣いの徹底的な排除
- 財政の中長期ビジョンの再構築
これらを行わずに増税を続けるだけなら、
国民負担は重くなる一方で、国の再生は遠のく。
■ 結論:増税は“終わりの始まり”ではなく、怠慢の清算
イギリスをここまで追い込んだのは、
一度の危機ではなく、数十年にわたる政治の失策の積み重ねだ。
そして今起きていることは、
その“清算”の始まりにすぎない。
「ついに終わった」のではなく、
“ついにツケを払わされ始めた”というのが正確だろう。





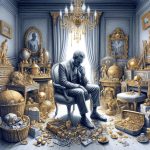


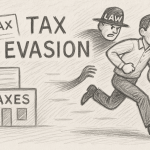

Comments