
はじめに
「イギリス人は曖昧で遠回しだ」とよく言われます。日本人と似たように見えるそのコミュニケーションスタイルは、他国の人々、特に率直な表現を好む国(例:アメリカ、ドイツ、フランスなど)からは「何を考えているのか分からない」と映ることもしばしば。
しかし、イギリス人はただ単に曖昧にしているのではなく、礼儀や相手への配慮、文化的背景からくる「間接表現」を駆使しているのです。本記事では、イギリス人の典型的な言い回し、その裏にある「本音」を読み解く方法、そして実践的な対応策までを、体系的に解説します。
第1章:イギリス人はなぜ遠回しに話すのか?
1.1 礼儀を重んじる文化的背景
イギリスでは、「相手を不快にさせないこと」が極めて重要です。そのため、批判や否定、指示といった角が立ちやすい表現はオブラートに包んで伝えるのが一般的。たとえば「No」と直接言うのではなく、「Perhaps not」「I’m not sure that’s the best idea」といった婉曲表現を使います。
1.2 隠された「階級意識」と「プライド」
階級社会の歴史が色濃く残るイギリスでは、「余裕のある振る舞い」が上品とされます。率直な物言いは「粗野」「がさつ」と見なされることも。そのため、遠回しであっても「賢く表現する能力」が高く評価されるのです。
第2章:典型的なイギリス的婉曲表現とその解釈
以下は、イギリス人が日常的に使う間接的な表現と、それが本当に意味するところを対応表で解説したものです。
| イギリス人が言うこと | 本音・真意 | 解説 |
|---|---|---|
| “That’s interesting.” | それはおかしい/賛成できない | 興味があるというより、皮肉で使われることも |
| “I’ll bear it in mind.” | 多分忘れる/実行しない | 「検討します」に近いが、行動には移さない |
| “I might join you later.” | 行かない可能性大 | 社交辞令としての「考えとく」 |
| “With all due respect…” | 否定・反論の前触れ | 「失礼を承知で言いますが」 |
| “It’s not quite what I had in mind.” | 全然違う | 上品な形で「違う」と伝える典型例 |
| “You must come for dinner sometime.” | 特に招待する気はない | 社交辞令の最たるもの |
| “That’s a brave proposal.” | それは無謀だ/現実的でない | 勇気があるね、は皮肉の可能性も高い |
第3章:ビジネスシーンでの注意点
3.1 会議での発言:反対意見は「前置き」で包まれる
- “That’s certainly an option.” → それ以外の案を推したい
- “I see where you’re coming from.” → でも私は違う意見を持っている
- “It’s an interesting idea, however…” → あまり良い案だとは思っていない
3.2 メール表現に隠れたニュアンス
イギリス人のメールでは、直接的な命令や要求はほぼ見られません。たとえば:
- “Would you mind…?” → 実は早くやってほしい
- “Just wondering if…” → もうそろそろ回答が欲しい
- “Per our previous discussion…” → 何度も言ってますよ、覚えてますか?
ポイント:柔らかい言い回しでも、急ぎや不満のサインが隠れていることが多い。
第4章:イギリス人の感情表現を読み解く技術
4.1 「表情」や「声のトーン」で見抜く
- 微笑みながらの否定 → 社交辞令の可能性大
- 語尾をやや上げる調子(疑問形) → 本気では言っていない
- 強調された”lovely”や”great” → 本当にそう思っているとは限らない
4.2 曖昧な表現が増えたら「拒絶のサイン」
- 「たぶん」「もしかしたら」「少し」「ある程度」などの副詞が多くなると、本心ではあまり賛成していないことが多い。
第5章:イギリス人と建設的にコミュニケーションをとる方法
5.1 相手のトーンや言葉を鏡のように使う
イギリス人は「控えめ」なスタイルを好むため、自己主張が強すぎると嫌悪感を持たれることも。まずは相手と似たトーンや言葉遣いで応じることで信頼を築く。
5.2 ダイレクトに聞きたいときの「ソフトな工夫」
- ❌「What do you really think?」(本音は?)
- ✅「Do you think there’s anything we could improve on here?」(改善点はありますか?)
間接的にでも、本音を聞き出せる表現を使うと良い。
5.3 皮肉・ユーモアに慣れる
イギリスのユーモアは「皮肉」や「自己卑下」が中心。深刻に受け取りすぎると誤解が生まれます。例えば:
- “Oh brilliant.”(まったく素晴らしい) → 実際には、うまくいっていない時の皮肉
ユーモアの裏にあるメッセージを読み取る練習も必要です。
第6章:逆に日本人がイギリス人に誤解されやすい場面とは?
6.1 無言での共感が通じない
日本人は「沈黙も会話の一部」と捉えがちですが、イギリスでは「意見がない」「無関心」と受け取られる可能性があります。
6.2 過度なへりくだりが不安を招く
日本流の「いえいえ、私など…」という謙遜が、イギリスでは「自信のない人」「能力に欠ける人」と見られることも。
第7章:まとめと実践アドバイス
イギリス人の表現は一見曖昧でつかみどころがありませんが、背景にあるのは配慮、上品さ、間接性という価値観。これを理解した上で、
- 曖昧な表現を逐語的に捉えず、行間を読む
- 「反対意見は前置きのあとに来る」と心得る
- 曖昧な表現=No の可能性を意識する
といった対応が求められます。
また、皮肉やユーモアに惑わされず、相手のトーン・表情・文脈から意味を読み取る練習も有効です。
付録:覚えておきたいフレーズ集
| 表現 | 解釈のヒント |
|---|---|
| “Not bad at all.” | 実はかなり良い(肯定) |
| “It could be worse.” | 悪いけど仕方ない(妥協) |
| “If you say so.” | あまり納得していない |
| “Let’s agree to disagree.” | 平行線、議論終了 |
| “Quite good.” | あまり良くない(逆説的) |
おわりに
イギリス英語には「言わないことで語る」という高度なテクニックが詰まっています。それをただ「遠回しで分かりにくい」と捉えるのではなく、相手の文化的背景を理解し、自らも“言葉の間”を読む姿勢が大切です。
イギリス人とより良い関係を築くために、本記事の内容をぜひ日々の実践に活かしてみてください。


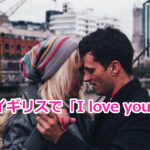







Comments