
はじめに
「イギリスでは労働者の権利がしっかり守られている」。これは多くの人が信じて疑わない常識のような認識である。特に日本など、労働者保護が薄いとされる国の視点から見ると、イギリスのような欧州諸国の労働環境は「進んでいる」「人権意識が高い」と称されることが多い。
だが、現実はどうだろうか。
筆者の親戚であるイギリス人女性が、先月、突如として雇用主から「今週の金曜日で終わりです」と一方的に解雇を言い渡された。事前の警告もなく、理由も明確に伝えられず、まさに「切り捨てられた」という形だった。この出来事は、イギリス社会において「労働者の権利」が本当に守られているのかという問いを改めて突きつけるものである。
本稿では、この具体的なケースを出発点として、イギリスにおける労働者の権利の制度とその実態、経済状況に左右される雇用の現実、さらには「人権とは何か」という根本的な問題について、考察していきたい。
イギリスの労働者保護制度 ― 法の建前と実態
イギリスには、一見すると労働者を保護するための法制度が整っている。例えば、以下のような権利が法的に保障されている。
- 最低賃金の保障(National Minimum Wage / National Living Wage)
- 不当解雇の保護(Unfair Dismissal Protection)
- 有給休暇の権利(年間28日間まで)
- 雇用契約書の提示義務
- 差別禁止(人種、性別、年齢、性的指向などに基づく)
- 労働組合加入の自由
しかし、これらの権利が「実際にどれほど守られているか」という点になると、話はまったく別だ。制度として存在することと、それが現場で機能していることは別次元の話であり、「法の建前」と「現実の運用」の間には、しばしば大きな隔たりがある。
上記の親戚の例のように、雇用主が突然解雇を言い渡すことは、形式的には不当解雇に該当する可能性がある。しかし、実際には次のような現実が立ちはだかる。
- 雇用期間が短ければ(2年未満)、不当解雇の保護が適用されない
- 解雇された側が訴えるには時間と費用がかかる
- 経済的な余裕がなければ泣き寝入りせざるを得ない
- 雇用主は「業績悪化」「ポジションの消滅」などの理由で合法的に解雇する手段がある
つまり、法的には守られていても、それが実際の生活レベルで反映されるとは限らないのだ。
「経済状況」によって変わる権利の価値
特に近年、イギリスを含む多くの国が景気後退の波にさらされている。COVID-19パンデミック、ウクライナ戦争、インフレ、高金利、エネルギー価格の高騰など、さまざまな要因が複合的に絡み合い、企業にとっては「生き残りをかけた経営」が常態化している。
このような中で、最初に削られるのが「人件費」だ。
企業はコスト削減の名のもとに、契約社員や派遣社員を真っ先に切り捨てる。正社員であっても業績不振を理由にリストラの対象となる。しかも、企業側は「合法的な手続き」を踏んで解雇を進めていくため、形式的には問題がないように見える。
だが、実際には、「権利」などあってないようなものである。企業は人間の生活や尊厳を守るよりも、自社の利益と生存を優先する。これは決して特定の企業に限った話ではなく、むしろ資本主義社会の構造的な問題であり、イギリスであろうと日本であろうと、同じことが起きている。
「人権」は景気のいい時の贅沢か?
この状況を見ると、「人権」や「労働者の保護」は、結局のところ「景気のいい時の贅沢品」ではないか、という疑念が湧いてくる。実際、以下のような声を現場ではよく耳にする。
- 「今は経済が苦しいから仕方がない」
- 「うちも人を雇い続ける余裕がない」
- 「会社が潰れたら元も子もない」
確かに、企業が潰れてしまえば、そこで働く人たち全員が職を失う。経営者の苦悩も理解できる。しかし、その論理がまかり通る限り、労働者の人権はいつまでも「景気に左右される消耗品」でしかない。
そもそも、「人権」という言葉は、どんな状況でも守られるべき最低限の価値を意味するはずだ。景気が悪くなったからといって、それが軽視されるならば、その社会は「人権を持つ人間」ではなく「生産性を持つ労働力」としてしか人を見ていないことになる。
「グローバル化」の影と雇用の流動化
さらに拍車をかけるのが「グローバル経済」の影響である。イギリスも例外ではなく、企業はグローバル競争の中で常に「コスト削減」「効率化」「人材の最適化」を求められる。結果として、非正規雇用の拡大、短期契約の常態化、そして「すぐに切れる人材」の使い捨てが加速する。
「フレキシブルな働き方」「自由な契約形態」という美名の裏で、実際には労働者が一方的に不安定な立場に置かれているのである。
一方、労働組合の力も年々弱まってきており、かつてのようにストライキや交渉で強い影響力を持つことは難しくなっている。特に民間セクターでは、組合に加入すること自体が少なくなり、団体交渉による権利確保は形骸化している。
「世界中どこでも同じ」という現実
イギリスに限らず、日本、アメリカ、アジア諸国、どこを見ても、労働者の不安定さと企業の論理優先は変わらない。違うのは、法制度の形式や表現の仕方であって、根底にある「企業中心の社会構造」は共通している。
つまり、「イギリスだから安心」「欧州だから人権が守られる」というイメージは幻想であり、結局のところ、世界中どこでも「企業が生き残るためには、人権よりも利益を優先する」現実があるのだ。
おわりに ― 問われるのは制度ではなく価値観
制度は整っていても、現実がそれに追いついていなければ意味がない。企業の論理がすべてを凌駕し、景気が悪くなれば人権が削られるような社会では、本当の意味での「労働者の権利」は存在しない。
求められるのは、制度の整備ではなく、「人間をどう見るか」という社会全体の価値観の再構築である。「労働者=コスト」ではなく、「労働者=社会の一員であり、尊厳を持った存在」として捉える視点こそが、今もっとも必要とされているのではないか。
イギリスのような先進国でさえ、経済状況によってあっさりと人権が踏みにじられる。この事実は、「労働者の人権」が制度だけで守れるものではなく、社会全体の意識に根ざすものであることを、私たちに強く突きつけている。






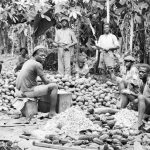



Comments