
英国人がトランプ前大統領を嫌っているというのは、もはや周知の事実だろう。風刺番組では彼の発言や振る舞いをネタにしたパロディが日常的に登場し、保守層でさえ「彼はアメリカの恥だ」と嘆く声を耳にすることも珍しくない。ロンドンでテレビにトランプが映ると顔をしかめ、チャンネルを変えるという市民は少なくない。だが、皮肉なことに——いや、だからこそ、と言うべきか——イギリス政府は、結局アメリカの意向には逆らえない。
たとえ相手がトランプであっても、あるいはその政策がどれほど利己的であっても、イギリスが「NO」と言うのは難しい。戦後ずっと「特別な関係(Special Relationship)」を謳いながらも、現実はアメリカの外交的従属国のような立場に甘んじている。実のところ、その構図は日本とほとんど変わらないのだ。
テレビを変えても外交は変わらない
ドナルド・トランプが2016年に大統領に選ばれた際、イギリス国内ではある種のパニックが広がった。「まさかあの男が……」という驚愕とともに、メディアや識者からはアメリカの衰退を示す徴候として分析され、政治的なジョークとして扱われることも多かった。
だが、イギリス政府にとっては笑い話では済まされなかった。ブレグジット(EU離脱)という自国の将来を左右するプロジェクトを抱えていたイギリスにとって、最も重要な貿易相手国であるアメリカとの関係は、生命線と言っていいほどに重要だった。EUという「後ろ盾」を自ら手放した今、イギリスは文字通り米国という大国の機嫌を取るしかない立場にあった。
トランプの外交方針がどれだけ一方的であっても、「アメリカ・ファースト」を押し通して他国の立場を軽視しようとも、イギリスにはそれに反論するだけの余地も、勇気もなかった。たとえ市民が彼を「テレビから消した」としても、ホワイトホール(英官庁街)はワシントンの指示を無視できなかったのである。
「特別な関係」という幻想
イギリスがしばしば口にする「特別な関係」という表現は、冷戦期から続く米英同盟の象徴である。軍事的にはNATOを通じて緊密に連携し、文化的にも英語圏同士として強いつながりを持つ。だが、この言葉がしばしば皮肉交じりに使われるのには理由がある。
現実の米英関係は、対等なパートナーというよりは、アメリカ主導の国際秩序における「忠実な副官」としてのイギリスの姿を映し出している。イラク戦争のときもそうだった。アメリカが「大量破壊兵器」の存在を理由に戦争を仕掛けると、ブレア首相は真っ先にそれを支持し、結果としてイギリスは甚大な外交的信用を失った。だが、ブッシュ政権に逆らうという選択肢は当時のイギリスには存在しなかったのである。
この「従属的忠誠」の構造は、トランプ政権下でもまったく変わらなかった。イラン核合意の離脱、WHOへの資金停止、気候変動協定からの脱退といった一方的な政策決定に対し、イギリスは何度も「懸念」を表明したが、最終的にはアメリカに同調せざるを得なかった。
日本と重なる「従属の構造」
こうしたイギリスの姿は、実のところ日本の対米外交と極めて似通っている。日本もまた、建前上は「対等な同盟国」でありながら、現実には米軍基地の存在や安保条約の制約のもと、アメリカの顔色をうかがわざるを得ない立場にある。
イギリスと日本は共に、「敗戦国」として戦後にアメリカの庇護を受けてきた歴史的背景を持つ。そして何より、アメリカに代わる外交的な「後ろ盾」を持たないという点が、両国をしてアメリカへの従属を不可避にしている。日本はアジアで孤立しないため、イギリスはブレグジット後の世界で自国の影響力を保つために、どうしてもアメリカに頼らざるを得ないのだ。
これが仮にオバマやバイデンといった穏健派の大統領なら、まだ「理念」を共有する同盟としての幻想が保たれる。だが、トランプのように自国の利益しか見ていない指導者に対しても忠実でいなければならないとなると、それは同盟ではなく、主従の関係と言うしかない。
「嫌い」と「従う」は両立する
これは奇妙な事実だが、国家の外交というものは、国民感情や倫理観とは無関係に進められる。「嫌いだから関わりたくない」と思っても、国の将来がその「嫌いな相手」に握られているとすれば、政治はそれを受け入れるしかない。
イギリス国民の大多数がトランプを嫌っていた。大統領としての品位、差別的な発言、暴力的なデモへの扇動。どれをとっても「民主主義のリーダー」にふさわしくないと考えられていた。だが、ボリス・ジョンソン首相はそのトランプと笑顔で握手を交わし、自由貿易協定の可能性を模索し続けた。
皮肉なことに、ボリス自身もまた「イギリス版トランプ」と評された政治家である。ポピュリズムを利用し、EUからの離脱を推進し、事実をねじ曲げるパフォーマンスで支持を得た。だからこそトランプとの共鳴が成立したとも言えるし、国民がその二人を並べて批判するのも当然だった。
だが、それでも政府はアメリカに従う。それは経済的な依存の構造が変わらない限り、どれだけ政権が変わっても続いていく運命なのだ。
今も続く「見えない占領」
イギリスも日本も、第二次大戦後の「西側陣営」に取り込まれた国家であり、冷戦構造の中でアメリカの外交戦略の一部として機能してきた。米軍基地こそイギリス本土には少ないが、情報機関、核兵器システム、金融ネットワークといった「見えない部分」でのアメリカの影響力は極めて強い。
サイバーセキュリティ、スパイ活動、経済制裁、ドル依存体制。いずれもイギリスが単独で決定できる事項ではない。アメリカが制裁すれば、イギリスも追随する。アメリカが禁輸すれば、イギリスも逆らえない。
表面的には「独立国家」だが、実質的にはアメリカという帝国の「属領」としての性格を持っている。これが「ポスト帝国」のイギリスの現実なのだ。
結論:アメリカを直視できない「中間国」の苦悩
日本とイギリス。この二つの国には距離も文化も違いがあるが、「超大国アメリカの顔色を伺う」という点においては驚くほど共通している。しかも、その相手がドナルド・トランプのような分断と強権を象徴する人物であったとしても、逆らえない構造は変わらなかった。
いくら市民がチャンネルを変えても、テレビを消しても、現実は変わらない。外交とは「好き嫌い」では動かない。そして、「NO」と言えない構造のもとにいる限り、どれだけ表面上の変化があっても、アメリカに逆らえない立場は続いていく。
イギリスがトランプを嫌っていた? それは間違いない。だが、いざとなったときにアメリカに従うしかなかったという点で、日本と何ら変わらないのである。

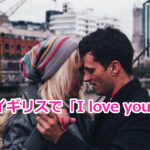








Comments