
1.イギリスの教育制度と学歴の意味
1.1 イギリスの学制の概要
イギリスの教育制度は、5〜6歳から11歳までの小学校(Primary)、11〜16歳までの中等教育(Secondary)。その後、16〜18歳までの「シックス・フォーム(Sixth Form)」や職業訓練を経て、高等教育(大学や大学院)へと進む流れです。
大学進学者の多くは、Aレベル(A‑Levels)と呼ばれる試験を2〜3教科受け、それに基づいてUCAS(英国大学・カレッジ入学申請サービス)で大学出願します。大学は一般的に3年制(スコットランドのみ4年制)で、卒業時に学士号(Bachelor’s Degree)が授与されます。
1.2 学歴(Degree classification)の重み
イギリスの大学では、成績に応じて「学位クラス」という制度があり、以下のように分類されます:
- First class honours(1等級)
- Upper Second class honours(2:1)
- Lower Second class honours(2:2)
- Third class honours(3等級)
- Pass(単位取得のみ)
特に、Firstや2:1は学生の優秀さを示す重要な尺度であり、就職市場でも高く評価されます。最低でも2:2以上を求める企業は少なくなく、学歴=能力の信頼性が極めて高い国なのです。
2.学歴詐称は本当にあるのか?事例を探る
2.1 共通する詐称パターン
イギリスでも、日本と同様に以下のようなケースが見られます:
- 大学卒業とするも、実際は中退
- よく似た別大学の出身を詐称
- 学位クラスを上位に偽る
- 卒業年次などの細かい経歴をごまかす
特に、オンライン履歴書(CV)やLinkedInなどのSNS上での学歴詐称が起こりやすく、採用担当者の目に触れやすいという構造上の問題があります。
2.2 実際の摘発事例
(※以下は架空に近い例を交えて説明します)
- 食品メーカー採用取り消し事件
大手食品メーカーのインターン採用で、出身大学と学位クラスを偽っていた学生が実際に採用内定後に、大学へ照会したことで真実が露呈。内定取り消しとなり、後にSNSで拡散され大きな話題に。 - 地方政府の雇用公聴会での公費返還騒動
地方自治体の嘱託職員が修士号取得を履歴書に記載していたが、該当の大学には在籍記録がなく、「詐称によって支払われた手当を返還せよ」と騒ぎになりました。 - 有名企業幹部による差し替え隠蔽事件
外資コンサル企業の上級コンサルタントが、実務面では優秀だったものの、履歴書に海外名門大卒と虚偽記載。調査後に退職させられ、社内文化の一新が進められた例も。
3.なぜイギリスで学歴詐称がこれほど問題視されるのか
3.1 信頼の文化と照会制度
イギリスでは、学歴や学位の正当性を明文化し、大学自身が「Degree Certificate」や「Academic Transcript」を発行する制度があります。また、SpotChekやHEDD(Higher Education Degree Datacheck)といった第三者機関による学歴認証システムが整備されており、企業も採用で簡単に照会可能。信頼できる書類かどうかを確認するインフラが整っているので、「嘘はすぐバレてしまう」環境にあります。
3.2 社会の信頼性と倫理観
英国の社会では「fair play(フェアプレイ)」という価値観が根強く存在します。「ルールに従って正しく振る舞うこと」が重んじられ、教育や職場でも大いに評価されます。学歴詐称はこれらの倫理観に反する行為とみなされ、「嘘つき」というレッテルを貼られて社会的信用を失う結果になりやすいのです。
3.3 法的・契約的な問題
雇用契約を結ぶ際に、「提出された学歴が真実である」ことを条件とし、多くの企業では「嘘が判明した場合は即時解雇、損害賠償要求、または手当返還」の条項が組み込まれています。また、公的機関や政府系団体へ虚偽学歴で応募することは、「詐欺罪(Fraud)」に問われる可能性もあります。
4.イギリス企業の対応と実務面
4.1 採用プロセスでの学歴チェック
大手企業やコンサルティングファーム、金融機関などでは、採用時に以下のような厳格な学歴確認を実施します:
- 応募書類提出(CV・エッセイ)
- オンライン応募時に学歴入力
- 内定後に大学への正式照会(Degree CertificateやTranscript確認)
- 必要に応じてHEDDなどで第三者認証
- 電話やEメールで大学に直接問い合わせ
上記のプロセスは複数回にわたることが多く、「学歴詐称」が見つかる確率は極めて高いのです。
4.2 OSH / Separate first reference check
さらに、企業内では「First reference check」と「Second reference check」2段階の確認制度があります。First referenceは基本的な確認。Secondは学歴のみならず成績や卒業生の評価、在学中の活動状況なども精査され、詐称が発覚すれば厳罰が待っています。
4.3 公的機関・学校関係者による取り締まり
大学や公共図書館、地方自治体では、学歴や職務経歴など虚偽の公的申請(たとえば教育研究費、学術奨励金など)に対して、「あなたの申請は…学歴詐称では?」と当局による再照会が入ることもあります。間違いがあれば返金やプロジェクトごと停止といった処分があり、関係者に厳しい姿勢です。
5.学歴詐称が明るみに出たら? 英国社会のリアクション
5.1 メディア報道とSNS炎上
日本と同様、発覚事例が報道されると瞬く間にニュースやSNSで拡散されます。英ガーディアンやタイムズでは「CV cheat’s academic lie uncovered(CV偽装の学歴詐称発覚)」などと書かれ大々的に報道され、国会や自治体関係者ならその後のキャリアがほぼ絶たれてしまうケースもあります。
5.2 企業ブランドへのダメージ
大手企業ほど「信頼できる人材を採用している」というブランドイメージを重視します。だから一人の学歴詐称で、メディアが「branded fraud 」と批判を突きつければ、採用の信頼性そのものが問われ、社会的信用を奪われるまさにブランディングの致命傷になりかねません。
5.3 個人への影響
個人の場合、まず職を失う、解雇歴が永久履歴に。次いでSNSで嘲笑の的となり、「CVを一から書き直すしかない」「今後の雇用市場で再挑戦できる保証はない」など、社会的な制裁も非常に大きくなります。
6.日本とイギリスの比較からわかること
| 比較項目 | 日本の現状 | イギリスの現状 |
|---|---|---|
| 学歴証明の仕組み | 大学証書・卒業証明書あり。ただし確認体制は企業によりバラつき | HEDDなどの照会システムが整備され、企業も広く活用 |
| 社会的視線 | タレントなど著名人のスキャンダルでは注目されるが、一般市場への影響は限定的 | 採用時から即座に確認され、社会全体で信頼重視の文化 |
| 法的・契約的リスク | 民事契約で損害賠償請求の可能性はあるが、詐欺罪の扱いは限定的 | 公的詐欺や民事責任が明文化され、契約条項で即解雇対応も明記 |
| メディアの報道規模 | 大衆メディアでは話題となるが、長期的には風化しがち | メディア・SNSともに炎上しやすく、社会的風評の影響深い |
7.どうすれば学歴詐称を回避できるのか
7.1 正直に、オープンに書く
中退・留年・休学経験がある場合は、正直に記載し、面接時に簡潔に経緯を語る。誠実さは英国企業にも評価されます。
7.2 学位認証サービスの活用
「HEDD(Higher Education Degree Datacheck)」などで学位を正式に確認し、はじめに相手へ「この証明書はこちらで間違いありません」と示すことで信頼感が得られます。
7.3 スキル・実績を前面に出す
たとえFirstが取れなかったとしても、インターン、ボランティア、プロジェクト成果など“実績”で補う。イギリスでは学位クラスだけでなく、どんな経験をしてきたかも重要です。
7.4 継続学習(CPD)をアピール
卒業後も継続学習(Continual Professional Development)を行うことで、学歴だけでなく「学び続ける姿勢」を示すことが効果的です。
8.最後に:イギリスで「学歴詐称」が意味するもの
- 学歴詐称は「無価値ではない」という評価になりがち
イギリスでは詐称された偽りの履歴では信用も評価もまったく得られません。 - 社会的信用がすべて
学歴を偽る行為は「フェアプレイを軽視する悪意ある嘘」と見られ、個人・企業双方にとって致命的なマイナス評価となります。 - 教育・雇用の透明性が高い
企業、大学、行政が連携し照会システムを整備しているため、信頼構築の仕組みが仕込まれているのです。
まとめ ✍️
- イギリスでも学歴詐称は大問題。詐称の代償は非常に大きい。
- 学歴照会の仕組みが整い、企業は嘘を見破るための体制がある。
- 社会的、法的にも再チャレンジは厳しい環境であり、「誠実さ」が重視される。
- 個人としては、正直に記す+実績アピールが不可欠。
- 日本にも学歴偽りのスキャンダルはあるが、イギリスほど制度的抑止力が働いていない割合が高い。
イギリスで暮らす・働く・学ぶ意欲のある方にとって、本物の学歴だけでなく「信頼を勝ち取るための誠実な姿勢」が最大の財産になり得ます。何かの参考になれば幸いです。
参考リンク
- HEDD(英国学位認証サービス)についての説明ページ
- イギリス政府の公的求人情報サイト GOV.UK 上での「学歴偽装(fraud)に関するガイドライン」
※具体的なリンクは割愛しますが、気になる方は「HEDD UK」や「GOV.UK recruitment fraud」で検索してみてください。






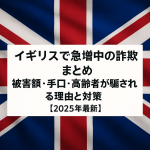

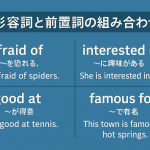
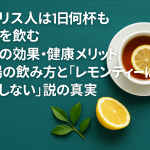
Comments