
1. そもそもの問いにある“直感”はどこから来るのか
この直感には少なくとも二つの背景があります。
(1) 同一化(identification)とジェンダー役割:思春期に入ると、子どもは同性親を「将来の自分像」として強く参照し、異性親とは距離を取りつつも承認を求めます。そのため、同性親が“被害者”だと映ると、子どもは加害側の異性親への怒りを強く感じやすい、という臨床現場の実感則が語られやすい。
(2) 進化心理学的な物語:男子は母親への保護本能に近い感情を、女子は父親への理想化や愛着を…といった物語が、俗流解説として広がりやすい。
ただし、これらは説明としての魅力が強いだけで、個別事例の多様さを十分に説明しきれないことに注意が必要です。
2. イギリスの制度と世論:歴史的・統計的な文脈
- 離婚制度の変遷:イングランド&ウェールズでは2022年に「ノーフォルト離婚(No-fault divorce)」が導入され、離婚時に特定の“有責(例:不貞)”を立証しなくてもよくなりました。これは、かつて離婚事由として「姦通(adultery)」がしばしば争点になっていた時代からの大きな変化です。制度が「誰が悪いか」を前面に出さなくなったことで、子どもが“どちらが悪者か”を一方的に刷り込まれる構図を緩和しうるという期待が語られてきました。
- 世論の傾向:英国の世論調査(例:YouGovなど)では、男女ともに配偶者の不貞を重大な背信とみなす傾向が強く、婚姻観はリベラル化しても「嘘」「隠蔽」「二重生活」への嫌悪は根強いことが繰り返し示されています。数値の振れ幅は年によってありますが、「浮気は間違いだ」とみなす割合は一貫して多数派です。
- 離婚理由と子ども:イギリスの家族支援団体(Relate 等)や家裁実務の周辺では、不貞そのものよりも、長期化した夫婦間葛藤・高葛藤離婚・親の片方による他方の悪魔化が、子どもの心理アウトカムを悪化させる要因として繰り返し指摘されています。つまり、「不貞=必ず重篤な影響」ではなく、それがどのように家庭内で扱われ、どんなコミュニケーションが為されたかが決定的です。
3. 心理学的に見えること:性差より“条件”
3-1. 愛着理論(Bowlby / Ainsworth)
イギリスで発展した愛着理論は、子どもにとって“予測可能で信頼できる養育反応”があるかを重視します。不貞の発覚は、子どもにとって「家の土台が揺れる」体感をもたらしやすいのですが、影響の大小は
- 親が感情的に崩壊し子どもを“代理パートナー”化してしまうか(過剰な愚痴吐きや巻き込み)、
- 家庭内のルーティンと情緒的安全が保たれるか、
- 事実の伝え方が年齢相応で、責任の所在を子どもに背負わせないか、
といった愛着の安定要因で大きく変わります。ここにはジェンダー差よりもケアの一貫性が効きます。
3-2. 家族システム論(Minuchin)
家族は**境界(boundaries)**の健全さが鍵です。不貞があると、親が子に機密の相談相手役を求めたり、**三角関係化(triangulation)**が起きやすく、これが長期の対人不安や罪悪感を残します。お父さんの不貞であれお母さんの不貞であれ、子が“どちらの味方につくか迫られる”状況が最悪で、ここでの圧力が“許せない”を固定化します。
3-3. 社会学・文化心理:ジェンダー役割期待
「男子は母を守る」「女子は父に理想を投影」といった役割期待は、英国でもメディアや同級生文化を通じて形を変えつつ存在します。思春期の同一化の相手(男子なら父、女子なら母)に強い羞恥や裏切りを感じるケースもあれば、逆に異性親への失望が恋愛観に長く影を落とすケースもある。つまり、反応は“逆”にも“同じ”にも出るため、単純な性差モデルで予測するのは困難です。
3-4. 発達段階の効果
- 学童期:善悪が二分法になりがちで、嘘・隠蔽への反発が強い。
- 思春期前期~中期:自我が鋭敏になり、“親の不完全さ”をどう統合するかが課題。不貞を“人格全否定”と重ねやすい時期。
- 後期思春期~青年期:恋愛・性・倫理観を自分で編み直すフェーズ。不貞に触れた家族史は、自分の境界設定や信頼の築き方に長期的影響を及ぼしやすい。
3-5. 研究が示す“より強い指標”
学術的レビューでは、(A) 家庭内の葛藤の激しさ・長さ、(B) DV や心理的虐待の有無、(C) 親のメンタルヘルス(抑うつ・依存等)、(D) 経済・住居の不安定化、(E) 共同養育(co-parenting)の質が、子どもの適応を最も説明します。不貞そのものは一要因に過ぎないという位置づけが妥当です。
4. 「父の不貞に娘が厳しく、母の不貞に息子が厳しい」は本当か?
臨床現場の証言としては**“その傾向が見られることがある”**のは事実です。理由としては、
- 異性親の裏切り=自分の将来の恋愛モデルの破綻として感じやすい場合がある。
- 同性親の痛みを背負う構図になり、怒りを増幅させる。
- 家庭内での語られ方が偏っている(例:父の不貞は“男はそういうもの”と軽視され、母の不貞は“母性の裏切り”として過度に糾弾される)など、文化的ダブルスタンダードが子どもの評価を歪める。
しかし、体系的な量的研究で強固に確認された一般則というよりは、語られ方(narrative)や家族内の力学が作り出す“見かけ上の傾向”であることが多い。英国でも、宗教・地域・階層・移民背景によって語りの文脈は多様です。
5. イギリス社会固有の事情:何が子どもに効きやすいか
- 支援アクセスの良さ/悪さ:NHSや学校カウンセリング、チャリティ(Relate, Childline等)へのアクセス可否はアウトカムを左右します。第三者が早期に介入できると、怒りの固定化を防ぎやすい。
- プライバシー文化と“穏やかな冷戦”:英国は「家庭のことは家庭で」という配慮が働きやすい一方、表面上の穏やかさの裏で長期の情緒的断絶が続くと、子どもは慢性的な不安と孤立を抱えやすい。これは“爆発型の喧嘩”以上に影響が長引くことがある。
- 学校・同輩の影響:英国の若者文化では、SNS を通じたプライバシー暴露やゴシップの拡散が、家庭の出来事を同級生の評価軸に乗せてしまう。羞恥と怒りが結びつくと、“許せない”感情は一層強化されます。
6. 実務からの示唆:親のふるまいが鍵
6-1. 伝え方
- 年齢相応に、事実関係を最小限・誠実に。性的詳細や相手の人格攻撃は避ける。
- 責任の所在を子どもに背負わせない(「あなたのために我慢している」等の罪悪感植え付けは禁物)。
- “これからどう安定を取り戻すか”の具体(住む場所、生活リズム、学校の継続)を示す。
6-2. 共同養育(co-parenting)
- 相手親の評価を子どもの前で下げない。子どもは“親の半分は自分”と感じるため、相手親の全否定は自己否定として返ってくる。
- 連絡ルール・引き渡し・学校行事の対応など、実務の合意が情緒の安定に直結する。
6-3. カウンセリング
- 学校カウンセラーや若者向けサービス(若者センター、チャリティ団体)を早めに案内。
- 保護者同席セッションで、子どもが安心して怒りや不信を言語化できる場を確保する。
- 思春期後期には、恋愛・性・境界の築き方を扱う心理教育が有効。
7. “許せない”が長期化するトリガーと緩衝因子
トリガー
- 長期の嘘・二重生活・金銭問題の露呈
- 親の一方が“被害者役”を過剰演じ、他方の悪魔化を子に求める
- 友人・親族・SNS 経由での二次暴露(羞恥の再活性化)
緩衝因子
- 学校生活・クラブ活動など家庭外の安定拠点
- 三者面談的にルールを可視化(連絡頻度、面会計画、怒鳴り合いの回避)
- 子が両親に言いにくいことを言える大人(親戚、教員、カウンセラー)の存在
8. 男子×母、女子×父で“より強く出るケース”の具体
臨床的には、以下の条件が重なると**“定型っぽく見える”**動きが出ます。
- 男子×母:シングルマザー家庭で母が主要ケアラーの場合、母の不在・嘘は生活の即時不安に直結しやすく、“守る相手の失望”が怒りに転化。
- 女子×父:父が“規範”の象徴で、家庭外で評判が良いほど、家庭内での不一致(ダブルバインド)が羞恥と裏切りを増幅。
ただしこれらはあくまで条件が揃ったときに見えやすい傾向であり、逆の事例も珍しくありません。例えば、父の不貞に対して息子が強く拒否し「将来は絶対に同じことをしない」と誓うケース、母の不貞に対して娘が「母の人生を取り戻す選択だった」と再解釈して関係修復が進むケースもあります。
9. 実務的ガイド:家庭内でできる5つのこと
- “事実”と“感情”を分けて語る
「起きたこと」と「あなたがどう感じているか」を分けて伝える。 - 境界線の明確化
子どもに“相手の監視役”“スパイ”をさせない。大人の問題は大人が扱う。 - 共通メッセージ
両親で合意した短いメッセージを用意(例:「あなたのせいではない」「学校や友達は変えない」)。 - タイムラインの見通し
引っ越し・面会・休暇の予定など、先の予定を早めに共有。予測可能性は安心を生む。 - 第三者の伴走
学校、GP、地域のカウンセリング、信頼できる親族――**家庭外の支えを“制度化”**する。
10. まとめ:問いへの答え
- 定説としての性差(女子→父を許せない/男子→母を許せない)は確認しがたい。
- 英国の制度変化(ノーフォルト離婚)や世論傾向は、「誰が悪い」で決着させるより、共同養育と子の安定を優先する方向にあります。
- 子どもの適応を最も左右するのは、不貞そのものではなく、その後のコミュニケーション、葛藤の扱い、生活安定、第三者支援です。
- したがって家庭での優先順位は、(1)誠実で年齢相応の伝え方、(2)悪魔化の回避、(3)共同養育の実務化、(4)外部支援の活用。
- “許せない”という感情は否定すべきものではなく、安全な場で言語化・整理されるほど、やがて「許す/許さない」以外の関係再構築(境界、信頼の新しい形)に進みやすいことが、臨床と研究の接点から見えてきます。




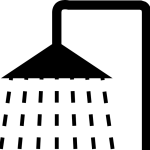




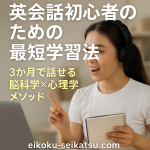
Comments