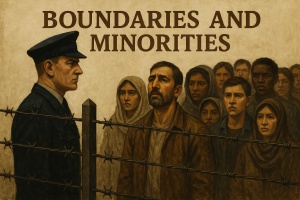
歴史を振り返ると、人間社会はしばしば「多数派」と「少数派」という構図に揺さぶられてきた。マイノリティは、単に数が少ないという理由だけで「異質な存在」として扱われ、時に反逆者、時に脅威としてレッテルを貼られてきた。そうすることで、暴力や差別の正当化が可能になり、支配体制を守ろうとする多数派の心理が働いたのだ。
イギリスにおける移民への反発も、その延長線上にある。経済的な不安や社会制度への負担が強調される一方で、根底には「外部からの異種」に対する拒否反応が存在する。日本においても同様で、均質性を重んじる文化の中では「外から来た人」は容易に「内側」へ取り込まれにくい。結果として、移民はしばしば社会の周縁に追いやられ、摩擦や排斥の対象となる。
興味深いのは、多くの人々が「移民は自分たちの生活を脅かす存在」と警戒する一方で、支配層――実際には人口の1%にも満たない人々――による経済的・政治的支配にはほとんど疑問を抱かない点である。異質な少数派への拒絶は容易に可視化できるが、構造的な支配には目が向けられない。その盲点こそ、国家が自らの統治を維持するうえでの最大の武器かもしれない。
では、人々が平穏に暮らすためには「イギリス人はイギリスで、日本人は日本で」という自国中心主義へと回帰するしかないのだろうか。確かに世界は、グローバル化の後退とともに「自国ファースト」的な風潮へ傾いているように見える。しかし、その先にあるのは閉じられた安定ではなく、さらなる断絶かもしれない。
マイノリティとマジョリティの対立は、単なる国境や民族の問題ではなく、人間社会そのものが抱える根源的な矛盾である。異質さを恐れ排除するのか、それともそれを契機に新しい共存の形を模索するのか――。その選択によって、21世紀の国家と社会の未来は大きく左右されるだろう。








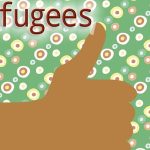

Comments