
1. ある夜、燃える光の中で
2013年、イングランド南西部の街ブリストル。
夜空を赤く染めた炎の中で、ひとりの男が命を落とした。
彼の名は ビジャン・エブラヒミ。
イランから移り住み、静かに暮らしていた障がいを持つ男性だった。
しかし、ある日を境に近隣住民から「子どもを盗撮している変態」だと噂される。
証拠はなかった。
彼が撮っていたのは、自分の庭に無断で入り込む若者たちの映像。
つまり、自分を守るための記録だった。
だが、誰も信じなかった。
警察に助けを求めても「被害妄想だ」と突き放され、
その数日後、怒りに駆られた住民たちは彼を家から引きずり出し、
殴り殺し、ガソリンをかけて燃やした。
「子どもを守るためにやったんだ」——主犯の男はそう語った。
彼の中では、それが**“正義”**だった。
2. 正義の名を借りた暴力
この事件は、いわゆる「自警行為」の典型だ。
警察への不信、SNSの噂、そして「守るべきものを守る」という共同体の幻想。
それらが重なり合い、“正義”が暴力へと変質した瞬間だった。
事件後、主犯の男は殺人罪で**終身刑(最低18年服役)**を宣告された。
だが、判決後も街には奇妙な同情が流れた。
「やり方は間違っていたが、気持ちは分かる」——そう語る声も少なくなかった。
そこには、善と悪の境界線があいまいになる恐怖があった。
人々は「正しいこと」をしたつもりだった。
だが彼らが燃やしたのは、ひとりの命だけでなく、**“正義そのもの”**だったのだ。
3. 復讐と正義の境界
人は不条理を前にすると、「正義を取り戻したい」と強く願う。
娘が暴行された父親が加害者に刃を向ける。
被害者の無念を思い、怒りを爆発させる。
その感情はあまりにも人間的で、痛いほど理解できる。
だがその瞬間、私たちは気づかぬうちに
**“被害者の側に立つ怪物”**へと変わっているのかもしれない。
復讐は一瞬の満足を与える。
だが、それは社会が積み上げてきた理性という防波堤を壊す行為でもある。
そして残るのは、「自分もまた壊れた」という事実だけだ。
4. 正義とは、誰のためのものか
エブラヒミ事件のあと、英国の裁判官はこう語った。
「正義とは、怒りの中ではなく、冷静な手続きの中にこそある。」
その言葉は冷酷にも聞こえる。
しかしそれは、人間の感情を否定するためではない。
むしろ、感情に飲み込まれたときにこそ
人間を守る仕組みが必要だという意味だ。
もし「正義」を個人の怒りに任せれば、
それは国家の暴力にも、群衆の狂気にも変わる。
かつて魔女狩りをした人々も、同じように言った。
「悪を滅ぼすためだ」と。
だが、今の私たちはその時代を“狂気”と呼ぶ。
正義は、人の手には余る力だ。
だからこそ社会は、裁く権利を個人から取り上げ、
制度の中に閉じ込めた。
それが文明の証であり、人間の理性の最後の砦なのだ。
5. それでも、人は怒りを手放せない
それでも。
自分の子どもが理不尽な暴力に遭ったとき、
誰が冷静でいられるだろうか。
誰が「法に任せよう」と言えるだろうか。
怒りは人間の自然な感情だ。
だが、それを行動に移すかどうかは理性と信念の問題だ。
“正義”とは、誰かを罰することではない。
「怒りに支配されないこと」こそが、本当の正義ではないだろうか。
6. 終わりに
燃やされたビジャン・エブラヒミは、
最後まで「自分は無実だ」と訴えていた。
だが、その声を誰も聞こうとしなかった。
彼を殺したのは、ひとりの男の拳だけではない。
それは、「自分は正しい」と信じた人々の沈黙と、
“正義”という名の熱狂だった。
もし正義が人を救うための言葉なら、
私たちはその力を、もう一度慎重に使わなければならない。
正義とは、人を裁く力ではなく、人を止める勇気である。









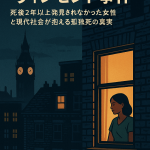
Comments