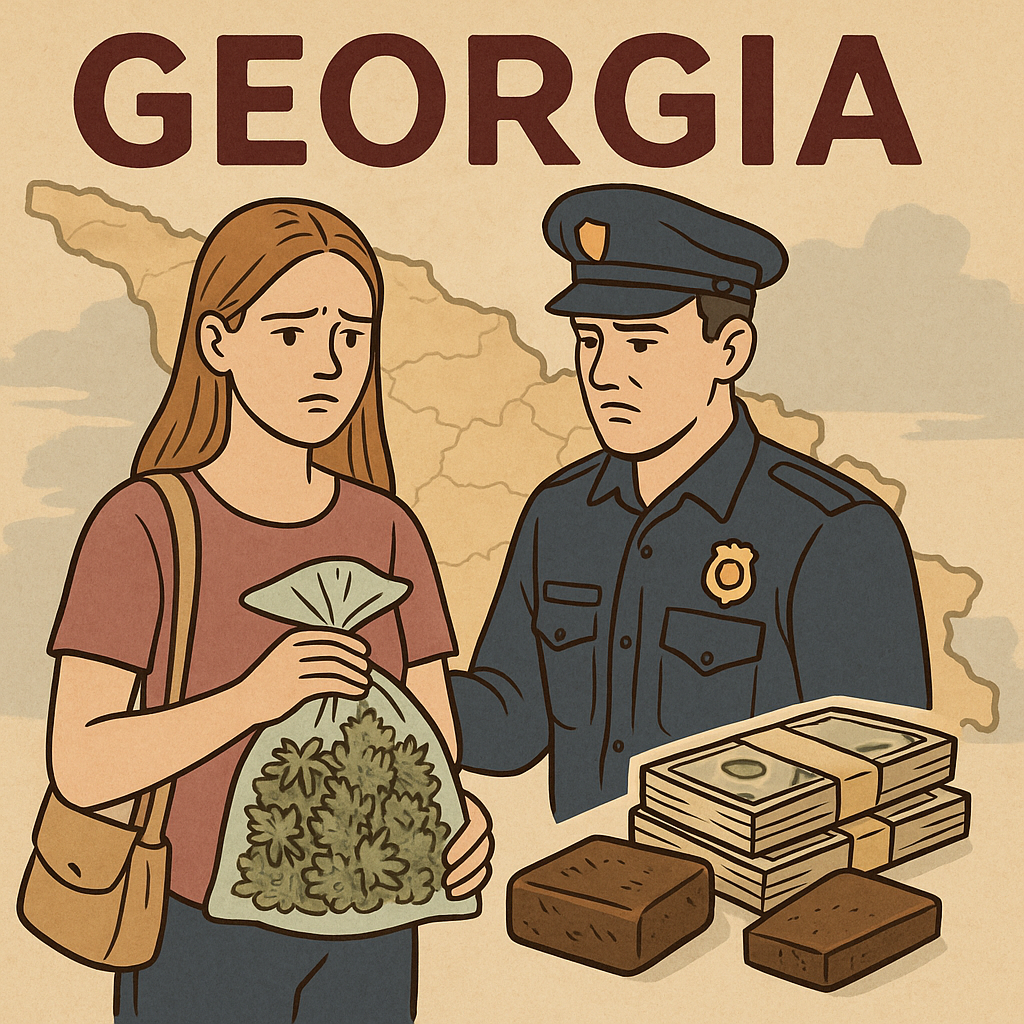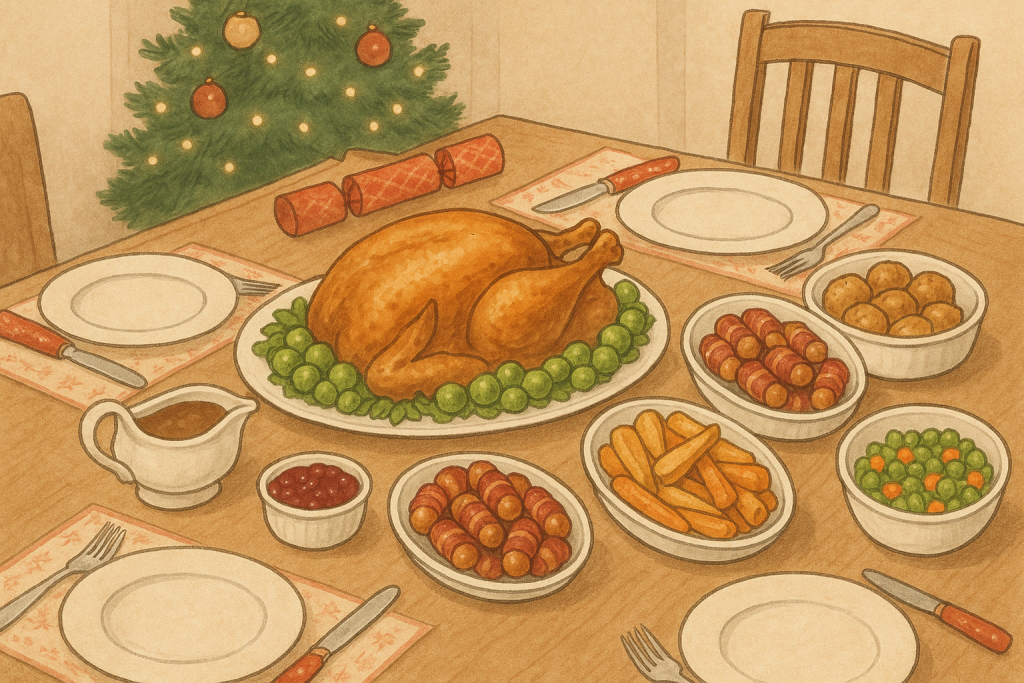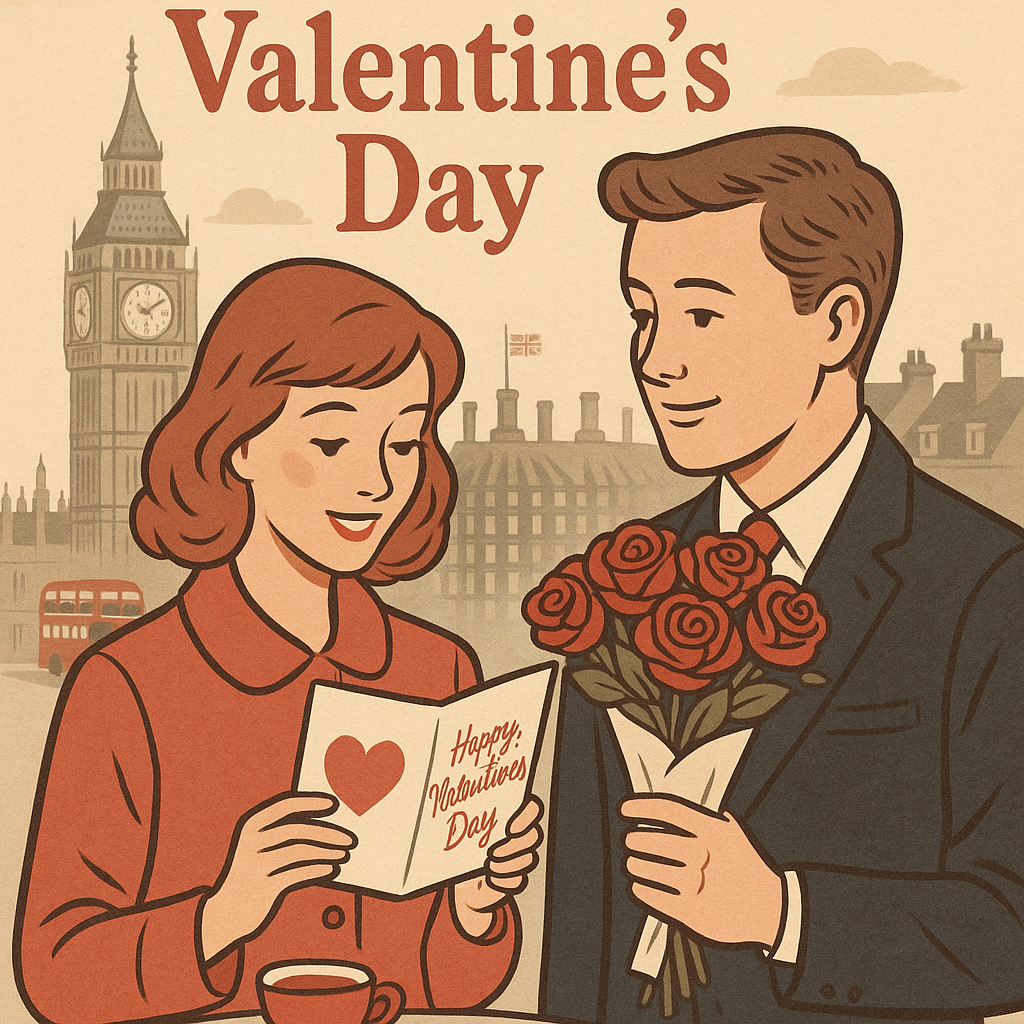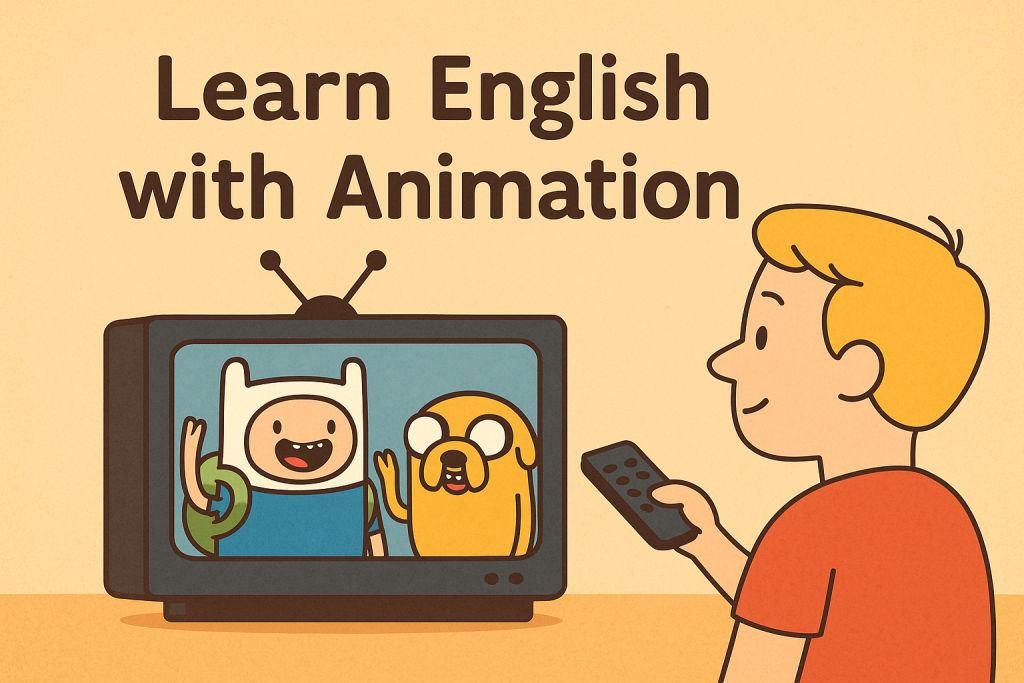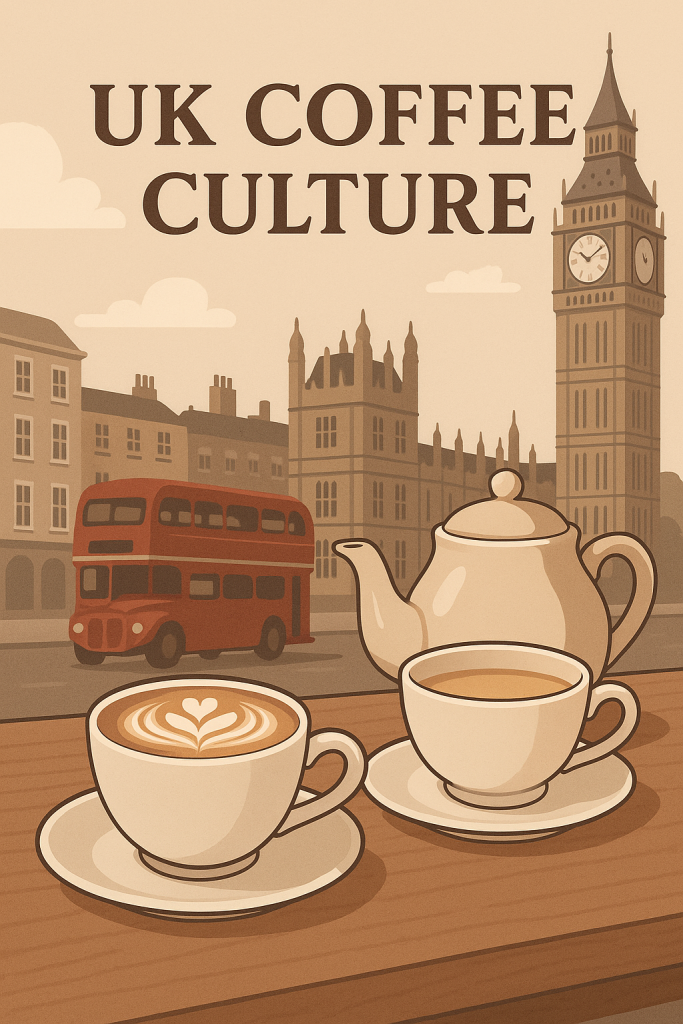…
Author:admin
英国人女性がジョージアで大麻密輸容疑 家族が2,600万円を支払い釈放――「ジョージアという謎の国」から見えること
…
イギリスで起きた無差別殺傷事件の背景
…
ロンドン賃貸市場に「失速」の兆し
…
イギリスのクリスマス定番ドリンクといえばモルドワイン(Mulled Wine)
…
イギリスのクリスマスディナー徹底ガイド|伝統メニュー・食卓マナー・日本での再現アイデア
…
バレンタインデーについて
…
アニメで楽しく英語を学ぶ!『Adventure Time』で身につく自然な英会話リスニング術
…
イギリス人は紅茶よりコーヒー好き
…
なぜロンドン株式市場は地味に見えるのか?|ニューヨーク・東京が活況の中で遅れを取る理由【2025年最新版】
…