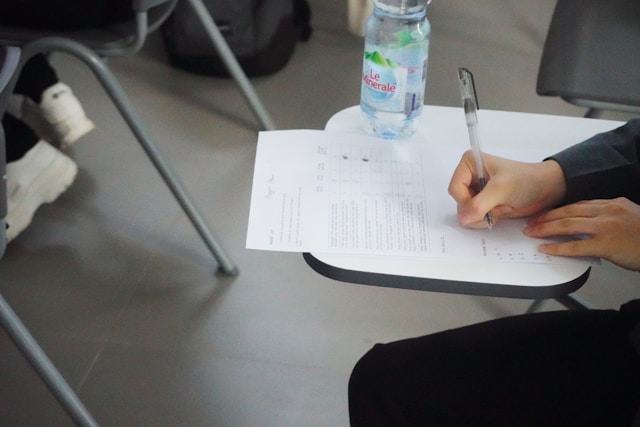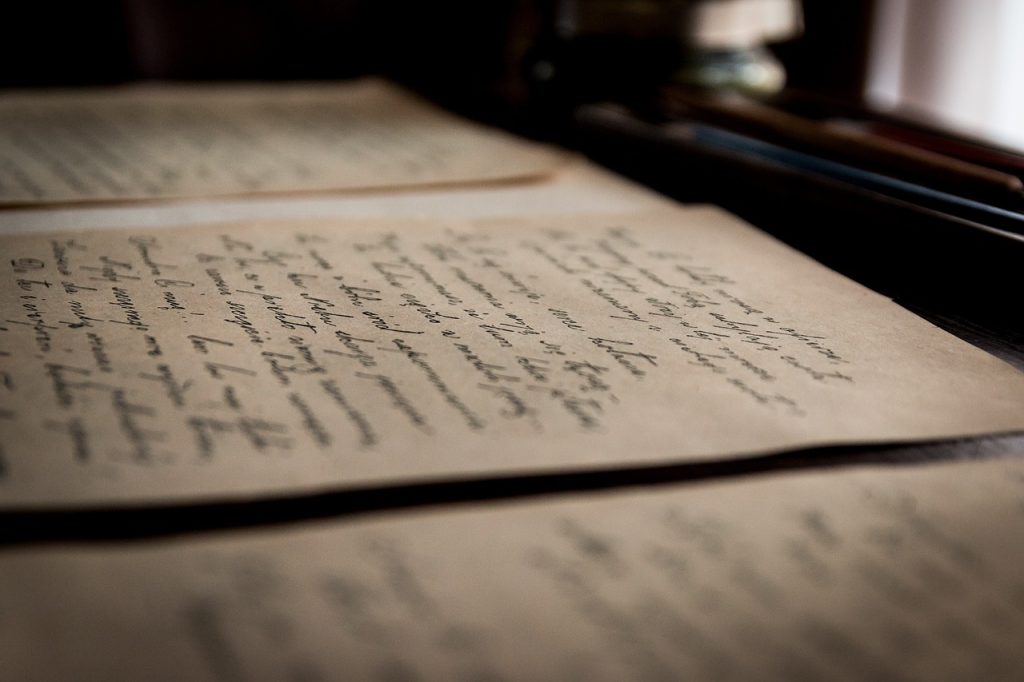…
教育
イギリスの学校制度や教育事情をわかりやすく紹介しています。ナーサリー(幼稚園)から小学校・中学・高校・大学までの教育システムの仕組み、学期制度や入学時期、学費、制服、そして留学や現地校・インターナショナルスクールの違いなどを詳しく解説。実際に子どもを英国の学校へ通わせている家庭の体験談も交え、在英日本人が安心して教育を選べるようサポートします。これから留学を考える方にも役立つ情報を発信しています。
なぜ日本人は英語が上手くならないのか?― 日本の英語教育と文化的背景を徹底解剖 ―
…
イギリスの学校における校則とその違反時の処罰制度
…
なぜイギリスの学校は頻繁に休みがあっても教育レベルが高いのか?
…
イギリスにおける入試制度と私立学校の実態
…
イギリスにおける大学進学率とその意味:学歴社会の現在地
…
イギリスにおける大学格差の実態:名門と三流大学の明確な違い
…
イギリスの学校でも作文というものはあるのか
…
イギリスの子育て文化と少年犯罪──「自由」と「しつけ」の間で揺れる親たちへ
…
オックスフォード大学の学生構成が変化!BME学生の割合が急増する理由とは?
…