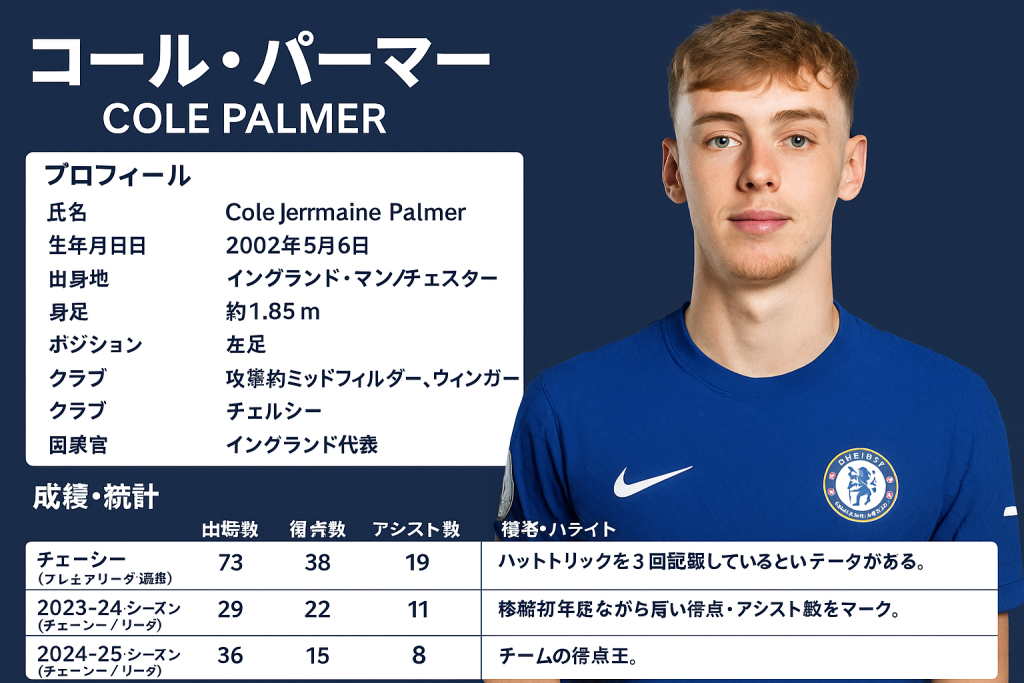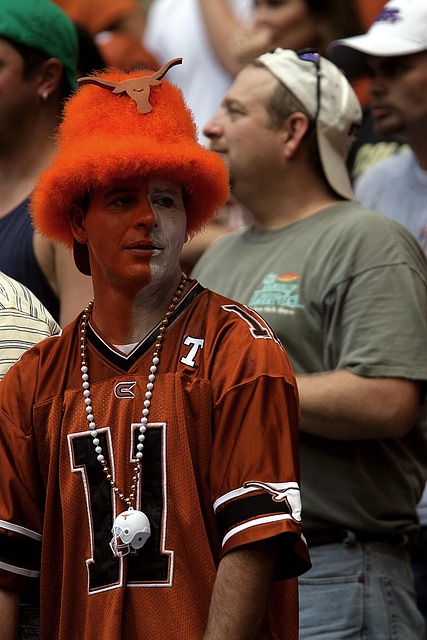…
サッカー
英国生活サイトが注目するイギリス出身のサッカー選手:コール・パーマー
…
英国生活サイトが今最も注目するイギリス出身のサッカー選手:デクラン・ライス
…
「勝てなければ即クビ」―イギリスのサッカーマネージャーという椅子取りゲーム
…
イギリスのサッカーファンを悩ます観戦コスト:チケット・グッズ・配信サービスの実態
…
サッカー大国イギリス:誰もが気軽にサッカーを楽しめる場所とは?
…
イギリスの草サッカー文化とは? 日本の草野球との違いと共通点を比較
…
夢を現実に変えるには?プロサッカー選手になる確率とその先の未来
…
イギリスにおける公認ギャンブルの全貌:多様性・収益・社会的責任の最前線
…
プレミアリーグ選手の年俸はいくら?平均・最高年俸とその背景を徹底解説!
…