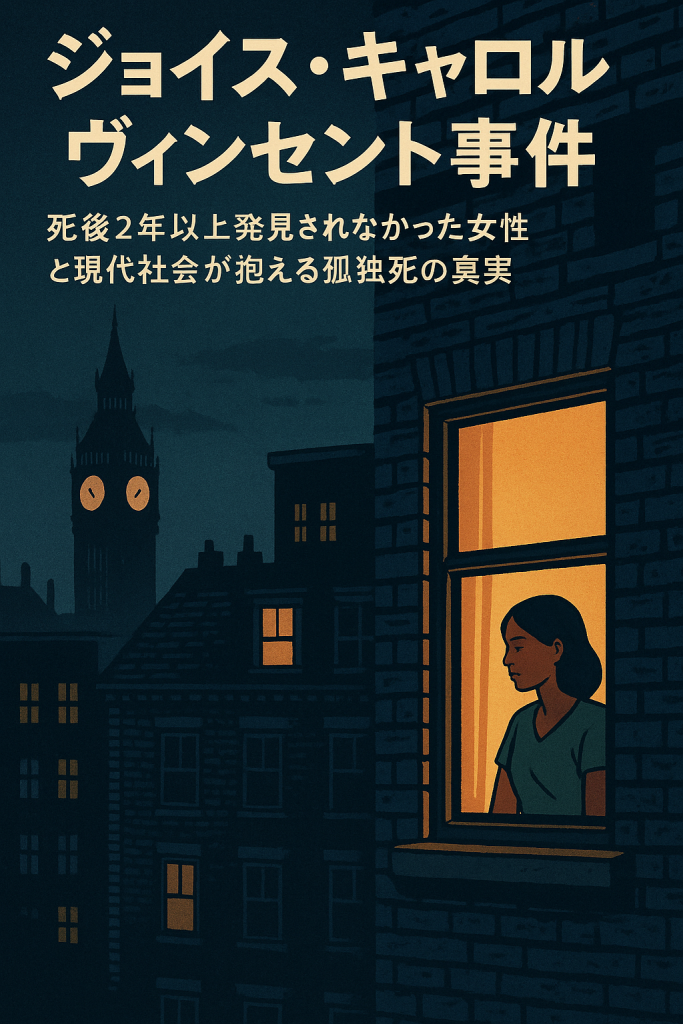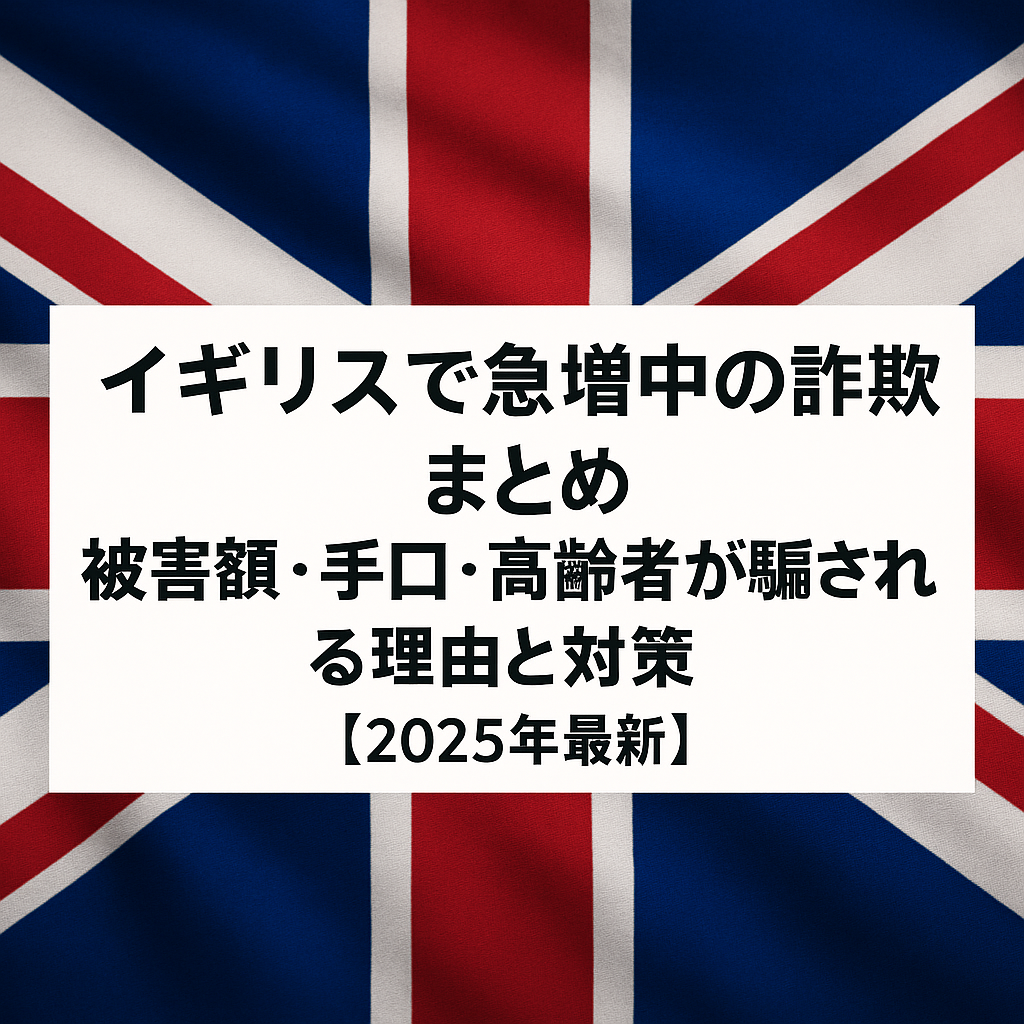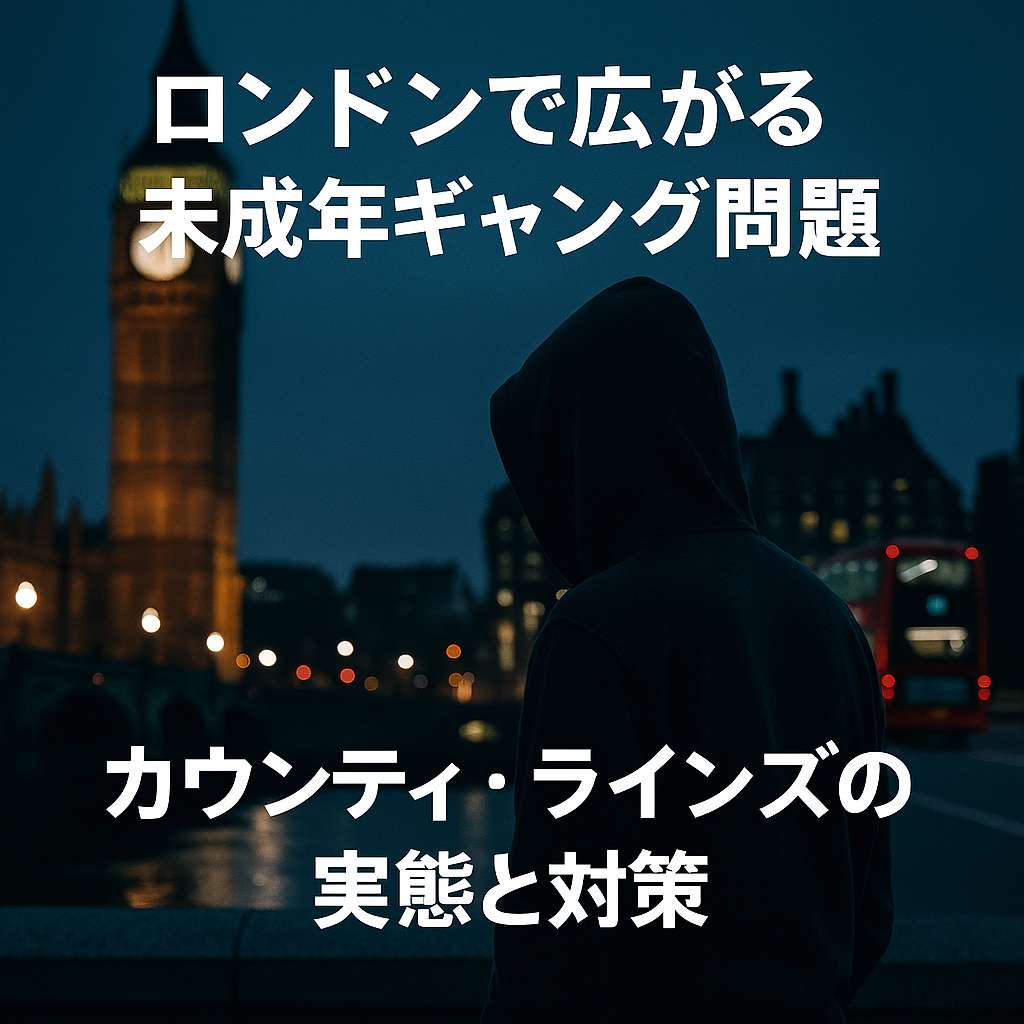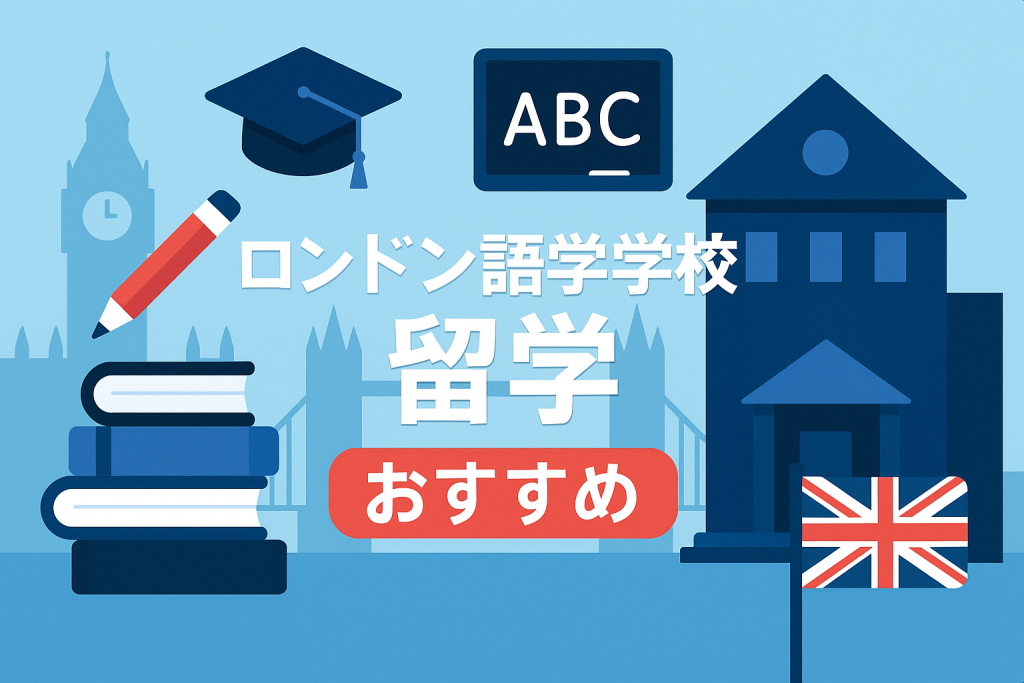…
ロンドン
ロンドンで生活する上でのお役立ち情報、ロンドンでの常識、ロンドンでの物件探し、小学校の申し込み方法、セカンダリースクールの申し込み方法、インターネットの料金形態、公共料金の支払い方法など、ロンドンで生活するうえで必要不可欠な情報満載の英国生活サイト。
ジョイス・キャロル・ヴィンセント事件|死後2年以上発見されなかった女性と現代社会が抱える孤独死の真実
…
イギリスで犯罪者が英雄化された事件史|ガイ・フォークスから現代SNSまで徹底解説
…
イギリスにクマはいる?野生の猛獣・危険動物事情を徹底解説
…
イギリスで多発するバス事故の実態|二階建てバスの運転が荒い?二日酔い運転・安全対策まで徹底解説
…
イギリスで急増中の詐欺まとめ|被害額・手口・高齢者が騙される理由と対策【2025年最新】
…
ロンドンで広がる未成年ギャング問題|カウンティ・ラインズの実態と対策
…
【2025年最新版】ロンドンおすすめ語学学校ランキング|失敗しない選び方と徹底比較
…
ロンドン賃貸市場に異常事態? 家賃高騰・供給減少・動き出す市場の歪みを解説
…
ロンドンで高い家賃を提示する不動産会社に注意|相場確認と交渉のポイント
…