
イギリスと聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのはロンドン、オックスフォード、ケンブリッジなどの大都市でしょう。これらの都市には多様な人種・文化・価値観が共存しており、グローバルな雰囲気が漂っています。しかし、そんな都市部を離れ、田舎に足を運んでみると、意外な現実に直面することがあります。
「田舎の人は素朴で親切」というイメージが先行しがちですが、実際には、田舎に行けば行くほど外国人に対しての距離感が強まり、ときにそれが“差別的”と捉えられる言動となって現れることもあるのです。なぜそのような現象が起きるのでしょうか?この記事では、イギリスの田舎における人種差別の実情と、その背景にある歴史・社会構造・心理について掘り下げていきます。
■ 「親切な田舎の人々」という幻想
日本でもよくあるように、「田舎の人=親切、素朴」というイメージはイギリスにも存在します。確かに、田舎の人々は都市の喧騒とは無縁で、表面的には穏やかに見えることが多いでしょう。しかし、この「親切さ」はあくまで“自分たちの共同体の中”での話であり、「異物(=外から来た人間)」に対しては排他的になる傾向があるのです。
特にアジア人や黒人といった「目に見えて違う」人種に対しては、都市部ではありえないような視線を浴びたり、無視されたり、時にはあからさまな差別的発言を受けることもあります。
■ 田舎と都市の「多様性格差」
ロンドンやマンチェスター、バーミンガムといった都市部では、多様なバックグラウンドを持つ人々が共に暮らしており、多文化共生の意識が根付いています。イギリス全体の人口のうち約15%がマイノリティ人種(非白人)であるとされますが、ロンドンではその割合が実に40%以上にも達しています。
一方、田舎や小さな町では、住民の大半が白人(特にイングランド系)で構成されており、日常的に「外国人」と接する機会が極めて限られています。そのため、彼らにとって異なる文化や言語を持つ人間は“未知の存在”であり、それが恐れや警戒、さらには偏見へとつながりやすいのです。
■ 「差別」ではなく「免疫がない」?
こうした田舎での外国人への態度について、「差別的だ」と感じるのは当然ですが、同時に「差別しようとしているわけではない」「単に免疫がないだけ」という声も少なくありません。実際、田舎の人々の多くは、悪意からではなく“どう接していいかわからない”という戸惑いから無言や回避的態度を取るケースが多いようです。
たとえば、アジア人が田舎のパブに入ると、店内の全員が振り返ってこちらを見るというような場面があります。これは敵意というよりも、「この村にこんな人が来るなんて珍しい」という単純な驚きや興味の現れであることもあるのです。
しかし、その「珍しい」という感覚こそが、マイノリティにとっては疎外感や不快感をもたらす原因となり得ます。つまり、意図せぬ無知や戸惑いが「差別的態度」として現れてしまうのです。
■ 保守的な価値観と教育の影響
イギリスの田舎は、政治的にも文化的にも保守的な傾向が強い地域が多く存在します。実際、2016年のEU離脱(Brexit)を巡る国民投票でも、田舎の多くの地域が離脱に賛成票を投じました。そこには「外国人が仕事を奪っている」「移民のせいでコミュニティが壊れていく」といった感情が背景にありました。
また、教育の質や内容にも地域差があり、多文化教育が十分に行き届いていない田舎の学校では、他国の文化や宗教、人種について偏った知識しか持っていないまま大人になる人も少なくありません。こうした背景が、無意識のうちに「よそ者=不安要素」として認識される構造を生み出しているのです。
■ 実際の体験談から見る現実
日本人や他のアジア系移民の中には、「田舎に住んだ途端に近所の人から話しかけられなくなった」「スーパーで店員があからさまに無愛想になった」といった経験を語る人もいます。
中には、「何か困っていても誰も助けてくれない」「バスに乗ると席をあけられる」といった、静かな排除を感じたという声も。これらはすべて、田舎特有の“閉じられた共同体”に外部者が入り込んだときに起こる摩擦の一端といえるでしょう。
■ 変わりつつある地域もある
とはいえ、すべての田舎が差別的で閉鎖的というわけではありません。近年では観光業の発展や留学生の増加、都市からの移住者によって、少しずつ外部との接触が増え、多文化への理解を深めようとしている地域も出てきています。
たとえば、スコットランド北部のある町では、地元の学校が国際理解教育に力を入れており、留学生との交流会や異文化フェスティバルなどを通じて、住民同士の理解が深まってきているという報告もあります。
このように、「変わりつつある田舎」も存在するのです。
■ 差別を“意識的に”減らしていくには
では、こうした田舎特有の差別や無理解を減らすためにはどうすればよいのでしょうか?以下のような取り組みが効果的だとされています。
- 教育の充実
多文化共生を子どもの頃から学ぶ機会を増やすことで、無知による差別を減らすことができます。 - 地域との積極的な交流
外国人の側も積極的に地域行事に参加し、自らの文化を紹介することで、住民との距離を縮めることができます。 - 差別を可視化し、議論を促す
「自分たちは差別していない」と思っている人にも、自分たちの行動がどう受け取られているかを伝えることが重要です。 - 行政による支援とガイドラインの整備
地方自治体が多文化共生ガイドラインを設けるなどして、地域全体の意識改革を後押しする必要があります。
■ 結論:田舎にこそ必要な“開かれた心”
イギリスの田舎における外国人差別の問題は、単なる悪意によるものではなく、無知や経験不足、保守的な価値観からくる“構造的な無理解”が根底にあります。そして、その無理解は放っておけば“静かな差別”として定着し、いつまでも解消されることはありません。
都市部では当たり前となっている多様性の価値を、田舎にも広げていくためには、双方の歩み寄りと継続的な対話が不可欠です。田舎の人々の親切さが、本当に“誰に対しても平等なもの”になるには、まだ時間が必要かもしれません。しかし、その一歩一歩こそが、多様性を認め合う社会への礎となるはずです。





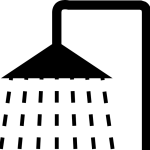



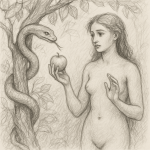
Comments