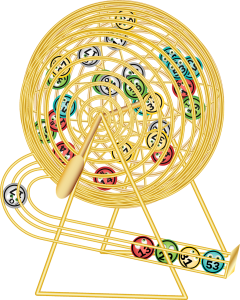
宝くじ。それは一攫千金の夢を追いかける最も古典的な手段の一つであり、多くの人々が毎週、あるいは毎月のように小さな希望を握りしめて買い続ける現代のロマンである。日本でもジャンボ宝くじやロトシリーズなど、多くの宝くじが販売されており、当選者の話がニュースになるたびに、「自分も当たるかもしれない」という期待が胸をよぎる。しかし、ふと海外の宝くじ事情を知ってしまったとき、その希望がいかに小さなものであったかに気づかされることになる。
特に、イギリスの宝くじ事情、そしてヨーロッパ全体で販売されるユーロミリオン(EuroMillions)の存在は、日本の宝くじファンにとって軽い衝撃では済まされない規模感を持っている。この記事では、イギリスおよびユーロ圏の宝くじがどれほどスケールの大きいものなのか、そしてそれを知った日本人が感じる切なさや違和感について、掘り下げていこうと思う。
イギリスのナショナル・ロッタリー:最低保証がすでに違う
イギリスには「ナショナル・ロッタリー(National Lottery)」という国家規模の宝くじが存在する。これは1994年にスタートし、政府の管轄のもとで運営されている信頼性の高いくじである。このロッタリーの中核をなすのが「Lotto」と呼ばれるもので、週に2回(毎週水曜日と土曜日)抽選が行われる。
このLottoの特徴は、最低ジャックポットが200万ポンド(約3億5000万円)からスタートする点にある。しかも、当選者が出なければ、キャリーオーバー(繰越)が発生し、最大5回まで繰り越される。その後の”必ず当選する”仕組みによって、賞金は必ず誰かの手に渡るのだ。
さらに驚くべきは、その配当のバランスである。日本の宝くじに比べて、下位等級(たとえば3等や4等)の当選金額が比較的高く、当選確率も現実的。”夢のまた夢”ではなく、”手が届くかもしれない夢”として設計されている。
ユーロミリオン:まさに桁違いの金額
さて、イギリスの宝くじに驚いている場合ではない。その上をいくのが「ユーロミリオン(EuroMillions)」である。
ユーロミリオンは、イギリスを含むヨーロッパ9カ国(スペイン、フランス、イタリア、ベルギー、ポルトガル、アイルランド、スイス、ルクセンブルク)で共同運営されている巨大ロトである。毎週2回抽選が行われ、ジャックポット(1等賞金)の最低保証金額はなんと1700万ユーロ(約27億円)である。
これだけでも日本のジャンボ宝くじの1等賞金(前後賞込みで7億円)をはるかに超えているが、ユーロミリオンの恐ろしさは、そこからのキャリーオーバーにある。ジャックポットが当たらないたびに、賞金はどんどん積み上がり、上限は2億4000万ユーロ(およそ380億円)という驚異的な数字にまで膨らむ。
実際、2023年にも2億4000万ユーロの当選者が出て話題となった。しかもその人はたった1口の購入でこの天文学的な金額を手に入れたのだ。
日本の宝くじ:人生は変わらないかもしれない
さて、ここで冷静に日本の宝くじに目を向けてみよう。たとえば、年末ジャンボ宝くじの1等賞金は7億円、前後賞込みで10億円。確かに数字だけ見れば「夢のある金額」に思える。
しかし、実際の当選確率を見てみると、1等に当たる確率は1000万分の1。これは、雷に打たれる確率や、隕石が直撃する確率に近いというジョークすらあるレベルだ。さらに問題なのは、当選金の課税の仕組みや、配当金の分配構造にある。
日本の宝くじは非課税である代わりに、売上の約50%が自治体や福祉事業に回され、実際の当選金に分配される割合は低い。つまり、我々が購入する宝くじの半分は夢ではなく寄付として消えていく。
加えて、日本の宝くじでは”キャリーオーバー”の制度が限定的であり、ユーロミリオンのような「賞金が青天井に膨らむ」ことは起こりえない。そのため、年末ジャンボであろうが何であろうが、最高賞金はある程度決まっており、数百億円単位の人生一発逆転という劇的な夢は存在しない。
金額の差がもたらす精神的インパクト
日本の宝くじファンにとって、ユーロミリオンのようなスケールを知ってしまうと、自国の宝くじに対して何とも言えない虚無感や諦めが生じるのは否めない。もちろん、7億円でも人生は大きく変わる可能性があるし、それを否定するわけではない。
しかし、370億円という数字を見せつけられると、それはもはや人生が変わるレベルではなく、人生が別次元に昇華するレベルである。働かなくていいどころか、国を超えた不動産投資や、財団設立、ジェット機購入、個人島の所有まで、できることが桁違いに広がる。
その視点で見たとき、日本の宝くじの「夢」は、どこか現実的すぎて、庶民の小さな望みを丁寧に包んだラッピングのようにも感じられる。それはそれで健全なのかもしれないが、本当に人生を変えたい人にとっては、少し物足りないかもしれない。
「夢の設計」が違うという現実
結局のところ、宝くじというのは「夢を売る商品」である。その夢の設計が、国ごとに大きく異なる。イギリスやヨーロッパの宝くじは、まさに”一夜にして人生が激変する”という派手な夢を演出しており、参加者のテンションも高い。
一方で、日本の宝くじは、当選しても慎ましく暮らす、もしくはローンを完済してちょっと贅沢する、といった程度の夢にとどまる設計になっている。それが文化的背景なのか、制度的な問題なのかは一概には言えないが、宝くじを通して見える”国民性”や”価値観”の違いは非常に興味深い。
まとめ:夢を見るならスケールにもこだわりたい
宝くじで人生が変わる。それは誰もが一度は妄想する夢だ。しかし、その夢のスケールが国によってあまりにも違うことを知ってしまったとき、人は何を感じるだろうか。
日本の宝くじにも魅力はある。だが、イギリスやユーロミリオンのような規模を知ってしまった今、その夢のサイズ感に物足りなさを覚えてしまうのもまた、正直な感情である。どうせ夢を見るなら、思いきりバカでかい夢を見てみたい。そんな思いが、日本の空の下で、少しずつ広がり始めているような気がしてならない。










Comments