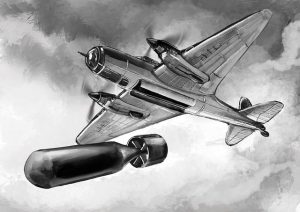
世界が不安定さを増す中、次に大規模な戦争に巻き込まれる国はどこか──。この問いは決して空想ではなく、イスラエルによるガザ攻撃、ロシアのウクライナ侵攻といった現実の戦争を見れば、常に現実味を帯びています。
戦争において「全滅させられるほどの軍事力」があっても、実際にはそうしない理由があります。それは 報復の恐怖 です。攻撃によって周辺諸国や同盟国を敵に回すことは、自らの国家存続を危険にさらすためです。
この視点から見ると、どの国が「報復の傘」に守られており、どの国が「孤立しているのか」を比較することは、将来の戦争の標的を予測するうえで非常に重要です。ここではイギリス、日本、台湾を例に、その立場の違いを整理していきます。
イギリス:NATOと国連常任理事国という最強の後ろ盾
イギリスは島国であり、日本と地理的には似ています。しかし安全保障体制は圧倒的に強固です。
- NATO加盟国
北大西洋条約機構(NATO)は世界最強の軍事同盟であり、その第5条は「加盟国の一国が攻撃された場合、全加盟国が共同で防衛する」と明記しています。つまりイギリスが攻撃を受ければ、アメリカをはじめとする30以上の国が自動的に反撃に動くのです。 - 国連安保理常任理事国
イギリスは国連安全保障理事会の常任理事国であり、国際政治において強大な発言権を持ちます。外交的な抑止力としても極めて大きな意味を持っています。 - 地政学的リスクの波及
さらにイギリスへの攻撃は、隣国アイルランドやEU加盟国を巻き込む可能性が高く、結果的にヨーロッパ全体を敵に回すことになります。攻撃する側にとって、あまりに大きな代償を伴うことは明らかです。
このため、イギリスは「攻撃されにくい国」の代表例といえるでしょう。
日本:日米同盟に依存する脆さ
日本は国連加盟国ですが、国連には 加盟国を自動的に守る義務は存在しません。安保理での決議が必要であり、米・露・中・英・仏の常任理事国の利害が一致しなければ軍事行動は不可能です。したがって、国連加盟は外交的には意味があっても、軍事的抑止力にはなりません。
現実的に日本を守る柱は 日米安全保障条約 です。アメリカは日本が攻撃を受ければ共同防衛にあたる義務を負っています。これは確かに大きな抑止力ではありますが、不安要素も見逃せません。
- トランプ前大統領は「同盟国を守るためにアメリカが金を払いすぎている」と繰り返し主張し、日本に対しても防衛費負担の増額を強く要求しました。
- アメリカが「自国第一」を優先し、同盟国防衛への関与を弱める可能性は現実的なリスクです。
- 日本はNATOのような多国間集団防衛の枠組みに参加していないため、「アメリカが動かなければ孤立する」という脆弱さがあります。
つまり、日本は「アメリカの政治状況に強く依存している」ため、完全な安心感を持つことはできないのです。
台湾:国際社会で最も孤立する危うさ
台湾はさらに厳しい立場に置かれています。
- 国連加盟国ではない
国連加盟国でないため、安保理や国際機関の枠組みで防衛を訴えることすら難しい立場です。 - 国家承認の少なさ
台湾を正式な国家として承認している国は20未満であり、国際的な孤立は深刻です。 - 米国との関係
アメリカは「台湾関係法」に基づき武器供与や軍事支援を行っていますが、日本同様に「自動的に防衛する義務」は存在しません。
さらに、台湾は地理的に中国本土と近く、補給線や国際的な援軍の派遣も困難であるため、現実的な軍事リスクは日本以上に大きいといえます。
結論:次に犠牲になる可能性が高いのは日本と台湾
比較すると、
- イギリス → NATOと国連の強力な後ろ盾に守られ、攻撃されにくい
- 日本 → 日米同盟はあるが、アメリカの政治判断に依存しすぎている
- 台湾 → 国際的に孤立し、守られる保証が極めて薄い
この構図から見えてくるのは、報復の恐怖を与えにくい「孤立した国」ほど標的になりやすいという事実です。
その条件に最も当てはまるのは、地政学的に孤立し、集団防衛体制を持たない 日本と台湾 です。
イギリスが安全保障面で「攻撃されにくい国」の典型である一方、日本と台湾は「犠牲になりやすい国」の代表例といえるでしょう。









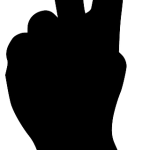
Comments