
序章:島国・日本と開かれた島国・イギリスの違い
日本に住む多くの人々にとって、移民問題はどこか遠い世界の話だ。確かに技能実習生や特定技能外国人が増え、都市部のコンビニで外国人店員を見かける機会は増えたが、それでもなお、日本は事実上「移民を受け入れない国」として知られている。一方、同じ島国であるイギリスは、長らく移民を受け入れ続けてきた。かつての大英帝国の植民地との関係性や、欧州連合(EU)加盟時代の政策もあり、世界中から人々が集まり、現在ではロンドンの人口の半数以上が「非白人」とも言われる。
この開放性が、多様性という強みを育てた反面、社会保障制度の崩壊という深刻な問題を引き起こしている。
第1章:イギリスを覆う移民の波
EU離脱と移民への焦燥
2016年のイギリスのEU離脱(ブレグジット)は、その背景に「移民問題」が色濃く存在したことは周知の事実だ。自由な労働移動を可能にしたEU加盟により、東欧諸国からの移民がイギリスへと大量に流入。医療や教育、住宅といった公共サービスに過度の負担がかかり、イギリス国民の不満が爆発した。これが保守政権を押し上げ、EU離脱を決定づける原動力となった。
中東・アフリカからの「難民」
近年、イギリスへの移民の中心は、もはや東欧出身者ではない。シリア、アフガニスタン、イラク、スーダンといった戦乱や独裁の影響を受ける中東・アフリカ諸国からの避難民が増加している。英仏間のドーバー海峡を小舟で渡る「ボートピープル」が増え、亡命申請者数は2023年に過去最高を記録した。彼らは本当に「難民」なのか、それとも「経済的移民」なのか。この線引きが極めて曖昧で、制度上は多くのケースで保護対象とされ、手厚い支援を受けることになる。
第2章:生活保護制度の歪み
英国の福祉国家モデルとは
イギリスは「福祉国家(Welfare State)」の元祖とも言える存在であり、国民全員に医療・教育・社会保障を提供する制度は世界的にも先進的だった。だが現在、この制度が移民流入により根底から揺らいでいる。
難民申請者やその家族は、審査期間中であっても住宅、生活費、医療といった基礎的なサポートを無料で受けられる。多くは就労が認められていないが、その分、政府からの支給金で生活が維持できる仕組みになっている。その財源は当然、納税者からの税金である。
生活保護と「文化の違い」
多くの移民は、自国では想像もできないレベルの手厚いサポートを受け取れることを知ってイギリスに来る。実際に、難民向けの情報をSNSや口コミで広めている組織も存在する。中には「イギリスでは働かなくても子供を産めば住宅と支援金がもらえる」といった内容を宣伝するケースもある。これが一部の移民にとって、福祉制度の「悪用」につながっているという批判がある。
また、イスラム文化圏からの移民の中には、女性が働かない家庭が一般的であるケースも多い。こうした家庭では、複数の子供を抱える中で政府支給の児童手当や住宅支援が生活の柱となっており、経済的な自立が難しい。
第3章:納税者の怒りと中間層の崩壊
「働く人が損をする国」
制度の歪みが最も深刻な影響を与えているのが、いわゆる中間層である。彼らはフルタイムで働き、税金を納め、社会保険料を支払い、家賃や学費を捻出している。しかし彼らは生活保護の対象にはならず、むしろ自らの負担が制度の維持に使われていることに強い不満を抱くようになった。
「自分は頑張って働いているのに、働かない人の生活を支えているだけではないか」という怒りは、保守層や移民反対派の支持を集め、政治的な分断も深めている。
富裕層の国外脱出
もう一つの問題は、高所得者の「逃避」だ。高い所得税、相続税、不動産税などに加え、国家の支出が移民支援に向けられることを快く思わない富裕層が、タックスヘイブンや他国への移住を進めている。ロンドン市内の高級住宅街でも、空き家や外国人オーナーによる「投資目的」の不在住が増え、地域コミュニティは空洞化している。
結果的に、国家は財政難に陥り、さらに中間層への課税強化や社会サービスの削減を迫られるという悪循環が生まれている。
第4章:崩壊する「共通善」の理念
かつて、イギリスの福祉制度は「国民全員の生活を支える」という共通善に基づいて設計されていた。しかし「国民」とは誰か? という問いが、今や制度の根幹を揺るがしている。
「難民」であれば保護されるが、「低所得のイギリス人」であれば支援は限られる。そんな現実に対して、強い違和感と不公平感を抱く国民が増えている。移民政策や難民受け入れの再考を求める声は、もはや極右や排外主義者のものではなく、一般的な市民感覚として広がりつつある。
終章:日本にとっての教訓
移民の大量流入、生活保護制度の崩壊、納税者の疲弊と政治の混乱。これらは決して「他人事」ではない。少子高齢化が進む日本でも、将来的に労働力不足を補うための「移民政策の転換」が避けられないと言われている。実際、技能実習制度の見直しや、より長期的な外国人受け入れ政策の検討が始まっている。
イギリスが辿った道を、日本がどう受け止め、どう差別化していくか。制度設計、文化理解、国民の納得感──どれもが欠かせない要素だ。
イギリスの失敗から学べることは多い。特に「理想だけでは国家を運営できない」という現実を、日本人は今から真剣に受け止めるべきだろう。







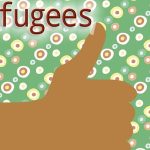


Comments