
イギリスに住んでいると、街中やビジネスの現場で多くのアフリカ系の人々と接する機会がある。ロンドンやバーミンガムなどの大都市には、歴史的な背景や旧植民地とのつながりもあり、アフリカからの移民が大きなコミュニティを形成している。彼らは飲食、物流、サービス業、さらには金融の一部にまで幅広く進出しており、イギリス経済にとって欠かせない存在だ。
こうした現実から見えてくるのは、アフリカ諸国とのビジネスには独自の文化的背景や価値観が色濃く反映されているという点だ。日本からはなかなか見えにくいが、この「文化の壁」を理解しないまま投資や事業展開を進めると、思わぬリスクを抱えることになる。
日本的常識は世界共通ではない
日本のビジネス文化は「時間を守る」「契約を重視する」「責任を果たす」といった要素が強く根付いている。しかし、これはあくまでも日本国内の常識であって、世界標準とは限らない。
例えばイギリスでアフリカ系ビジネスパートナーと接していると、時間の感覚が日本とは異なる場面に直面することがある。打ち合わせが予定通りに始まらない、合意したことが柔軟に変わる、といったことは珍しくない。もちろんそれが「悪意」や「怠慢」ではなく、単純に文化や生活習慣の違いとして根付いているケースも多い。
「意識改革」ではなく「相互理解」が鍵
日本国内では「相手の意識を変えなければならない」と考えがちだが、現実的には他国の文化を根本から変えることは不可能だ。むしろ成功の鍵は、相手の文化を前提にした仕組みづくりにある。
イギリスでアフリカ系の人々が築いているビジネスを観察すると、時間のルーズさを前提にバッファを組み込んだ契約や、信頼できるコミュニティ内でのネットワークを重視するなど、独自のリスクヘッジが存在する。つまり「違いを克服する」のではなく「違いを理解して折り合いをつける」ことこそが、持続可能なビジネスには欠かせない。
日本の政治家・企業に求められる現実的視点
現在、日本政府や企業は「アフリカは最後の巨大市場」として投資や経済協力を推進している。人口増加、資源の豊富さ、消費市場の拡大といったポテンシャルは確かに魅力的だ。しかしその一方で、現地の文化や社会構造への理解が不十分なまま巨額の資金を投入すれば、成果は上がらず「お金をどぶに捨てる」ことになりかねない。
政治家や経営者がもし「日本流を押し付ければうまくいく」と安易に考えているなら、それは危険な幻想である。むしろ必要なのは、現地パートナーの選定に時間をかけること、柔軟な契約設計を行うこと、そして現地の社会的慣習を制度的に補完する仕組みをつくることだ。
警鐘:痛い目を見る前に
イギリスにおけるアフリカ系コミュニティの存在は、日本にとって大きな教訓を与えてくれる。彼らのビジネス慣習を目の当たりにすれば、アフリカ投資に潜むリスクと可能性の両方を理解できるはずだ。
もし日本がこうした文化的現実を軽視し、資金だけを流し込むようなやり方を続けるなら、成果はほとんど得られず「痛い目を見る」ことは避けられない。投資はお金だけではなく、相互理解と仕組みづくりがあって初めて成功する。その認識を日本の政治家や企業が持てるかどうかが、今後のアフリカ戦略の成否を決定づけるだろう。




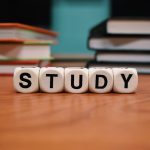





Comments