
英国において、社会の奥に潜む“真の悪(true evils)”とは何か。表面的なニュースで語られる事件や出来事だけではなく、制度・構造・無意識の連鎖として社会を蝕む問題群を、本稿では改めて論じます。私たちは単に「悪い人が悪いことをした」という単純な構図で済ませてよいのでしょうか。英国の歴史・現状・未来を踏まえつつ、真の悪と向き合うための視点を整理します。
構造的・制度的な「悪」の存在
まず注目すべきは、法律・政策・社会インフラが意図せず「悪」を内包してしまっているという点です。たとえば所得格差、住宅の劣悪環境、教育アクセスの地域・階層差、医療・福祉の地域格差。こうした制度的な枠組みが、個人の意図を超えて不利益を生み出し、被害を受ける側が声をあげにくい“悪循環”を作っています。
英国では、地域によって平均寿命や健康指標が大きく異なり、また子どもの貧困率・住環境の悪化・社会的排除が社会問題化しています。これらは「偶発的」ではなく、長年蓄積された構造の下にあると言えます。
無意識の文化・慣習としての悪
次に重要なのは、文化や慣習、暗黙のルールとして機能する「悪」です。差別、ステレオタイプ、移民・少数民族に対する見えないバイアス、階層間の信頼喪失など。これらは明確な悪意を伴わないことも多いですが、結果として社会を傷つけ、機会を奪い、深刻なダメージを与えます。
英国では、例えばある地域が長年「見捨てられた地域(left-behind places)」と呼ばれ、インフラ・雇用・住環境の改善が遅れ、住民が“断片化”されているという状況が存在します。こうした現象は「無関心」「慣れ」という文化的圧力を通じて、見えにくい悪を生んでいます。
個人・集団レベルの悪行とその背後
もちろん、明らかな「悪い行為」も存在し続けています。暴力、性的搾取、児童虐待、人身取引といった犯罪は見過ごせません。ただし、これらを単純に「悪人が悪事を働いた」と捉えるだけでは、不十分です。なぜそれが起きたのか、なぜ被害者が支援を受けられなかったのか、なぜ再発が防げなかったかを問い直すことが重要です。
英国の調査では、被害が多発する背景には貧困・住環境の劣化・地域の断絶・司法・警察・福祉の支援網のギャップが見られます。つまり、悪行は単独の事件ではなく、支援機構・社会構造・文化慣習の隙間から生まれ、育っているのです。
未来に向けて――“悪”に立ち向かうための視点
では、私たちはどうすればこの「真の悪」と向き合えるのでしょうか。以下の視点が鍵となります:
- 可視化・データ化:制度や慣習がもたらす不利益を数値・報告・研究で明らかにし、議論を深める。
- 住民参加・地域再生:“見捨てられた地域”を当事者中心で再構築し、支援・公共インフラ・雇用が循環する仕組みを強化。
- 教育と文化の転換:ステレオタイプ・無意識バイアス・排除的な習慣を問い直し、包括的で多様性を尊重する社会規範を育てる。
- 早期介入と支援の網:被害が起きる“前”のリスク(住環境・貧困・断絶)に注目し、支援を手厚く、アクセスを確保。
- 制度の刷新:法律・政策が“古い構造”を温存しないよう、透明性と説明責任を高め、修正可能な枠組みにする。
結びに――“真の悪”から目をそらさないために
私たちは、悪をただ「起こったこと」として受け止めてしまいがちです。しかし、真の悪は表層に現れるだけではなく、制度・文化・構造の中に深く根を下ろしています。それを見抜き、問い直し、変えていくことこそが、社会を真に守る道だと言えるでしょう。
英国の現在は、過去の失敗を繰り返さないために、真の悪と向き合う転換点にあります。私たち一人ひとりが視点を持ち、行動を起こすことで、社会の底辺に潜む見えない悪を少しずつ浮かび上がらせ、変革への一歩を刻んでいくことができます。







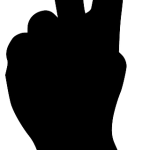


Comments