
はじめに
「人間の暮らしを優先するために木を伐採し、巣を失った鳥が死んでいく」「天然ウナギが絶滅の危機に瀕しているのに、食卓の都合で養殖ウナギを推進する」。日本におけるこうした環境対策は、「人間中心主義」の現れだといえる。対照的に、イギリスでは自然そのものに権利があるという考えのもと、自然環境の保全が社会制度や文化に組み込まれている。
この記事では、日本とイギリスの環境意識の差を掘り下げ、日本がいかに自然との共生から遠ざかっているかを、倫理的・文化的・制度的視点から分析する。そして、なぜ私たちは「自然の声」に耳を傾けられないのか、どうすればそれができるのかを考えてみたい。
第1章 人間中心主義の根強い日本
苦情が「正義」になる社会
近年、日本各地で「迷惑だから」という理由で街路樹が伐採されたり、公園の草木が切られたりするケースが急増している。その背景には、「落ち葉で滑る」「虫が多い」「鳥の鳴き声がうるさい」といった苦情がある。たとえば東京都のある住宅街では、サギの繁殖地となっていた木々が、住民の苦情によって一斉に伐採された。結果、営巣していたサギたちは大量死し、次の年からその地域でサギを見ることはなくなったという。
このように、日本では自然環境を守るよりも「人間の生活の快適さ」が優先される。苦情=市民の声=善という構図が強固に根づいており、「自然の権利」は最初から交渉のテーブルにすら上がらない。
天然資源を「消費」の対象としか見ない
ウナギの例も象徴的だ。ニホンウナギは絶滅危惧種に指定されて久しいが、日本では土用の丑の日が近づくたびにウナギが大量に消費される。天然ウナギの乱獲が問題視されるなか、次に登場したのが「完全養殖ウナギ」である。これによって「安心して食べられる」と安堵する消費者も多いが、それは「食べる」という行為が前提にあるからであり、ウナギという生き物そのものの尊厳や生態系のバランスにはほとんど関心が向けられていない。
この構図は、日本の自然観の縮図でもある。つまり、自然は「人間の役に立つ限りにおいて価値がある」とされており、それ以外の存在意義は無視される。これは明らかに、人間中心主義の発想である。
第2章 自然に権利を認めるイギリスの発想
「自然には自らを保つ権利がある」という哲学
イギリスでは、環境保護が単なる善意や努力ではなく、「制度」として確立されている。たとえば、英国の国立公園では自然環境の保全が最優先され、開発は極めて制限されている。家を建てるにしても、野鳥の営巣地やコウモリの生息地に配慮することが義務付けられ、違反すれば厳しく罰せられる。
また、2021年にはイギリスのダービーシャー州が、川に「法的権利」を与える条例を可決した。これは、川という自然存在が「自らを汚染されずに存在する権利」を持つと認めたものであり、まさに自然を主体として扱う姿勢の表れだ。
「人間も自然の一部にすぎない」という教育
イギリスでは、初等教育から環境倫理が重視されており、「自然を守ることは人間を守ること」と教えられる。都市部の子どもたちでさえ、週に一度は「フォレストスクール(森林学校)」として自然の中で過ごす時間を持つ。自然は「触れるもの」「楽しむもの」であると同時に、「尊重すべき対象」であることが肌感覚として身についている。
第3章 なぜ日本は自然を軽視するのか
「自然は制御すべきもの」という歴史
日本の自然観は、地理的・歴史的背景に根ざしている。台風・地震・津波といった自然災害が多い日本では、自然は畏怖の対象であり、「制御すべきもの」として捉えられてきた。稲作文化もまた、自然のリズムを読み取りながらも「人間の管理」によって成り立つ側面が強く、「自然に任せる」よりも「自然を従わせる」ことに価値が置かれてきた。
このような背景から、日本人は自然を「コントロールするもの」「管理するもの」と見なす傾向が強く、自然の側に主体性や権利を認めるという発想に至らない。
教育の問題
日本の教育制度では、「自然保護」が道徳や理科の一部として扱われるにとどまり、倫理的・哲学的な議論としては取り上げられない。環境問題は「知識として覚えるもの」であって、「問い直すべき価値観」としては扱われていない。そのため、多くの日本人は「自然を守るとは何か」「人間以外の生命に権利はあるのか」といった根本的な問いに触れる機会がないまま大人になる。
第4章 自然の声を聞くということ
苦情を超えて、共生の視点へ
苦情によって伐採された木の下で、巣を失って死んだ鳥たちの命。私たちは、その命に対して何を語ることができるのか。たしかに「鳥の鳴き声がうるさい」と感じる人もいるだろう。しかし、そこには「共に生きる」という視点が欠けている。
共生とは、相手が迷惑だと感じた瞬間に排除することではない。むしろ、「どうすれば共に存在できるか」を考えることが、共生の出発点だ。人間の都合ですぐに自然を切り捨てる日本の構造は、まさに「共生」の対極にある。
経済効率よりも、生態系の持続性を
天然ウナギが絶滅しかけているのに、代替手段として「養殖で食べ続ける」ことを正当化する発想。これは自然の側から見れば暴力である。根本的な問いは、「私たちは本当にウナギを食べ続ける必要があるのか?」であり、そこに対する答えがなければ、どれだけ技術が進歩しても持続可能性など成り立たない。
イギリスでは、ある種の魚が絶滅の危機に瀕すると、漁を一時的に全面禁止することがある。市場や飲食業界からの反発があっても、「生態系の回復が先だ」という判断がなされる。その背景には、「自然もまた社会の一員である」という倫理観がある。
第5章 自然と共に生きる未来へ
私たちにできること
日本でも、自然に対する意識を変える動きは少しずつ生まれている。市民による自然保護活動、学校教育におけるESD(持続可能な開発のための教育)の導入、環境NGOの活動など、草の根の努力は確かに存在する。
しかし、問題は「構造」と「価値観」だ。人間中心主義から脱却するには、制度設計の見直しとともに、「自然に対するまなざし」を変える文化的転換が必要である。そのためには、自然の声を聞き、その存在に権利を認めるという根本的な価値転換が不可欠だ。
自然の沈黙を、私たちが語る時
自然は語らない。しかし、その沈黙のなかに無数の「死」がある。鳥が巣を失って死んだとき、ウナギが河口から消えたとき、私たちは何を感じるべきなのか。その「違和感」こそが、変化の出発点である。
自然に権利を――それは、感情の問題ではなく、倫理の問題であり、社会の設計思想の問題である。そして、自然の側に立つという姿勢は、決して「人間を犠牲にすること」ではない。むしろ、それが人間の生存を持続可能にする唯一の道なのだ。
終わりに
日本が本当に豊かな国であるためには、自然を「守るべき対象」ではなく、「共に生きる仲間」として捉え直す必要がある。木を伐れば鳥が死に、魚を獲りすぎれば海が枯れる――それは「人間の問題」ではなく、「生態系の問題」ではない。私たち自身の在り方の問題である。
自然を中心に考える社会。それは空想ではなく、すでに多くの国で現実となっている。日本がその歩みに加わるためには、まず「人間中心」の視点を問い直す勇気が求められている。








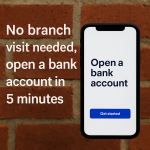

Comments