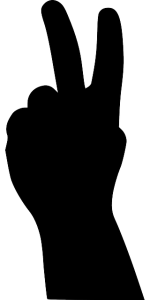
はじめに:平和はどこから来て、誰が守るのか?
現代に生きる私たちが「平和」と聞いたとき、何を思い浮かべるでしょうか?
穏やかな日常。戦争のない世界。豊かな経済。自由な発言や思想。
しかし、こうした「平和」の定義は、国や文化、そして歴史によって大きく異なる場合があります。
とりわけ、日本とイギリス。この二国は第二次世界大戦を巡って“敵同士”だった歴史を持ちますが、戦後80年近く経った今では、互いに友好関係を築き、国際社会の中で「平和国家」としての地位を確立しています。
では、「イギリス人が考える平和」と「日本人が考える平和」は同じものなのでしょうか?
また、「敗戦を経験していない国民」が考える平和とは、一体どのようなものなのでしょうか?
今回は、こうした疑問に答える形で、イギリス人の「平和観」を探りつつ、日本との比較や歴史的背景を交えて考察していきたいと思います。
第1章:イギリス人にとっての「平和」とは?
1-1 歴史と共に歩む国の視点
イギリスは、長い歴史の中で世界をリードする大英帝国を築きました。
アフリカ、アジア、オセアニア、カリブなど多くの地域を植民地として支配し、常に国際政治の中心にありました。イギリス人にとって、「国を守る」「影響力を持つ」「秩序を維持する」といったことは、単なる防衛ではなく「平和を作る」行為として認識されてきました。
つまり、彼らにとっての平和とは「力の均衡の上に成り立つもの」なのです。
これは、冷戦期にイギリスがアメリカと共にNATOの中核を担い、核兵器を保持し続けた事実にも表れています。
平和とは、話し合いや理想主義によって得られるものではなく、時に「戦う意思を見せることで維持される」ものという考えが根底にあるのです。
1-2 “戦争の記憶”と“勝者の記憶”
第二次世界大戦において、イギリスはナチス・ドイツの空襲に晒され、多大な被害を受けましたが、「敗戦」は経験していません。
それどころか、チャーチル首相のもと、連合国の勝利の立役者として名を馳せ、「自由と民主主義の守護者」という自負を育んできました。
この「勝者の記憶」は、戦争に対する意識にも影響しています。
イギリスでは、毎年11月に「リメンブランス・デー(追悼の日)」があり、戦争で亡くなった兵士たちに哀悼の意を表します。しかしそこには「戦争の悲惨さ」に加えて、「祖国のために戦った誇り」も含まれています。
つまり、「平和」は「過去の犠牲の上に成り立つ、努力の成果」という意識が強くあるのです。
第2章:日本人にとっての「平和」とは?
2-1 「戦争は悪」という絶対的価値観
日本は、第二次世界大戦で敗戦国となり、東京大空襲、広島・長崎の原爆など、圧倒的な被害を受けました。その後、アメリカの占領下で非軍事化が進み、憲法第9条によって「戦争の放棄」「戦力の不保持」が明記されます。
この歴史的背景が、日本人の平和観に大きな影響を与えました。
「戦争は絶対悪」「平和とは、戦わないこと」という意識が強く、戦争や軍事行動に対して極端に敏感になったのです。
そのため、自衛隊の海外派遣や、防衛費の増額といった話題にも、常に議論が巻き起こります。
2-2 「加害と被害」の記憶
日本は同時に、アジア諸国に対して加害者でもありました。しかし、国内ではその側面よりも「被害者としての日本」が強調されがちです。
これは、「戦争を繰り返さないためには、二度と軍事に関わらないことが必要」という意識をさらに強固にしてきました。
つまり、日本における「平和」は、反省と赦し、そして徹底的な非武装の上に築かれた「静的な平和観」と言えるかもしれません。
第3章:「敗戦を知らない国民」の平和とは?
イギリスのように、近代において国土が占領されず、「敗戦」を経験していない国民は、自国の力を信じ、必要であれば「武力による平和の確保」も容認する傾向があります。
例えば、アメリカやフランス、イギリスなどの旧列強国家は、軍事力の保持と行使を「国際的責任」として位置づけることが多く、「平和のための介入」という論理をよく使います。
イギリス人にとって、軍人とは「英雄」であり、「国家のために働く誇り高き職業」です。これは日本のように「軍人=戦争の象徴」という見方とは根本的に異なります。
第4章:二つの平和観のすれ違いと交差点
4-1 理想と現実のはざまで
日本の「平和を守るには戦わないことが重要」という理想主義的な視点と、イギリスの「平和を維持するには時に戦う覚悟が必要」という現実主義的な視点。
この二つは、しばしば国際的な議論の中で衝突することがあります。
しかし近年、国際テロ、ウクライナ侵攻、台湾海峡問題など、平和の脅威は「戦争の有無」だけで語れないものになってきました。
そうした中で、日本でも「抑止力としての防衛力」が再評価されつつあります。
4-2 共通点は“平和を望む心”
ただし、両国に共通するのは、「平和を望む気持ちは誰しもが持っている」という点です。
その手段や前提条件が異なるだけで、平和の重要性を疑う人はいません。
どちらの国も、戦争の記憶を糧にしながら、次の世代に「平和の価値」をどう伝えるかに真剣に向き合っているのです。
おわりに:今、私たちが考えるべき平和とは?
イギリス人にとっての平和とは、「守り、勝ち取り、維持するもの」。
日本人にとっての平和とは、「守られ、与えられ、失わないようにするもの」。
この違いは、単なる思想の違いではなく、それぞれの歴史と経験の違いから生まれた「平和へのアプローチ」の差です。
しかし、世界が多極化し、価値観が揺らぎ始めた今こそ、異なる視点を理解し合うことが大切なのではないでしょうか。
私たちは、過去の教訓から目を背けることなく、しかし未来の現実とも向き合いながら、新しい「平和のかたち」を模索していく必要があるのかもしれません。









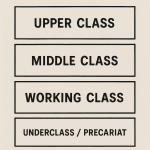
Comments