
「イギリスのテニス選手は、なぜ本番で実力を発揮できないのか?」
これは、長年イギリスのスポーツファンや評論家の間で囁かれてきた疑問である。ジュニア時代や若手の頃には「将来のウィンブルドン王者」と騒がれる才能ある選手が何人もいた。だが、その多くがシニアの大舞台に立ったとき、期待されたような結果を残せずに消えていった。
もちろん例外もある。アンディ・マリーのように、逆境をはねのけて頂点に立った選手も存在する。だが、彼は“例外的存在”であり、多くの選手たちはその域に達することなくキャリアを終えている。
では、なぜイギリスのテニス選手は本番で弱いのか?
この問いに対し、技術や戦術、トレーニング方法など様々な観点からの分析が試みられてきたが、今回はあえてその根本を「教育の在り方」に求めたい。
■ 成績優秀なジュニア期、それでも伸びない選手たち
ジュニア時代から注目されていたイギリス人選手の中には、世界ランキング1桁に入る可能性を示していた選手も少なくない。だが、いざグランドスラムやATPツアーといった大舞台に上がると、心が折れたようなプレーを見せるケースが目立つ。
彼らは技術的には世界トップクラスの選手たちと遜色ない。しかし、「勝たなければならない」「ここで結果を残すんだ」という精神的なプレッシャーに耐えきれず、自滅していく姿は何度も見られてきた。
このメンタルの脆さの背景にあるのが、イギリスで数十年前から実施されてきた「ゆとり教育」に他ならないと私は考える。
■ イギリスの「ゆとり教育」とは何か?
「ゆとり教育」というと、日本の話だと思う人も多いだろう。だが、イギリスでも1980年代後半から1990年代にかけて、教育の在り方が大きく見直され、競争よりも“個性”や“自己肯定感”を重視する教育方針が採用されてきた。
その中では、「勝ち負けにこだわらない」「みんな違ってみんないい」「競争で優劣をつけることは精神的なダメージを与える」という考えが浸透し、学校現場でも順位や成績を明確にしない、評価を言葉で和らげる、といった取り組みが増えていった。
こうした教育方針が、子供たちにどんな影響を与えたか?
端的に言えば、「負けてもいい」「勝ちにこだわらなくても大丈夫」という無意識のメッセージが刷り込まれていったのだ。
■ 負けることへの耐性と、勝負にかける覚悟
スポーツの世界は、究極的には勝者と敗者に分かれる世界である。いかに善戦しても、いかに努力しても、勝てなければ栄光は手に入らない。その厳しさがあるからこそ、勝った者の価値が際立ち、観る者に感動を与える。
だが、もし幼い頃から「負けても恥ずかしくない」「結果よりも過程が大切」「勝敗はそこまで重くない」と言われ続けて育ってきたら、果たしてその子は“勝つことの意味”を本当の意味で理解できるだろうか?
イギリスのテニス選手の多くが本番で心を折られる理由の一つは、「負けること」に対する感情の持ち方が曖昧だからだ。つまり、「ここで絶対に勝たなければ」という覚悟が生まれにくい環境で育ってしまっているのだ。
■ 「甘い教育」は「強いアスリート」を生まない
アスリートとして成功するには、才能だけでは不十分だ。負けたときに悔し涙を流し、次こそ勝つために苦しいトレーニングを積み重ねる、そんな“飢え”が必要だ。
だが、「負けてもあなたの価値は変わらない」「努力したことが素晴らしいんだ」と常に優しく言われ続ける環境では、競争への飢えが生まれにくい。
もちろん、人間としてはそれで良いのかもしれない。だが、勝負の世界ではそれは致命的な弱さとなって表れる。
■ アンディ・マリーという「異端児」
ここで、アンディ・マリーという一人の存在が光を放つ。彼はウィンブルドンを含むグランドスラムを3度制し、長年イギリスのエースとして世界と戦い続けてきた。
では、なぜマリーだけが「本番に強い」選手になれたのか?
彼の育った環境を見ると、スペイン・バルセロナでの過酷なトレーニングが鍵となっている。若干15歳で親元を離れ、他国のライバルたちと熾烈な競争の中で育った経験が、彼のメンタリティを鍛えたのだ。
つまり、彼はイギリスの「ゆとり教育」からはある種逃れた存在であり、だからこそ“本物の競争”に耐えられるアスリートになれたのだ。
■ 教育は人を育てる。だが同時に、ダメにもする
教育は、人間の人格形成において最も重要な要素である。だからこそ、その方向性を誤れば、善意であっても人を“弱く”してしまうことがある。
「個性を尊重する」「自己肯定感を育む」──それ自体は素晴らしい理念だ。だが、それが「負けても気にしない」「勝たなくてもいい」にすり替わってしまっては、競争社会で生き抜く力は養えない。
とりわけスポーツという極めてシビアな世界では、その弱さが如実に結果に現れる。
■ イギリス社会は教育を再定義すべき時期に来ている
イギリスのスポーツ界だけでなく、ビジネスやアカデミアの分野でも、「実力はあるのに本番に弱い」「海外のライバルに気圧される」といった傾向が指摘されている。
この現象に対し、「教育」という根本にメスを入れる必要がある時期に来ているのではないか。
勝負にこだわることは、決して悪ではない。むしろそれは、努力を肯定し、真剣に生きる姿勢を身につけるために必要な価値観である。
■ 終わりに:勝つことの意味を、もう一度
スポーツにおいて、勝つことはすべてではない。だが、すべてを懸けて勝とうとする姿勢こそが、アスリートをアスリートたらしめるものだ。
もし、教育がその姿勢を削いでしまうのであれば──それはどれだけ理念が美しくとも、子供たちから未来を奪うことになりかねない。
イギリスが再び“強い選手”を輩出するために必要なのは、技術や戦術の向上だけではない。根本にある「勝ちにこだわることの価値」を、もう一度見つめ直すことにあるのではないだろうか。







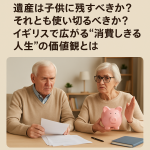


Comments