
🌆 はじめに
近年、ロンドンにおける学生の住宅事情は深刻さを増しています。特に、学生向けのシェアハウスが急激に減少しており、多くの学生が「住まい難民」と化し、学業や生活に大きな支障をきたしています。
かつては比較的手頃で柔軟な住まい方の象徴だった「シェアハウス」ですが、なぜ今、それがロンドンから消えつつあるのでしょうか。本記事では、その背景、原因、現状、そして学生と社会への影響を多角的に掘り下げ、将来への課題と可能性を考えます。
1. 賃貸物件減少の背景にある複合的要因
ロンドンの住宅市場は、世界有数の高額で競争的な市場として知られていますが、ここ数年で特に「学生向け賃貸市場」の供給環境が悪化しました。
1-1. パンデミック後の需要急増
新型コロナウイルスによるロックダウン中は、学生が実家などへ帰省するケースが多く、賃貸需要が一時的に低下しました。しかし、パンデミックの終息とともに、対面授業の再開により一気に需要が戻り、学生向け物件は「取り合い」となりました。
この急激な需要回復に対し、賃貸供給は追いつかず、家賃の高騰を引き起こしました。
1-2. 政策的規制強化の影響
シェアハウスは通常「HMO(House in Multiple Occupation)」として規制されていますが、最近、HMOに対する規制が一層厳格化しました。これにより、貸主側が新たにシェアハウスとして物件を提供するために必要な許可申請、建物の仕様変更、法的コンプライアンスのコストが増加しました。
特にロンドンの一部自治体では、HMOライセンス申請の審査が長期化しており、結果的に「ビジネスとして見合わない」と考える家主が撤退するケースが続出しています。
1-3. 建設コストの上昇と投資家離れ
原材料費の高騰、金利上昇などにより、新築・改築による学生用住宅開発の費用が膨らみ、投資としての魅力が薄れています。多くの不動産投資家は、学生を相手にするよりも高収益が見込める短期滞在型のアパートや、より高所得層向けの賃貸住宅へのシフトを選択しています。
2. 学生向けシェアハウスの激減と現場の実態
2-1. シェアハウスの「絶対数不足」
学生向けシェアハウスの減少は、単なる「供給不足」にとどまりません。特にロンドン中心部では、過去10年でHMO物件の割合が顕著に減少しており、「かつてあった選択肢そのものが消滅している」状況です。
家主がHMOライセンス維持をやめ、ファミリー向けや短期賃貸に切り替える動きが進んだため、以前なら手頃な価格で利用できたシェアハウスが、市場から次々と消えていきました。
2-2. 家賃の異常な高騰
仮にシェアハウスが見つかったとしても、その家賃は「学生が払える水準」を大きく上回っています。一般的な学生ローンでは、週に支払える家賃には限界がありますが、ロンドン市内の多くの物件は1週間あたり300ポンド近い水準に達しており、補助なしでは入居が難しくなっています。
特に都市中心部では、賃料の上昇が続く一方、地方出身の学生にとっては移住の初期費用(デポジットや家具購入費など)も含めて大きな負担になっています。
2-3. 個人家主の撤退
法律改正により、無過失退去の禁止、居住者保護ルールの強化が進められています。これらは居住者にとっては安心できる要素ですが、個人家主にとってはリスクと負担が増えたことを意味します。結果的に、多くの小規模オーナーが学生相手のビジネスから手を引くことになりました。
3. 学生の生活と学業への深刻な影響
3-1. 長距離通学の常態化
住宅が確保できない学生は、ロンドン郊外やさらに遠方に居住するしかなくなり、通学時間が1時間半〜2時間に及ぶ例も珍しくありません。これにより、授業への出席やキャンパス内での活動が制約され、大学生活そのものの質が低下しています。
3-2. 経済的ストレスとワーク・スタディ・バランスの悪化
高騰する家賃を賄うために、アルバイト時間を増やさざるを得ない学生も増えています。本来は学業に専念するための時間が削られ、心身の健康に悪影響を与えるケースも報告されています。
睡眠不足、精神的ストレス、不規則な生活は、成績低下のみならず、中退率の上昇にもつながっています。
4. 現状に対する政府・大学・産業界の対応
4-1. 政府・自治体の施策と課題
ロンドン市は一部の「手頃な価格」の学生用宿泊施設の新設プロジェクトを承認しましたが、実際には建設ペースが遅く、需要を埋めるには程遠い状況です。さらに、地域計画の複雑さから、新たなHMO開発も進んでいません。
4-2. 大学側の取り組み
いくつかの大学は、民間デベロッパーと連携し、独自の学生寮を増設しようとしていますが、都市部の用地不足と高コストの壁は依然として大きな障害です。学生寮の多くは国際学生を優先的に収容する傾向もあり、国内学生には恩恵が届きにくいという現実もあります。
4-3. 不動産業界の現状
大手不動産業者は「PBSA(Purpose-Built Student Accommodation:学生専用住宅)」を増やしていますが、これらは高級仕様であり、一般の国内学生には手が届きにくい水準です。
シェアハウスのような柔軟な選択肢を補完するには至っていません。
5. 学生ができる対応策とコミュニティの役割
現状を打破するために、学生自身も工夫を強いられています。
- 共同契約による物件確保:知人同士で早期にチームを作り、HMO物件を共同で借りる。
- ロンドン郊外の物件検討:中心部へのアクセスが良好な周辺地域で、比較的家賃が抑えられるエリアを視野に入れる。
- 大学の支援サービスの活用:大学には住宅支援オフィスが存在し、空室情報や短期宿泊オプションなどを提供しています。これらを最大限活用することが求められます。
- コミュニティ型の住居モデル:コ・リビング(共用空間を重視したシェアハウス型住居)や短期入居型住居などの新しい住まい方も視野に入れる。
6. 未来への課題と展望
現在、ロンドンの学生向け賃貸市場は、「需要の増加」「供給の硬直」「価格の高騰」「政策規制の複雑化」といった多重の課題に直面しています。
根本的な改善には、次のような政策的方向性が必要です。
- HMO規制の緩和と適正化
- 手頃な価格のPBSAの公的支援
- 大学・自治体・民間企業のパートナーシップ強化
- 学生の多様なニーズに応える住宅市場の形成
ロンドンは国際都市として、さまざまなバックグラウンドを持つ学生を受け入れてきた歴史があります。この多様性を維持し、将来世代の教育環境を守るためにも、「安心して住める住居」の確保は急務です。
🎯 おわりに
ロンドンの住宅事情は、単なる「不動産の問題」ではなく、教育政策、若者の機会平等、都市の持続可能性に関わる社会全体の課題です。
住まいを失った学生は学業への集中を妨げられ、経済的負担に苦しみ、健康やメンタルにも影響を受けます。逆に言えば、「住める」環境が整えば、ロンドンは未来を担う若者にとって魅力的な学びの都であり続けることができます。
これからも、学生、大学、政策決定者、住宅業界が一体となり、持続可能で公正な住宅市場を再構築する努力が必要です。
住まいは、学びと未来を支える基盤である──この原点を忘れず、ロンドンの街が誰にとっても「住みやすく、学びやすい場所」であり続けることを願います。

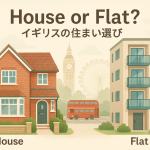








Comments