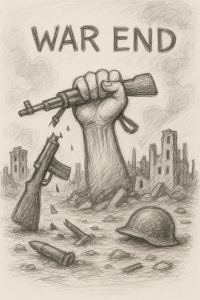
はじめに
人類の歴史を紐解くと、そこには絶え間なく戦争の影が落ちている。戦争は国家の興亡を決し、領土を塗り替え、文明の行く末を変えてきた。しかし、果たして戦争に「勝者」は存在するのだろうか。
イギリスという国は、その長い歴史の中で多くの戦争を経験してきた。100年戦争、ナポレオン戦争、第一次・第二次世界大戦、フォークランド紛争、そして現在に至るまで、直接的・間接的に様々な戦いに関与してきた。その中で形成された「イギリス人の戦争観」は、勝者と敗者の単純な二元論では語りきれない、もっと深く複雑な哲学的視座を内包している。
この論考では、「戦争に正式な勝者はいない。たとえその国が一時的に滅びても、どこかで生き残った同胞が時を経て復讐し、また戦争が始まる。そしてまたどこかの国が滅びる。その繰り返しの中で、最も苦しむのは常に一般市民である」という視点から、イギリス的戦争論を考察していく。
1. イギリス史に見る戦争と記憶の連鎖
1.1 経験としての戦争
イギリスは「島国」であるがゆえに、地理的には大陸国家ほど頻繁に侵略されてはいない。しかしその一方で、イギリスは常に「他国の戦争」に介入し、また自らも植民地帝国として世界中の戦争を引き起こしてきた。彼らにとって、戦争とは遠くの世界の話ではなく、国家のアイデンティティと密接に結びついた「経験」そのものである。
1.2 「勝った」とは何か?
イギリスは第二次世界大戦に「勝った」側に属している。だが、勝利の代償はあまりに大きかった。空襲で焼け落ちたロンドン、兵士として送り出された若者たちの喪失、経済的破綻、そして「大英帝国」の終焉。チャーチルは確かにヒトラーを打ち倒すために立ち上がったが、戦後のイギリスは、もはや世界を支配する超大国ではなかった。
このような体験から、イギリス人の間には「戦争に勝っても、それは本当の意味での勝利ではない」という認識が根を下ろしていった。
2. 復讐と報復の連鎖
2.1 歴史は繰り返す
戦争が終わった直後は、たしかに平和が訪れる。しかしその平和は、かつての敗者が悔しさを胸に秘め、復讐の機会を待ち続ける「潜在的戦争状態」に過ぎないことが多い。
第一次世界大戦の敗北国ドイツは、ヴェルサイユ条約という屈辱的な和平の中で、国民の誇りを奪われた。その憎しみと屈辱が、ナチス・ドイツという復讐の塊となって再び火を噴いたことは、歴史の証言である。
イギリス人はこのような歴史の循環に対して、ある種の冷笑的な諦念を持っている。「戦争は終わらない。ただ時間が空く。そしてその間に、次の戦争の芽が育つだけだ」と。
2.2 帝国の記憶、植民地の怒り
イギリスがかつて築いた植民地帝国の影も、この「復讐と報復」の論理に当てはまる。インド、アイルランド、中東、アフリカ。イギリスによって統治され、抑圧された人々の記憶は、国家の独立を勝ち取った後も「植民者への憎しみ」として引き継がれている。
現代の国際政治においても、テロや地域紛争の根には、こうした植民地支配の記憶が色濃く残っている。イギリス人は、かつての「帝国の栄光」が、同時に未来への「報復の種」でもあることをよく知っているのだ。
3. 一般市民こそ最大の犠牲者
3.1 軍人ではなく、民間人が死ぬ時代
かつての戦争は、軍隊同士の「戦場」での戦いだった。しかし現代の戦争では、空爆、テロ、経済制裁、ハイブリッド戦争といった新しい形が主流になっており、最も犠牲になるのは一般市民である。
第二次世界大戦中のロンドン大空襲、現代のガザ紛争、ウクライナ侵攻。どの戦争を取っても、民間人の死者は膨大な数にのぼる。食料や水が絶たれ、日常が破壊され、未来を持っていたはずの子供たちが命を落とす。
イギリス人の多くは、戦争の最も悲劇的な側面がこの「市民の犠牲」であることを痛感している。そしてその犠牲がまた、新たな憎しみと報復の連鎖を生む温床となる。
3.2 メディアと戦争の感情
イギリスのメディアは、戦争に対して常に「二重の視点」を持って報道している。一方で国益を守るための「正義の戦争」として描く一方、もう一方では被害を受ける市民への共感と人道的懸念を伝える。
このような情報の重層性は、イギリス人の戦争観に深い複雑性を与えている。勝ったはずの戦争にも、常に「哀しみ」が残る。負けた国だけが不幸なのではなく、勝った国もまた、癒えない傷を抱え続ける。
4. 「戦争に勝者はいない」という哲学
4.1 栄光の陰にある無意味さ
イギリスの詩人ウィルフレッド・オーウェンは、第一次世界大戦に従軍し、戦場で命を落とした若き詩人である。彼の詩「Dulce et Decorum est」は、戦争の栄光を称える古代ローマの言葉に対して、次のように反駁する。
It is a lie to say, “It is sweet and fitting to die for one’s country.”
この詩に象徴されるように、イギリスの知識人層には、戦争における「栄光」というものがいかに虚構であるかを冷静に見抜く視点がある。死者の山、破壊された都市、精神を病んだ兵士たち。それらの現実の前では、「勝利」はただの言葉に過ぎない。
4.2 記憶と対話こそが平和への道
戦争は避けられないと考える者もいる。しかしイギリスでは、「記憶を風化させないこと」「対話を続けること」によって、連鎖を断ち切ろうとする努力もなされている。
ロンドンには多くの戦争記念碑があり、戦没者追悼式が毎年行われる。しかしそれは、戦争を称えるためではなく、二度と繰り返さないための「警鐘」として存在している。
また、EU離脱後の外交関係においても、イギリスは対話と協調の重要性を再認識している。軍事力だけでは、報復の連鎖を断ち切ることはできないという現実が、そこにある。
結論:終わらない戦争の中で、我々ができること
イギリス人が持つ戦争論の核心には、明確なメッセージがある。それは、「戦争に正式な勝者はいない」という冷厳な現実であり、「戦争は復讐の連鎖を生むだけである」という歴史的教訓である。
国家が栄え、または滅びようとも、その国の民は生き延び、記憶を抱いて次の時代へとつなげる。そして復讐の炎は、数年後、数十年後にまた燃え上がる。勝者は敗者を生み、敗者はまた勝者を目指す――それが戦争という名の終わりなき循環である。
その中で、常に犠牲になるのは一般市民である。彼らは戦争を望んでいないにもかかわらず、最も深く傷つき、最も多く命を落とす。
イギリス人が戦争を語るとき、それは単なる国家戦略や軍事の話ではない。そこには、人間の弱さ、社会の愚かさ、そして何より「二度と繰り返したくない」という切実な願いが込められている。
だからこそ我々は、過去を記憶し、対話を重ね、報復の連鎖を断ち切る努力を続けなければならない。戦争に勝者がいないのならば、平和こそが唯一の「勝利」なのである。









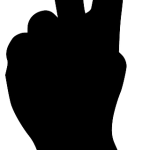
Comments