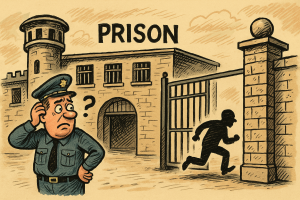
国民の安心だけはなぜか収監され続けている
イギリスの刑務所が、またしても堂々と“社会への嫌がらせ”のような出来事を起こした。
性犯罪で有罪となっていた ブラヒム・カドゥール=シェリフ が、誤って釈放されたのである。
これは「事務の手違い」と説明されているが、強姦犯を「うっかり外に出す」国家運営は、もはやコメディとスリラーの中間である。
「まさか釈放していい人物を間違えた?」
いや、そのまさかだ。
だが、悲劇は単発では終わらない。
同じ時期、同じくHMPワンズワースでは、詐欺罪で有罪となった ビリー・スミス も間違って“自由”を与えられた。
こちらは後に自ら出頭したが、国家の管理能力の方は戻ってきた様子が見えない。
■ 「人間なんだからミスもあるよね?」で済む話ではない
今回の一連の誤釈放劇は、
「書類の確認が甘かった」という、家庭内の買い物メモレベルの言い訳で処理されている。
しかし失われたのは
家に必要な牛乳ではなく、
社会の安全である。
安全保障が「まあ、見間違えたんですけどね〜」で片づけられる国。
警告音のボリュームは、最大にすべきだ。
■ 「また」起きることの恐ろしさ
誤釈放は今回が初めてではない。
誤放免は近年増加しており、もはや
「イギリス刑務所恒例の季節行事」
といっても差し支えない。
そのうちニュースでこう流れるだろう:
「今年の誤釈放、開幕です」
笑えないのに、笑うしかない。
■ 紙と記憶で運用される 21世紀の治安システム
驚くことに、囚人管理の一部は今も紙ベース。
そして職員は人員不足。
つまり管理は、職員の記憶と勘 に支えられている。
国民の命は、
「この名前、見たことある気がするけどまあいいか」で決まるらしい。
それはもはや運営ではなく、占いである。
■ 一般市民が取るべき自衛
本来、国が行うべき護りを、今は市民が自分で補う必要がある。
- 地域の防犯・不審者情報をチェックする
面倒だが“知らない”は最も危険。 - 夜間の人気のない場所は避ける
悲しいが、現実的なリスク回避。 - 不安を感じたら、理由なくても逃げる
直感は身体が学習した経験の結晶。 - スマホの位置情報・防犯アプリは遠慮なく使う
国家が信用できないなら、技術に頼ればいい。 - 「自分は狙われない」と思わない
犯罪者は“油断している人”を選ぶだけ。
■ そして最も重要なこと
「おかしいことはおかしい」と言い続けること。
声を上げなければ、それは“許容された仕様”になる。
・議員・自治体への意見
・署名
・SNSでの共有
・単純に「笑い話にしない姿勢」
これは政治活動ではなく、
自分の生活圏を守るための最低限の行為 だ。
■ 終わりに
自由になったのは囚人で、
不安を抱え続けるのは市民だった。
鍵を預けたはずの相手が鍵を無くしたのなら、
その扉の前に立つのは 自分自身 である。
安全とは、与えられるものではなく、
今は 守り取るもの になってしまった。





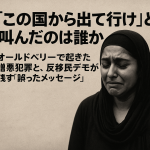
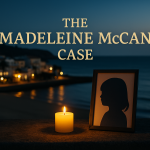


Comments