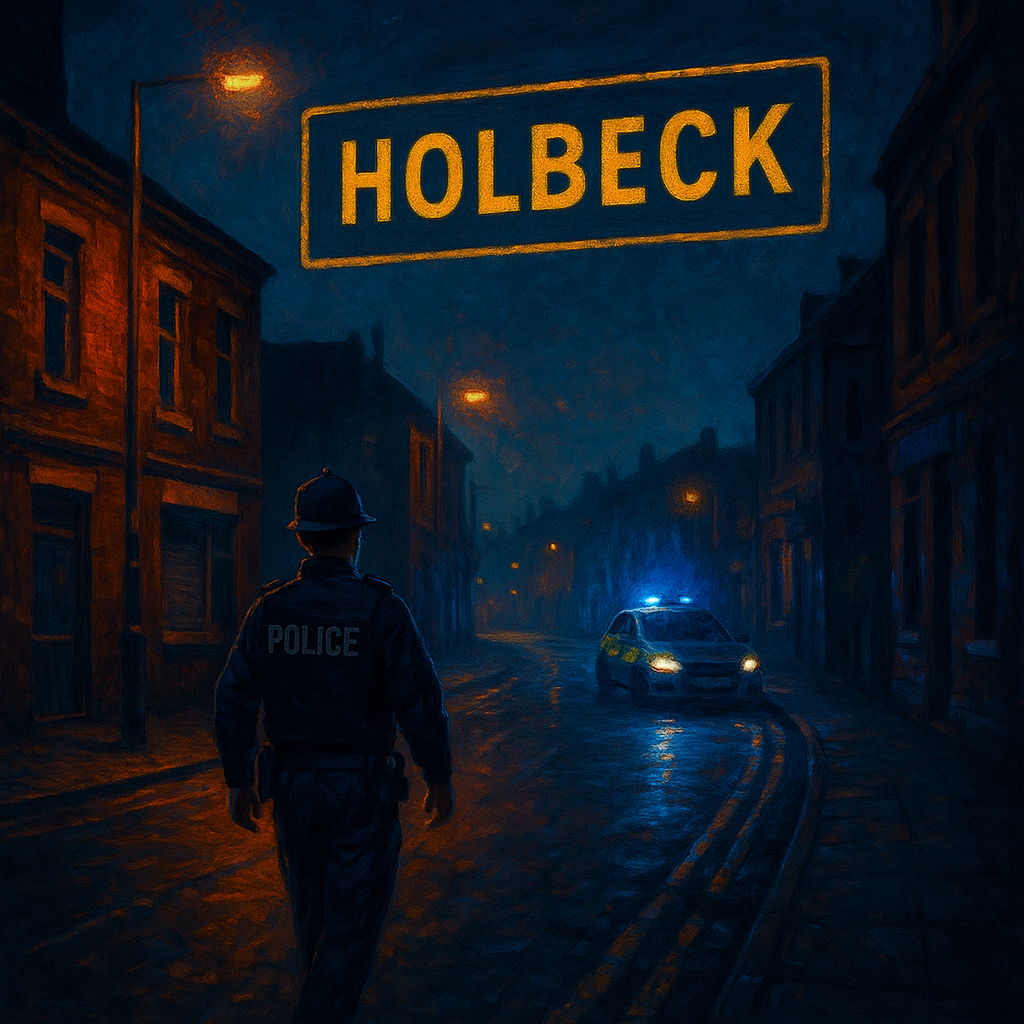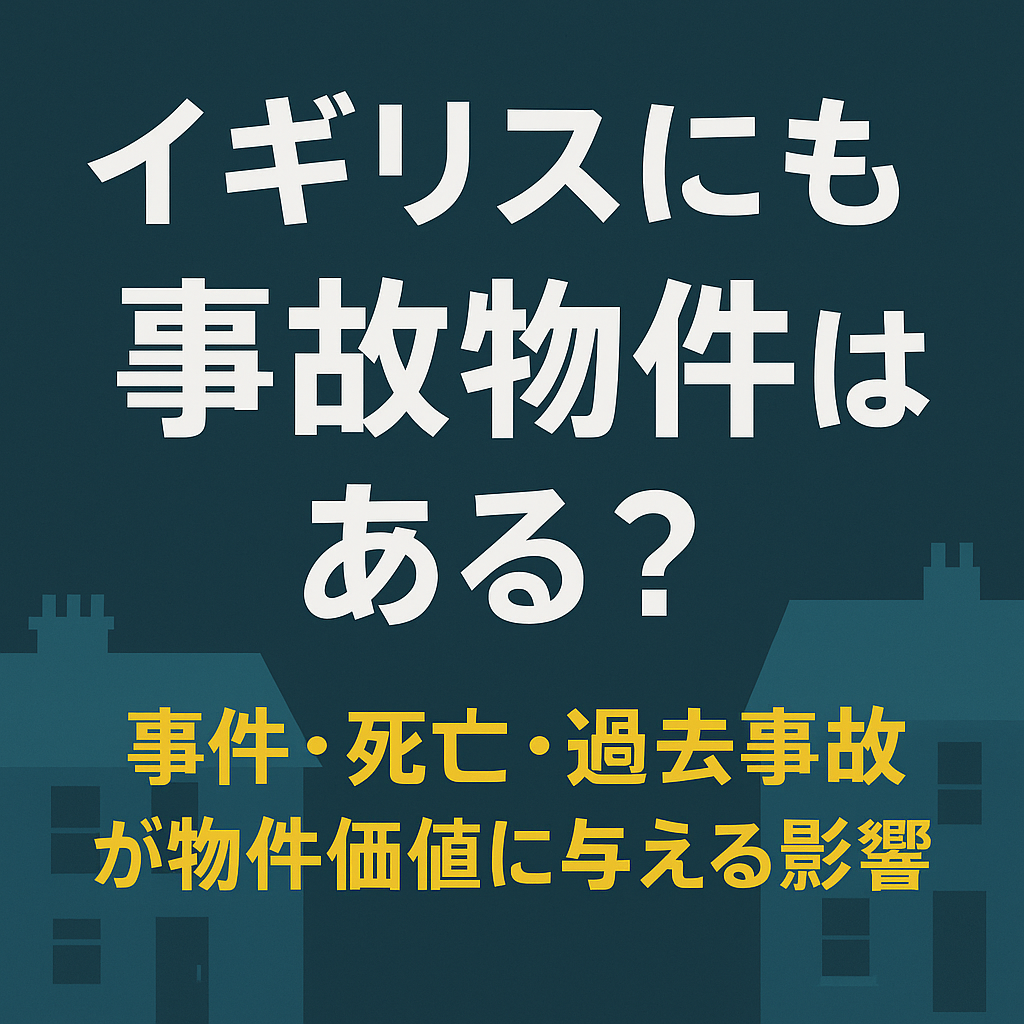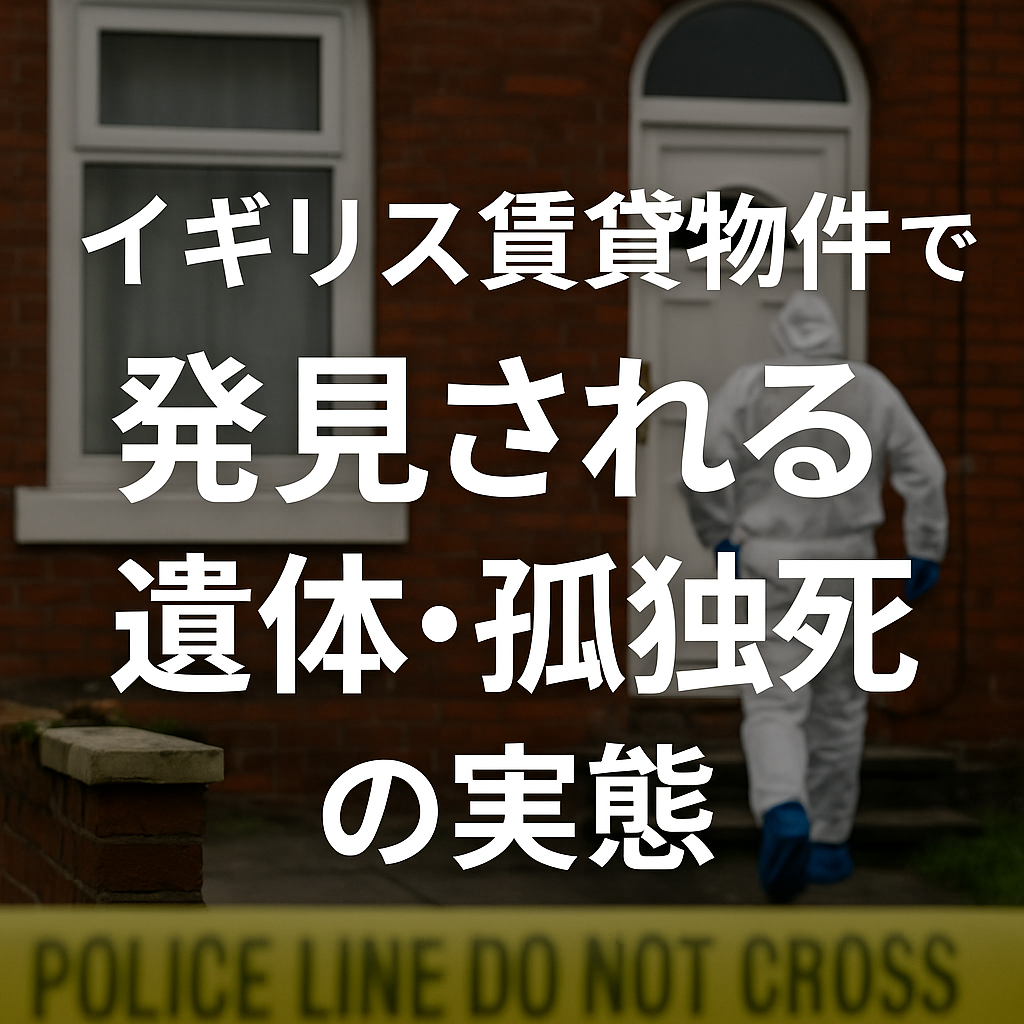…
Author:admin
【イギリス・リーズ】ホルベック地区の治安と“売春許可ゾーン”の実態【2025年最新版】
…
イギリスにも事故物件はある?事件・死亡・スティグマ物件の実態と法律対応
…
イギリス賃貸物件で発見される遺体・孤独死の実態|スタッフが直面する最悪のケースと予防策
…
イギリスの賃貸トラブル完全ガイド|ガス爆発・水漏れ・ネズミ被害など最悪のケースと対処法
…
イギリス賃貸市場の現実|「自分の物件が世界一」と信じる家主がはびこる理由と背景
…
イギリスの不動産会社の利益の仕組み|仲介・管理・手数料・ビジネスモデルを徹底解説
…
イギリスの不動産仲介の仕組み|仲介手数料・賃貸の流れ・注意点まで解説
…
イギリスで日本キャラクターが知られない理由|PlayStationとマリオに見る認知度の差と最新事情
…
イギリスでの出産ガイド|NHSの仕組み・費用・手続き・出産までの流れを完全解説
…