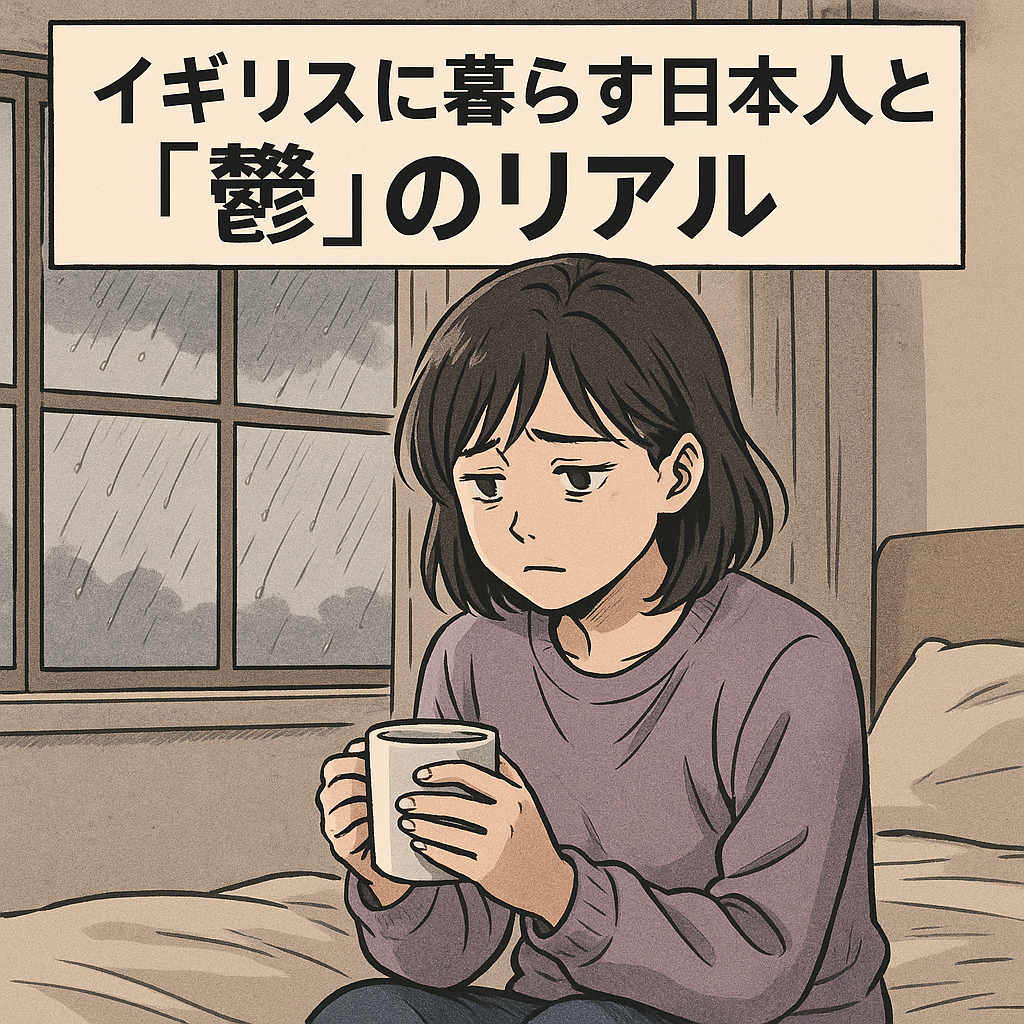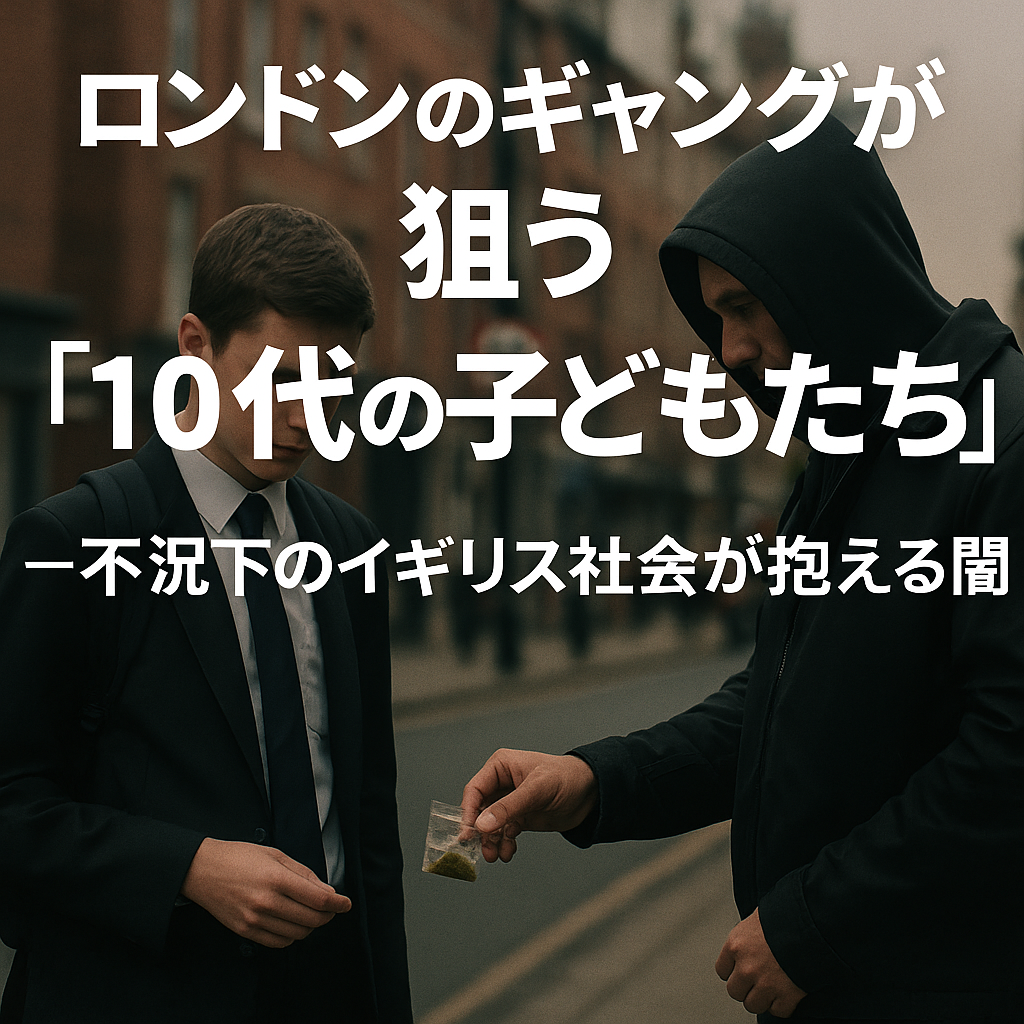…
Author:admin
9月13日 ロンドン市内で反人種差別デモ行進 ― 日本人参加者への注意点
…
イギリスに暮らす日本人と「鬱」のリアル
…
イギリスにおけるタバコとアルコール
…
イギリスで広がる反移民感情と右傾化への懸念
…
「This is my country」と叫ぶユーチューバーの欺瞞 ― イギリスと日本に見る“排外エンタメ”の危険性
…
不法移民と生活保護をめぐる神話 ― イギリス社会に広がる誤解を解きほぐす
…
ロンドンのギャングが狙う「10代の子どもたち」——不況下のイギリス社会が抱える闇
…
イギリスのフードデリバリーサービス ― 拡大する市場と揺らぐ足元
…
ロンドンにおけるストライキ文化 ― 公共交通とNHSをめぐる労働者たちの闘い
…