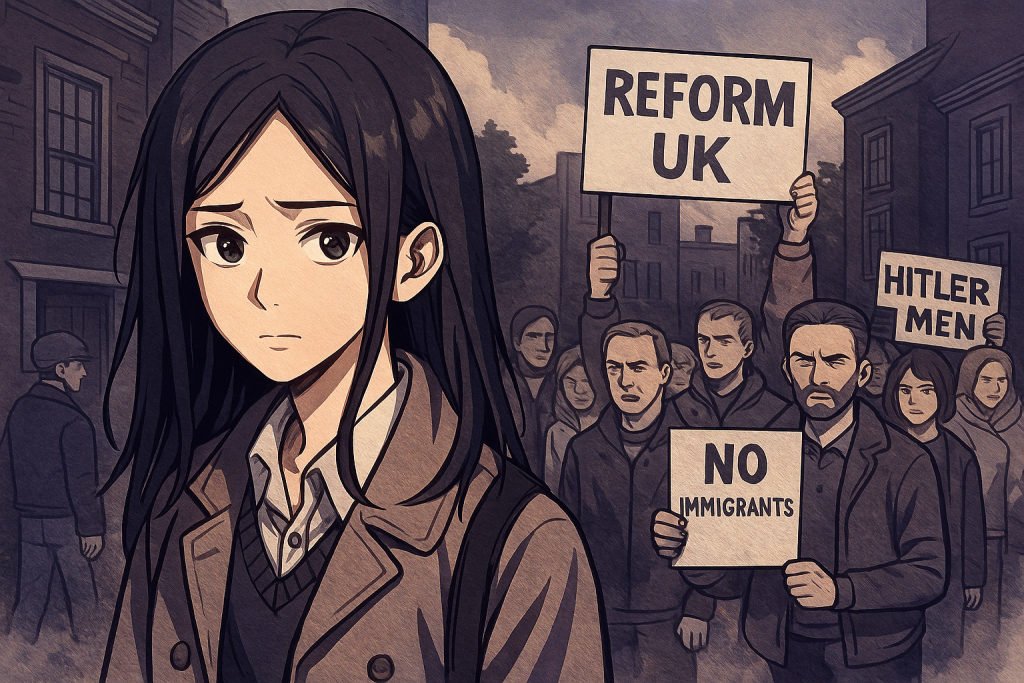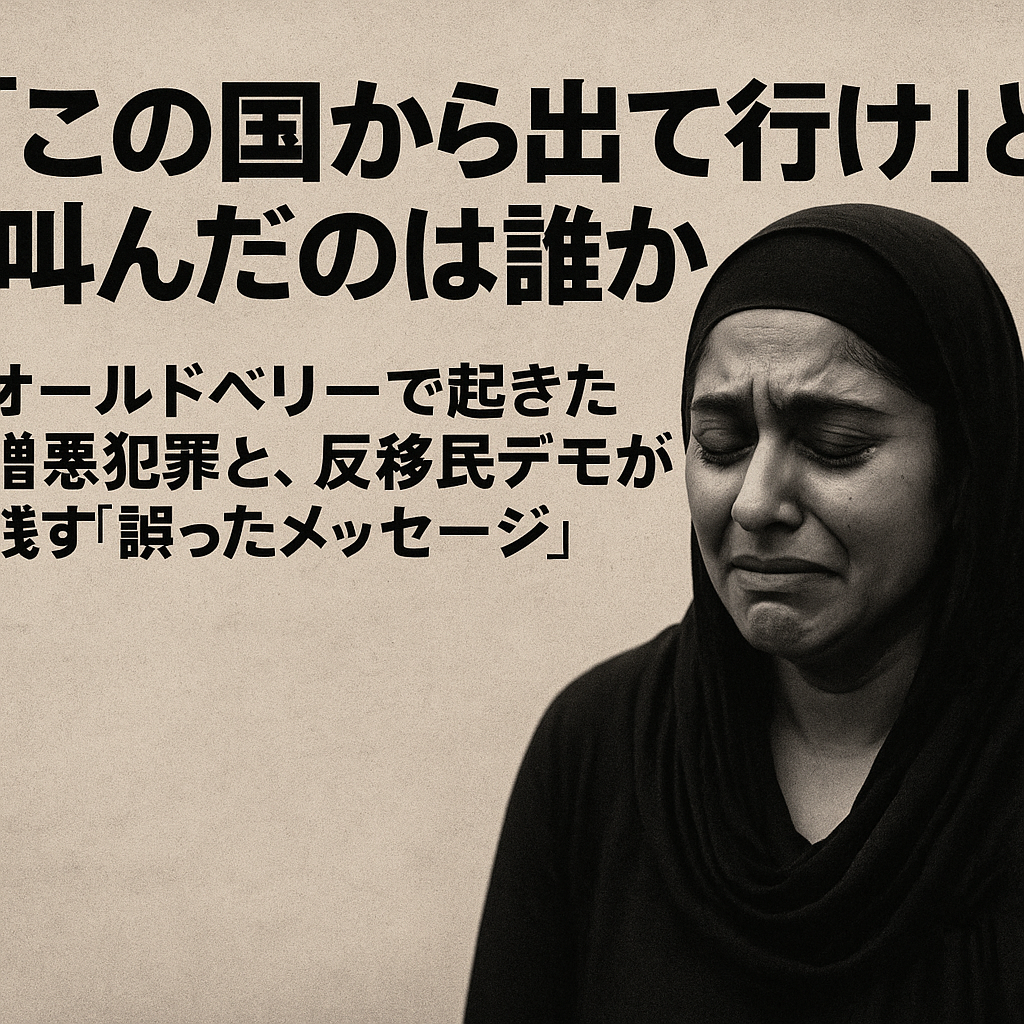…
人種差別
イギリスを震撼させた極右過激派のテロ計画―BBC報道に世界が衝撃
…
イギリスで深刻化するヘイトクライム――白人以外が安心して暮らせない国に?プロサッカー選手も標的に
…
イギリスで宗教や人種差別による攻撃から外国人が身を守る方法【ヘイトクライム対策ガイド】
…
Reform UK がもたらす「差別主義社会」の危険性
…
「この国から出て行け」と叫んだのは誰か――オールドベリーで起きた憎悪犯罪と、反移民デモが残す“誤ったメッセージ”
…
9月13日 ロンドン市内で反人種差別デモ行進 ― 日本人参加者への注意点
…
イギリスで広がる反移民感情と右傾化への懸念
…
「This is my country」と叫ぶユーチューバーの欺瞞 ― イギリスと日本に見る“排外エンタメ”の危険性
…
イングランドの国旗とレイシズム:偏見か現実か
…