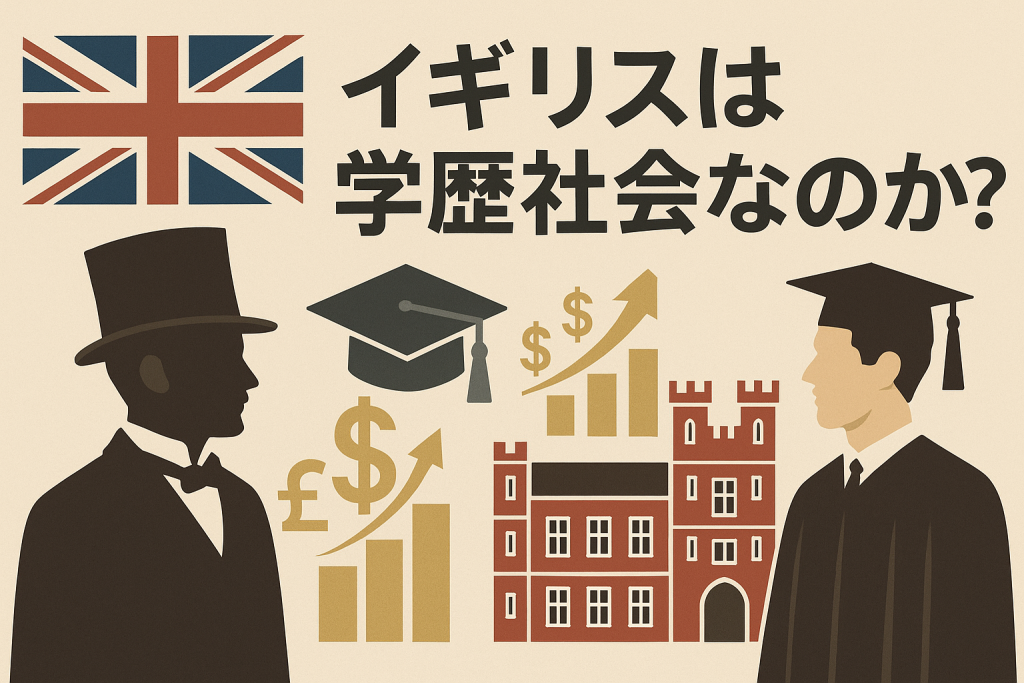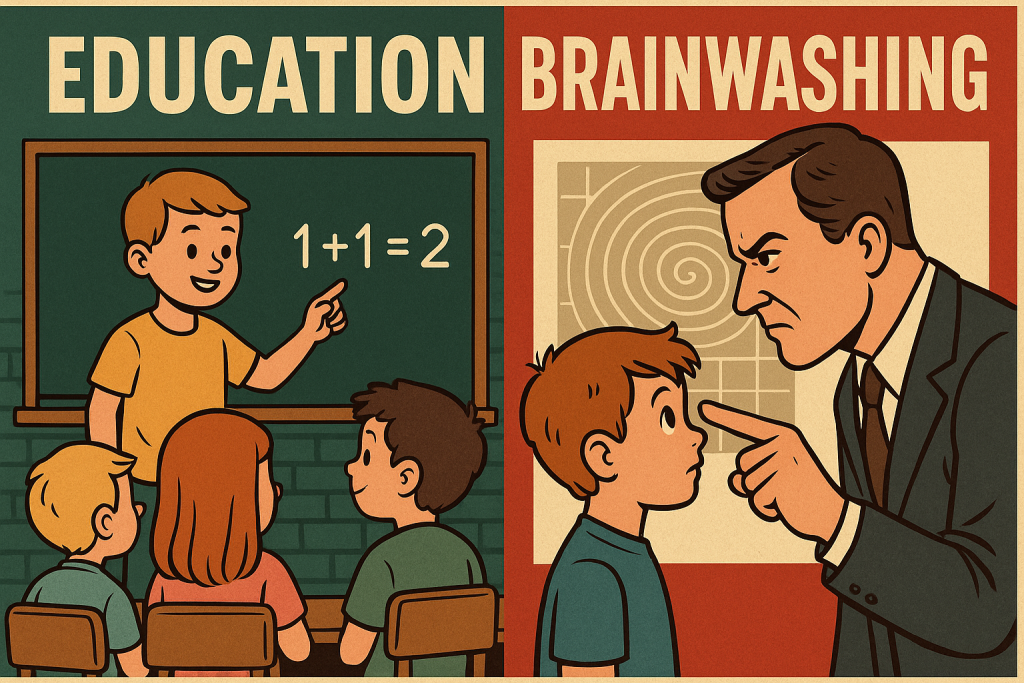…
教育
イギリスの学校制度や教育事情をわかりやすく紹介しています。ナーサリー(幼稚園)から小学校・中学・高校・大学までの教育システムの仕組み、学期制度や入学時期、学費、制服、そして留学や現地校・インターナショナルスクールの違いなどを詳しく解説。実際に子どもを英国の学校へ通わせている家庭の体験談も交え、在英日本人が安心して教育を選べるようサポートします。これから留学を考える方にも役立つ情報を発信しています。
イギリスでの学校の選び方|種類・学費・出願手順まで徹底ガイド【2025年最新版】
…
イギリスでのプライマリースクールの探し方と申し込み方法
…
競争を忘れた国の行き着いた先 ― イギリス教育の代償
…
教育と洗脳のあいだ ― 学校という場の再考
…
否定と肯定の教育文化――イギリスと日本の教育に見る自己形成の違い
…
子どもを犯罪者にしないために──イギリス式プロファイリングが示す「承認欲求」と育児のバランス
…
ベッカム論文とテイラー・スウィフト学——イギリス三流大学が切り拓く“新時代アカデミア”
…
イギリスの幼稚園教育の現場における課題:体罰と資格制度の現実
…
イギリス上流階級の子育てと躾の真実:本当のお金持ちはなぜ子どもに厳しいのか?
…
イギリスで最も高学歴・高収入なのは誰か?人種別データで読み解く教育と所得格差の実態
…
なぜ日本人は英語が上手くならないのか?― 日本の英語教育と文化的背景を徹底解剖 ―
…