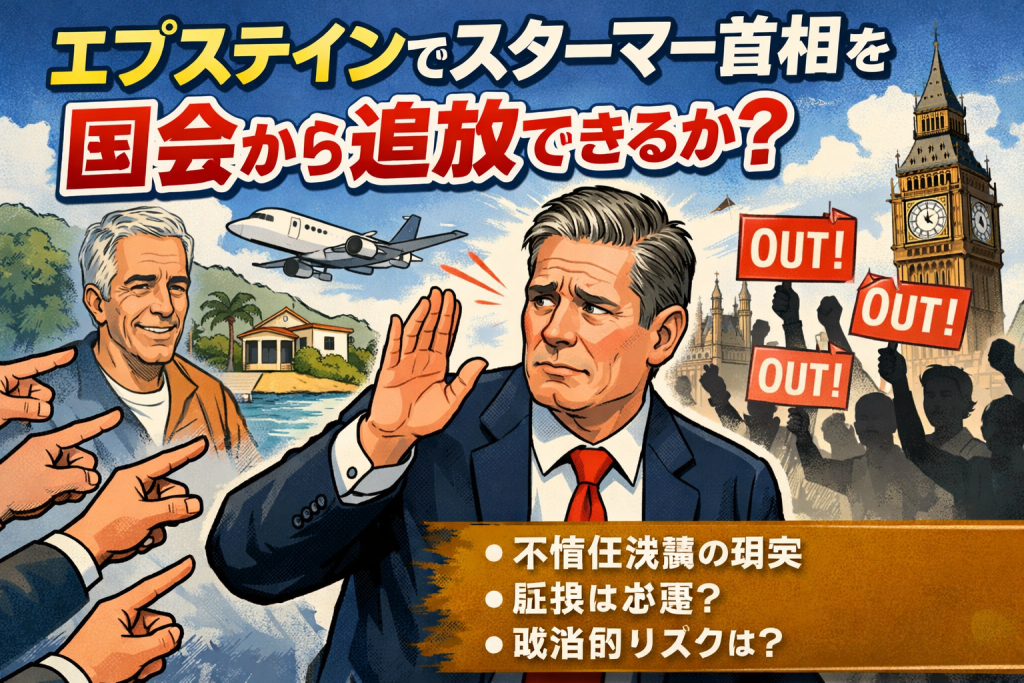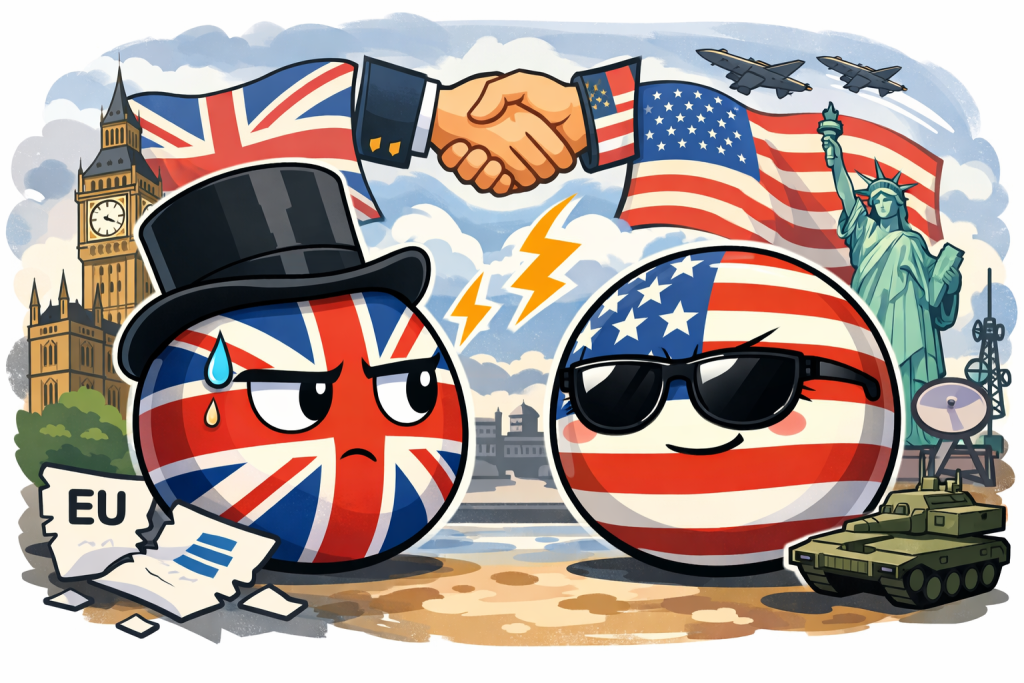…
政治
エプステイン問題をネタにスターマー英首相を国会から追い出すことは可能か?
…
イギリス政府はカナダと同じ道を歩むのか?――中国と親密な関係を築く可能性を探る
…
なぜイギリスはアメリカに強く言えないのか
…
イギリスは中国にどの程度依存しているのか
…
なぜアメリカは世界の問題に深く関わり、イギリスは「蚊帳の外」に見えるのか
…
アメリカとイギリスにおける国家形成と移民をめぐる政治構造の差異
…
政治家が言う「生活コストの改善」とは実際になんなのか
…
「普通の白人家族が見えない」と語った英国議員発言に揺れる英国社会――在英日本人が感じた“居場所”の揺らぎ
…
【2025年版】イギリスはEUに再加盟するしかないのか|経済停滞と国際的孤立を打破する現実的シナリオ
…