
序章:「冷酷」という言葉が飛び交う中で
ガザの地で、子供たちが命を落とし、家族を失い、飢えと恐怖に晒されながら生き延びている。「人道支援が届かない」「病院が機能しない」「水も電気もない」といったニュースが連日流れてくる。そんな凄惨な現実を、世界は画面越しに「鑑賞」している。
あるイギリスのニュース番組では、ガザを封鎖するイスラエルの強硬姿勢が「冷酷だ」と非難されていた。そしてそのニュースを、さらに多くのイギリス人がテレビやSNSで見て、「イスラエルは残酷だ」と批判を口にしている。
だが、私はふと思ったのだ。
本当に「冷酷」なのは誰なのか?
第1章:対岸の火事、という無意識な傍観
「対岸の火事」という言葉がある。これは、他人の不幸や困難をまるで自分には関係のないものとして眺める姿勢を示す言葉だ。
ガザとイスラエルの対立を、ロンドンのカフェでコーヒーを飲みながら批判できる者。X(旧Twitter)で「#FreePalestine」とハッシュタグを付けて投稿することで満足する者。あるいは、何も言わず、ただ無関心にスクロールし続ける者。
こうした人々は、ガザにミサイルが降り注ぐ瞬間、イスラエルの子供がロケット弾のアラートで地下に逃げ込むその瞬間に、ソファに座りながらポテトチップスをつまんでいる。
どこかで命が奪われているという現実に対し、私たちはどれだけ本気で「向き合っている」と言えるだろうか。
第2章:イスラエルの「高みの見物」への視線
確かに、イスラエル国内の一部には、ガザで起きていることを「当然の報復」と見なす者がいる。極端な右派は「ガザを地図から消せ」とさえ言う。
しかし、全てのイスラエル人がそうではない。毎週のように平和を訴えるデモに参加しているイスラエル人もいれば、パレスチナ人の命を救おうとする医療従事者もいる。そうした声は、国際メディアにはあまり届かない。
イギリス人ジャーナリストが「イスラエルは非人道的だ」と書いた記事を読みながら、ふと私はこう思った。
「それを安全な土地から言うのは簡単ではないか?」
第3章:イギリスという「安全圏」からの批判の構造
イギリスは確かに戦火から遠い。爆撃の音は聞こえず、空爆の心配もない。日常が普通に営まれ、インフレや選挙、スポーツの話題が人々の関心をさらっていく。
そんな中で、イスラエルを一方的に非難することは簡単だ。なぜなら、それは「正しそう」に見えるからだ。道徳的優位に立ち、「戦争反対」「子供を守れ」と唱えれば、拍手喝采がもらえる構造がある。
しかし、その批判は本当にガザの人々に寄り添っているのだろうか?
本当に声を届けたい相手は誰なのか?
もしかすると、それは**「正しさを消費したい自分自身の欲求」**にすぎないのではないか?
第4章:ガザの「今この瞬間」にある現実
2025年の今も、ガザでは医療インフラが崩壊し、数十万人が避難生活を余儀なくされている。10歳にも満たない子どもたちが、爆音で目を覚まし、両親の死を受け入れざるを得ない日常を生きている。
そしてその隣に、武装した兵士や、ドローンで監視する目がある。さらには、イスラエル国内の一部では花火が上がり、「やったぞ」と歓声を上げる群衆もいる。まさに**「高みの見物」**と批判したくなる状況だ。
だがそれを見て、「なんて残酷な民族だ」と言ってしまうイギリス人がいたとしたら、それは表面的な理解でしかない。戦争の構造、国家の歴史、宗教的な衝突、占領政策、ハマスの支配体制、こうした複雑な要素を一つの視点で切り取ることの危険性を、私たちは忘れてはならない。
第5章:「見るだけ」の私たちの冷酷さ
テレビやSNSを通じて、ガザでの悲劇を「見るだけ」で終えてしまう私たち。その場に行くわけでもなく、寄付をするわけでもなく、ただ「かわいそう」と感じて満足している。その一方で、イスラエル側だけを悪者にして安心する。
この構造に、私は強い違和感を抱く。
「見るだけ」で何も動かないということは、つまり、見殺しにしているということだ。
それは、「冷酷」ではないのか?
自分の手を汚さず、傷つかず、リスクを負わず、他人の悲劇を言葉だけで消費する私たちは、「冷酷」と呼ばれるに値しないのか?
終章:私たちにできることは「批判」ではなく「関与」
戦争は残酷だ。誰が正しい、誰が悪い、という単純な構図では測れない。ただ一つ確かなのは、「苦しんでいる人が今この瞬間にもいる」という事実だ。
そして、私たちにできることは、「誰かを冷酷と批判すること」ではなく、「自分が冷酷にならないように、関与すること」ではないだろうか。
寄付をすること。教育に関心を持つこと。選挙で中東政策を問うこと。現地の声を直接聞こうと努力すること。批判するよりも、耳を傾けること。
それは小さな一歩かもしれない。だが、**冷酷さとは「何もしないこと」**なのだ。
だったら、まずは自分が「何かをする人間」になりたい。
まとめ
「冷酷だ」と誰かを指差す前に、自分自身の中にある冷酷さと向き合わなければならない。
遠くから石を投げるのではなく、目をそらさず、関与し続ける。
その積み重ねこそが、ガザで苦しむ子どもたちにとっての、たった一筋の希望かもしれないのだ。
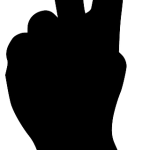









Comments