
街角で赤いベストを着たボランティアが声をかけてくる。スーパーマーケットの出入り口に設置された募金箱、あるいはテレビCMで流れる「あなたの1ポンドが命を救う」という訴え。イギリスでは、募金活動(チャリティ)の文化が日常のあらゆる場面に根付いている。だが、多くの人々が同時に抱えているのは、「この募金、本当に困っている人に届いているのか?」という疑念だ。
■ チャリティ大国・イギリス
イギリスは世界でも有数の「チャリティ大国」として知られている。英国内には約16万を超える登録済みのチャリティ団体が存在しており、Charity Commission(慈善団体委員会)によって監督されている。教育、医療、動物保護、難民支援、途上国援助、環境保護など、その活動内容は多岐にわたる。
例えば、世界的に有名な「オックスファム(Oxfam)」はイギリス発の国際NGOであり、途上国の貧困削減を目的としている。また「セーブ・ザ・チルドレン(Save the Children)」も、イギリスに本部を持つ国際的な子ども支援団体だ。国内の貧困層を支援する団体も数多く、特にフードバンクの運営に携わる「トラッセル・トラスト(The Trussell Trust)」などは、コロナ禍以降に支援要請が急増した団体として知られている。
■ 募金活動の手法:街頭からデジタルへ
イギリスのチャリティ活動は、方法も多様だ。古典的な街頭募金はもちろん、テレビやラジオでの募金キャンペーン、チャリティイベント、スポーツチャリティ(マラソンやチャリティバイクなど)、さらにはSNSやクラウドファンディングを使ったデジタル募金も盛んである。
特に「Comic Relief」や「Children in Need」といったテレビ番組と連動した募金キャンペーンは、国民的行事とも言えるほどの認知度を持っており、毎年数千万ポンドを集めている。
また、イギリスの税制には「Gift Aid(ギフト・エイド)」という制度があり、募金者が納税者であれば、その寄付に対して政府が一定の割合(25%)を上乗せしてチャリティ団体に支払う。これは寄付を促進する重要な仕組みとして機能している。
■ お金はどこに行くのか?募金者の不安
これだけチャリティ活動が活発なイギリスだが、「募金がどこに行くのかわからない」「本当に役立っているのか不透明」といった不安を抱く人は少なくない。
実際、イギリスの調査会社YouGovが行った世論調査(2023年)によると、「チャリティ団体に対する信頼度が低下している」と答えた人は全体の38%に上る。また、「募金の使途が明確でないことが寄付をためらう理由である」と回答した人は全体の45%にも達している。
こうした懸念が表面化したのが、2015年に発覚したいくつかのチャリティ団体による不正会計事件や、募金者に対して過剰にしつこい連絡が繰り返されたことによるスキャンダルである。中には、高齢者が電話勧誘によって複数の団体に大金を寄付し、生活が困窮したという事例も報道された。
■ チャリティ団体の構造と使途の内訳
イギリスでは、チャリティ団体の収入源の大部分が個人や企業からの寄付であるが、それと同時に政府からの補助金、商業活動からの収益(チャリティショップなど)も存在する。
例えば、2022年度のデータによると、イギリスのチャリティ団体全体の収入は約840億ポンド(約15兆円)にのぼる。そのうちの約40%が個人寄付から、30%が政府補助、残りが投資収益やチャリティショップなどの事業収入である。
ただし、集まったお金のすべてが直接的な支援活動に使われるわけではない。多くのチャリティ団体では、以下のような費用がかかる:
- 管理費・運営費(人件費、事務所維持など):平均で全体の15〜30%
- 募金活動コスト(広告宣伝、イベント開催費など):平均で10〜20%
- 現場活動費(実際の支援対象に使われる部分):約50〜70%
つまり、1ポンドの寄付のうち、0.50〜0.70ポンド程度が実際の支援に回されるのが一般的とされる。
この割合が低い団体は「効率が悪い」「資金の無駄遣い」とされて批判されることがあるが、逆に管理体制をしっかり構築するためには一定の管理費が必要であるというジレンマも存在する。
■ チャリティ評価サイトの台頭と市民の行動変容
こうした状況に対応する形で、近年は「どの団体に寄付すべきか」を支援する評価機関や比較サイトも登場している。代表的なのが「Charity Navigator」「GiveWell」などで、団体の透明性、財務健全性、インパクト評価などをもとにスコアを提示している。
また、寄付をする側も「ただ寄付する」のではなく、「寄付先を吟味する」「毎月定額を小規模団体に分配する」といった戦略的な行動を取る傾向が強まっている。
■ イギリス人も迷っている:「善意の使い道」に対する不安
イギリス人の間でも、「善意の気持ちが正しく伝わっていないかもしれない」という懸念は根強い。特に以下のような声がよく聞かれる:
- 「CMで豪華な映像を流しているチャリティは、そんなお金があるなら現地支援に回すべきでは?」
- 「CEOが高給をもらっている団体には寄付したくない」
- 「できるだけ現場に近い、小規模で地道な団体を探している」
このように、寄付に対する意識は「感情的なもの」から「合理的で情報に基づく行動」へと変わりつつある。
■ まとめ:「寄付は信頼から始まる」
イギリスにおける募金文化は長い歴史と制度的な支えによって発展してきた。しかし、善意の行動であるはずの募金が、いつしか「疑念」や「不信感」と隣り合わせになるようになった背景には、情報の透明性や説明責任の不足がある。
一方で、評価サイトや寄付プラットフォームの進化、市民の意識の成熟といったポジティブな動きも見られる。今後、チャリティ団体側がいかに透明性を確保し、寄付者との信頼関係を築けるかが、募金文化の未来を左右すると言えるだろう。
「その1ポンドは、どこに行くのか?」
この問いに納得できる答えを得られることが、今のイギリス社会にとって、最も重要な課題である。






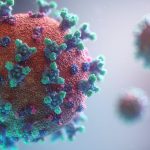



Comments