
中東という地域を語るとき、しばしば浮かび上がるのは混沌、宗教対立、石油利権、そして絶え間ない紛争である。そんな中で、まるで異物のように存在するのがイスラエルという国家だ。ユダヤ人国家として1948年に建国されて以来、イスラエルは自らを取り囲むアラブ諸国と幾度も戦い、時に外交的孤立に陥りながらも、今日に至るまでその地位を強固に築いてきた。
本稿では、中東におけるイスラエルの「味方」とされる存在、アメリカの軍事的関与、そしてイスラエルの“強さ”の根源に迫り、その地政学的現実と精神的基盤を多角的に読み解いていく。
■ 中東で「味方」となりうる国々:敵か、共通の利害か
中東でイスラエルを公然と支持する国は極めて少数である。だが、状況は一枚岩ではない。近年、一部のアラブ諸国との関係改善が見られ、その背景には単なる外交戦略以上の地政学的現実が横たわっている。
● アブラハム合意という地殻変動
2020年、トランプ政権下で結ばれた「アブラハム合意」は、イスラエルとアラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、モロッコ、スーダンといった国々との国交正常化を実現させた。
これは単なる平和協定ではない。中東地域において、長年にわたり敵対関係にあったアラブ諸国がイスラエルとの「共存」を選んだ瞬間であり、イランという共通の脅威が、その背後にある大きな原動力であったことは否定できない。
イランの核開発やシーア派圏の拡大に脅威を感じるスンニ派アラブ諸国にとって、イスラエルはもはや「共通の敵」ではなく、「共通の守り手」としての可能性を帯び始めているのだ。
● サウジアラビアという“非公式の協力者”
サウジアラビアは、公式にはいまだイスラエルと国交を樹立していない。だが、水面下では安全保障や情報共有の分野において、静かな協力関係が築かれていると多くの報道が示唆している。
とりわけ注目すべきは、イスラエルとサウジがともにイランを最大の戦略的リスクと見なしている点である。地政学的合理性が、この二国を不可視の協力関係へと導いているのだ。
■ アメリカ軍は本当に中東から撤退したのか?
ここ数年、「アメリカは中東から手を引いた」といった報道を耳にすることがある。だが、その実態はもう少し複雑である。
● 地上戦からの「引き上げ」と駐留の現実
たしかに、アメリカはイラクやアフガニスタンといった地域から多くの地上部隊を撤退させた。長引く戦争と国内世論の疲弊を受けての決断であり、「無限戦争」に終止符を打とうとする動きでもあった。
しかしそれは、中東全体からの「完全撤退」を意味しているわけではない。カタール、クウェート、バーレーン、UAEなどには今も多数の米軍基地が存在しており、その駐留は続いている。
特にバーレーンには、アメリカ海軍の中東地域担当である第5艦隊が駐留しており、ペルシャ湾から紅海、アラビア海に至るまでの広大な海域をカバーしている。
● 軍事的「プレゼンス」から影響力の維持へ
つまり、アメリカは直接的な戦争の前線からは後退したが、中東地域における影響力は手放していない。むしろ、空軍・海軍力、そして諜報力を通じて、間接的に戦略的主導権を保持しているとも言える。
このアメリカの“後方支援”的な存在感が、イスラエルにとっては重要なセーフティーネットでもある。
■ イスラエルの「強さ」はどこから来るのか?
中東で孤立する小国イスラエル。だがその小国は、決して弱くはない。むしろ、「強すぎるがゆえに孤立している」と言った方が近いかもしれない。その強さは、単なる軍事力の話ではない。より深層に、精神的・国家的な強さが潜んでいる。
1. 軍事・技術力という「質」の防衛
イスラエルの軍事技術は、世界でも屈指の水準にある。「アイアンドーム」に代表される防空システム、最先端のサイバー戦能力、ドローン技術、さらには情報機関モサドの存在。どれをとっても小国のそれとは思えない。
加えて、徴兵制度により国民の多くが軍事訓練を受けている社会であるため、国防に対する国民的な意識も高い。
2. アメリカとの「特別な関係」
イスラエルは、年間30〜40億ドルにものぼる軍事支援をアメリカから受け取っている。この規模は世界でも異例であり、イスラエルがいかにアメリカの戦略的拠点であるかを示している。
これは単なる軍事同盟ではなく、「代理国家」的な性質を持つ。中東においてアメリカが直接軍を展開せずとも、イスラエルを通じて地域への関与を続ける構図がある。
3. 国家としての覚悟と結束
建国以来、戦争とテロにさらされ続けてきたイスラエルには、**国家存続に対する“本気度”**がある。国民一人ひとりが「もし戦争になれば戦う」という意識を持ち、国家全体が生存戦略としての防衛体制を日常的に意識している。
「我々が守らなければ、誰も守ってくれない」──この根底の意識が、外交でも軍事でもブレない行動原理となっている。
■ 「自分たちは正しい」という確信の源泉
イスラエルが強硬な姿勢をとるたび、国際社会から批判の声があがる。しかし彼らはなかなかその姿勢を変えない。その根底にあるのは、確固たる「自己正当化」の信念である。
● 宗教的確信
ユダヤ教における「選民思想」や、「神から与えられた土地」という信念が、イスラエル人にとっての土地と国家の正当性を支えている。
これは、外から見ると宗教的独善に見えることもあるが、彼らにとってはアイデンティティそのものである。
● 歴史的なトラウマ
ホロコースト、ポグロム、数世紀にわたる迫害の歴史。これらがユダヤ人に深い教訓を与えた。
「もう二度と、無力ではいられない」
このフレーズがイスラエル建国の精神的バックボーンとなっており、それは今も外交や軍事のあらゆる場面で反映されている。
● 民族的アイデンティティ
長く離散しながらも民族としての一体感を失わなかったユダヤ人たちが、自らの国家を手に入れたという事実。そこには国を持つことの意味に対する深い自覚と誇りがある。
■ 結論:イスラエルという「孤高の戦略国家」
イスラエルの強さは、兵器や支援金だけでは語れない。それは、
- 歴史に刻まれたサバイバルの記憶
- 現実的で冷徹な地政学戦略
- 自らの正義を信じて疑わない精神性
これらが絡み合いながら形成された“戦略国家”としての姿である。
その姿は時に傲慢に映る。時に絶望的なまでの覚悟に見える。しかし確かなのは、イスラエルがただの軍事国家ではなく、生存のために最適化された国家であるということだ。
その存在は、中東の混迷の中で、ひとつの“異質で孤高な光”のようにも見える。




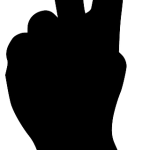





Comments