
近年、私たちが暮らす社会は「安全」の名のもとに、さまざまなものが過剰に柔らかく、無害に設計される方向へと進んでいる。刺さらないフォーク、切れないナイフ、丸みを帯びた家具の角……。一見すると人を傷つけないための優しい配慮だが、それが行き過ぎると、まるで刑務所のような世界に近づいていくのではないか、という懸念を抱く人も少なくない。
刑務所における「徹底した安全」の論理
刑務所という特殊な環境では、人を傷つける可能性が通常の社会よりも格段に高い。そこで使われる物品は、凶器となり得る要素を極力排除するように設計されている。刃物はもちろん、割れやすいガラスや硬すぎる金属なども避けられる。これは極めて合理的な判断であり、閉ざされた集団生活において暴力や自傷行為を防ぐための最低限の対策でもある。
しかし、この「安全至上主義」の思想がそのまま社会全体に広がったとき、果たしてそれは本当に望ましいのだろうか。
「危険」を取り除くことは不可能
人間が生きる環境において、危険を完全に取り除くことはできない。包丁を使えば手を切ることもあるし、自転車に乗れば転んで頭を打つこともある。階段から落ちる、熱い鍋に触れる、遊具で擦りむく――こうした日常のリスクはゼロにはできない。むしろ、危ないからこそ「注意深く扱う」「正しく使う」という学びが生まれる。
ナイフは本来よく切れるからこそ料理ができる。フォークは鋭いからこそ食べ物を刺して口に運べる。危険性と便利さは表裏一体であり、そのどちらかを完全に切り離すことはできないのだ。
教えるべきは「危険の排除」ではなく「危険との付き合い方」
本来、大人が子どもに伝えるべきは「危ないものを遠ざけること」ではなく、「危ないものとどう付き合うか」だ。
・刃物は人に向けてはいけない
・火は便利だが触れば火傷をする
・高いところでは足元に注意する
こうした具体的な知恵や習慣を教え、体験を通じて危険との距離感を学ばせることが、社会を生きるうえでの本当の教育ではないだろうか。
だが、現代では「最初から危ないものを与えない」という方向に傾きつつある。結果として、子どもたちは刃物を使った経験が乏しくなり、火や工具を前に過剰な恐怖や無知を抱えるようになる。これは一見「安全」なようでいて、実は大きなリスクを将来に先送りしているに過ぎない。
「安全第一」の果てに待つもの
もし社会全体が、刑務所と同じ発想で「危険を排除する方向」だけを進めば、人々は自分の手でリスクを判断し、コントロールする能力を失っていく。危険を知らない大人たちは、ほんの小さな事故にも対応できず、かえって被害を大きくするかもしれない。
さらに、すべてが「傷つけない仕様」に設計された世界は、ある意味で「管理された社会」とも言える。人々は危険を恐れて守られる存在となり、自由に選び取る責任を奪われる。その先には、便利さの裏で人間の主体性が薄れていく未来があるかもしれない。
大人の責任とは何か
便利で危ない道具は世の中に溢れている。だが、それを「危ないから使わない」ではなく、「危ないからこそ正しく使う」と教えることこそ、大人に課された義務ではないだろうか。
刃物を正しく使える人は、人を傷つけるためにではなく、料理を作り、暮らしを豊かにするためにそれを扱う。火を恐れすぎない人は、暖を取り、食を楽しみ、災害時に命を守る。危険を含んだ道具を「文明の知恵」としてどう生かすかを伝えることは、人間社会にとって不可欠な教育なのだ。
おわりに
「安全」とは、危険をゼロにすることではなく、危険を理解し、適切に向き合える力を持つことではないだろうか。刑務所のように徹底的に管理された環境は、ある特殊な場面では合理的かもしれない。しかし、それを日常生活にまで拡張してしまえば、人は学ぶ機会を失い、逆に弱い存在になってしまう。
大人たちが放棄してはならないのは、「危ないからダメ」と一言で片付けることではなく、「危ないけれど便利なものを、どう使えばいいのか」を伝え続けること。その姿勢こそが、健全で自由な社会を守る基盤となるのだ。








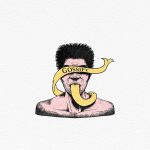

Comments