
イギリスの伝統的商店街が消えつつある背景
かつてイギリスの町や村の中心にあった「ハイストリート(商店街)」は、地域住民の交流や買い物の拠点でした。 しかし近年は、オンラインショッピングの普及や大型ショッピングモールの台頭により、伝統的商店街の多くが衰退しています。 さらに、コロナ禍を経て人々の行動パターンが変化し、地元の商店を支える構造が揺らいでいます。
① 店舗減少と現金経済の現状
調査によると、イギリス全体で2024年には1日平均37店舗が閉店したと報告されています。 特に衣料品店や小規模カフェ、書店など、地域密着型の個人経営店の撤退が目立ちます。 一方で、家族経営の雑貨店や床屋、ミニマーケットなど「現金中心」で営業を続ける店舗が残り、地域の生活を支えています。
イギリスではキャッシュレス化が進んでいますが、依然として「現金主義」の小規模店が多く、 これは商店街の文化的な特徴でもあります。現金取引は手数料を抑えやすく、経営の柔軟性が高いため、 中小零細ビジネスにとって一定の利点があります。
② 現金取引ビジネスと金融監視の強化
一方で、英国の金融当局(FCAやNCA)は、現金取引が多い小規模ビジネスの中に「資金の流れが不透明な店舗」が存在する可能性を指摘しています。 床屋・食品店・小規模スーパーなど、少額現金取引が頻発する業種では、資金洗浄(マネーロンダリング)や脱税防止の観点から監視が強化されています。
この問題は「特定の地域や民族」に限らず、**構造的に現金依存の高い業態に共通する課題**です。 政府はマネーロンダリング防止(AML)と税透明化のため、銀行との取引履歴・入出金管理を厳格化しており、 2025年には小規模ビジネスにも電子記録義務を拡大する方針を示しています。
こうした取り組みは、「犯罪対策」という側面だけでなく、 地域経済の健全化・店舗の信頼回復にもつながると期待されています。
③ 地域社会・経済への影響
現金取引型の店舗が監視対象になることで、一部の事業者は銀行口座の凍結や融資難に直面することもあります。 一方で、デジタル決済導入や会計の透明化を進める店舗は、信頼度が向上し、観光客や地域住民からの支持を得ています。
つまり、「現金主義の伝統」と「透明性の向上」の間で、イギリスの商店街は今、転換点を迎えています。
④ 商店街再生と透明性向上への取り組み
- 自治体によるデジタル決済導入支援やキャッシュレス教育の拡大。
- 商店街の空き店舗をコミュニティスペースや共有オフィスに再利用。
- 現金取引と電子会計の両立を目指す「ハイブリッド経営」モデルの推進。
- 地元銀行・信用組合による中小ビジネス支援プログラム。
これにより、伝統的な商店街の魅力を残しつつ、金融リスクを抑えた新しい形が模索されています。
⑤ 旅行者・生活者が感じる変化
旅行者が英国の商店街を歩くと、キャッシュレス決済と現金取引が混在していることに気づくでしょう。 地域によっては「現金のみ」の店舗も多く、観光客は少額の現金を持っておくと安心です。 また、地域経済を支える個人店を利用することは、地元文化や人々との交流を感じられる貴重な体験でもあります。

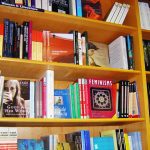








Comments