
日本において「アイドル」といえば、若くて可愛らしい外見、親しみやすさ、成長の物語、そしてファンとの距離の近さが特徴的な文化である。AKB48、乃木坂46、ももいろクローバーZといったグループが象徴するように、日本のアイドル文化は非常に独自性が高く、海外にも熱心なファンが存在するほどの影響力を持っている。
では、イギリスにも「アイドル」は存在するのだろうか?また、日本のように熱狂的な「アイドルオタク」的存在は、イギリスにもいるのだろうか?この記事では、イギリスの音楽文化・芸能事情を中心に、日本との違いや共通点を探りつつ、両国における「アイドル」と「オタク」の定義と実態について考察していく。
1. そもそも「アイドル」とは何か?:日英の文化的違い
日本における「アイドル」は、単なる歌手や俳優とは異なり、「未完成であるがゆえに応援したくなる存在」として消費される。「可愛さ」や「一生懸命さ」「ファンとの距離感」などが重要な要素であり、パフォーマンスの質よりも“人間性”が重視されることも多い。
一方、英語圏、とりわけイギリスにおいて「idol(アイドル)」という語は、アメリカの「American Idol」のように、才能や実力を競うコンテスト番組のタイトルに使われるなど、「スター性」や「完成度」を意味する場合が多い。つまり、「アイドル」という言葉は存在するが、その意味内容や文化的背景は大きく異なっている。
2. イギリスの「アイドル」的存在:ボーイバンドとガールグループ
イギリスの音楽シーンにおいて、日本のアイドルに最も近い存在といえば、やはりボーイバンドやガールグループである。たとえば:
- The Beatles(ビートルズ):1960年代の“元祖アイドル”ともいえる存在で、全世界にビートルマニア(熱狂的ファン)を生んだ。
- Spice Girls(1990年代):ガールパワーを前面に押し出し、キャラ立ちしたメンバーがファンを魅了した。
- One Direction(2010年代):オーディション番組「The X Factor」出身のボーイバンドで、ティーンエイジャーを中心に世界的なブームを巻き起こした。
これらのグループは、日本の「アイドル」にも似た側面(ビジュアル重視、ファンとの交流、SNS活用など)を持ちながらも、基本的には「音楽アーティスト」としての位置づけが強い。つまり、「アイドル的」であっても、「アイドル文化」として体系化されているわけではない。
3. ファン文化の違い:イギリスのファンと日本のオタク
日本のアイドルオタク文化:
日本では、ファンが「オタク」として自己同一化し、ライブ遠征やグッズ収集、握手会への参加などに多大なエネルギーを注ぐことが一般的である。SNSでの交流やファンコミュニティの形成も活発で、ある種の“ライフスタイル”として確立している。
イギリスのファン文化:
イギリスにももちろん熱狂的なファンは存在する。One DirectionやLittle MixのファンはSNSで自作のファンアートを投稿したり、ライブに通い詰めたりもする。しかし、「オタク(Otaku)」という言葉に相当する文化的枠組みは存在しない。むしろ、“obsessed”(夢中になっている)という形容がされるが、それはあくまで個人の趣味に過ぎず、社会的に認識された「オタク文化」とまでは言えない。
また、イギリスのファンは比較的「クール」であることが求められる傾向があり、「狂信的なファン」であることを公にするのは、ある種の“恥”とされる側面もある。
4. オタクという概念はイギリスにあるのか?
厳密に言えば、「オタク」という概念はイギリスにも存在するが、それは主にアニメ、ゲーム、SFといった**“ギーク文化”に限られる。たとえば、「Doctor Who」や「Harry Potter」のファン、または日本アニメのファン**などがその対象となる。
その一方で、日本のように「アイドル専門のオタク」「地下アイドルを追いかけるマニア」などの細分化された層は、イギリスにはほとんど存在しない。地下アイドルそのものがほぼ存在しないという文化的背景もある。
5. イギリスにおけるK-POPブーム:アイドル文化の輸入
イギリスにおいて、近年の「アイドル文化」的な現象として無視できないのがK-POPの人気である。BTSやBLACKPINKといった韓国のアイドルグループは、イギリスでもチャートを席巻し、現地の若者たちの間でK-POPオタクが形成されている。
彼らは、韓国語を学び、ライブやサイン会に参加し、SNSで世界中のファンとつながっている。その意味では、韓国のアイドル文化がイギリスに「オタク」という概念を部分的に輸出したともいえる。つまり、「アイドルオタク」という存在は、純粋な国産ではなく、輸入された文化の一部として存在している。
6. 「地下アイドル」は存在するか?
日本のアイドル文化の多様性は、「地下アイドル」や「ローカルアイドル」などのサブカルチャーにも広がっている。イギリスにおいても、音楽フェスや小規模ライブシーンで活動する無名のパフォーマーは多く存在するが、それらは「アイドル」と呼ばれることはなく、むしろインディーミュージシャンというカテゴリに入る。
したがって、日本における“地下アイドル”というジャンルは、イギリスには基本的に存在しない。存在したとしても、それは日本的なアイドル文化を模倣した数少ない例に限られる。
7. イギリスにおける将来的な可能性
グローバル化が進むなか、イギリスでもアニメ、K-POP、日本のアイドル文化などが若者に浸透してきている。現在はまだ少数派だが、将来的には、英国内でも「アイドル」を志向する若者や、それを支える「オタク的」ファンダムが育つ可能性がある。
YouTubeやTikTokといったプラットフォームを通じて、自らを「インフルエンサー」として売り込む若者が増える中で、「ファンとの距離感」や「成長ストーリー」を重要視する“新しい形のアイドル”が登場する可能性もある。つまり、日本型でも韓国型でもない、“イギリス型アイドル文化”が形成されるかもしれないのだ。
結論
イギリスにも「アイドル的な存在」は存在する。しかし、それは日本におけるような文化体系とは異なり、より「アーティスト」や「スター」としての側面が強調される。また、「アイドルオタク」という概念も、現地では社会的に定着しているとは言いがたく、主にK-POPファンダムなど、外来文化の影響を受けた限定的な現象にとどまっている。
しかし、世界の文化がますます融合していくなかで、イギリスにおける「アイドル」や「オタク」のあり方も、静かに変化を遂げている。その変化の行く先を見届けることは、今後のグローバル・カルチャーを理解するうえで非常に興味深い課題となるだろう。









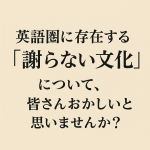
Comments