
ロンドンの街角。カメラを片手に歩き回る若いユーチューバーが、移民風の労働者に声をかける。
「This is my country. Go back to your home.」
挑発的なやり取りはそのまま動画となり、再生数は数十万回を超える。彼らにとって「移民を追い払う瞬間」は、社会問題を語る真剣な場ではなく、再生数を稼ぐためのコンテンツにすぎない。だが視聴者は「よく言った!」と拍手喝采を送り、その言葉はSNS上で拡散されていく。
しかし裏を返せば、そうしたユーチューバー自身がまともに働いていなかったり、納税すらしていなかったりするという現実もある。つまり、社会に責任を果たしていない人間が「国を守る」と声高に叫ぶ――その矛盾こそが、今日の排外主義の滑稽さを象徴している。
日本でも広がる“排外エンタメ”
この現象はイギリスに限られない。日本でも最近、似た構造のユーチューバーが現れつつある。
例えば、繁華街で喫煙所以外に立ちタバコをしている観光客を注意する動画。彼らはカメラを回しながら毅然と注意し、最後にこう言い放つ。
「ここは俺の国だ」
一見すれば、正義感の表れにも見える。だが冷静に考えれば、路上喫煙をしているのは外国人観光客だけではない。日本人だって同じようにマナーを破っている。それなのに、わざわざ外国人を狙って撮影するのはなぜか?
そこにあるのは「マナー遵守」への真剣な姿勢ではなく、「外国人を叱る俺」という演出であり、差別をコンテンツ化して消費している構図に他ならない。
「俺の国」という言葉の虚構
「This is my country」「俺の国だ」――このフレーズは、聞こえは勇ましいが、実際には根拠の薄い主張だ。なぜなら、国は誰か一人が所有するものではないからだ。
私たちは、ただ「たまたま日本に、日本人として生まれた」あるいは「たまたまイギリスに、イギリス人として生まれた」にすぎない。それを所有権のように振りかざすのは、偶然の出生を「特権」と取り違える錯覚でしかない。
さらに言えば、国は歴史や社会の積み重ねによって成り立つ「共同体」であり、そこには無数の他者の貢献が含まれている。移民労働者がいなければ成り立たない産業もあるし、外国人観光客がいなければ潤わない地域経済もある。にもかかわらず、「俺の国」と排除することは、むしろ自分の生活基盤を狭める行為にすらなり得る。
差別の“見えない仕切り”をどう壊すか
イギリスのユーチューバーは「移民」を、日本のユーチューバーは「観光客」をターゲットにする。その構造は共通している。つまり、「自分と違う存在」に線を引き、「ここは俺の場所だ」と主張することで、自らのアイデンティティを保とうとする心理だ。
だが、この“見えない仕切り”こそが差別を生む。マナー違反を注意するのであれば、日本人にも外国人にも同じ態度を取るべきだ。公平さを欠いた時点で、それは「マナー」ではなく「差別」の実践へと変質してしまう。
問題は「誰を排除するか」ではない
結局のところ、私たちが問うべきは「誰を排除するか」ではなく、「どう共に生きるか」だろう。国は誰か一人のものではなく、社会全体の営みの上に成り立っている。
イギリスで移民を追い払うユーチューバー、日本で観光客を叱責するユーチューバー。彼らは視聴者の欲望を刺激する存在かもしれない。だが、その先にあるのは社会の分断と、相互不信の拡大だ。
「This is my country」と叫ぶ前に、私たちは立ち止まり、考える必要がある。
本当に守るべきものは“国”ではなく、“人と人との共生”ではないか。
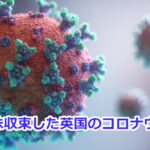


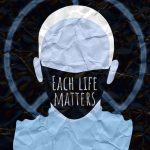





Comments