
2025年に開催される大阪・関西万博。その準備が着々と進む中で、ある意外な話題がSNSを賑わせました。それは、英国パビリオンで提供される「アフタヌーンティー」が、なんと“紙コップ”で出されているという事実。
「英国といえば紅茶の国」「アフタヌーンティーといえば優雅でクラシックなティーセット」というイメージが根強い日本のSNSユーザーたちの間では、「これはちょっと残念」「イギリスの文化に対するリスペクトが足りないのでは?」という声が飛び交いました。
しかし、いざフタを開けてみると、当のイギリス人たちは意外にもまったく気にしていない様子。「紙コップで何が悪いの?」といった反応が目立ち、むしろ日本側の過剰な反応を不思議に思っているようなのです。
なぜこのような文化的なギャップが生まれたのでしょうか。そして、紙コップで提供される紅茶は、果たして“英国らしさ”を失っているのでしょうか?
日本人が抱く「アフタヌーンティー」のイメージとは
まず、なぜ日本人が「紙コップの紅茶」に違和感を覚えるのか、その背景から考えてみましょう。
日本で「アフタヌーンティー」といえば、ホテルのラウンジなどで提供される“贅沢なティータイム”のイメージが強くあります。三段トレイに美しく盛り付けられたサンドイッチやスコーン、ミニケーキ。シルバーのティーポットに繊細な陶磁器のカップ。まるで貴族のような優雅な時間を過ごす体験——それが日本における「アフタヌーンティー」の典型像です。
このようなイメージは、英国文化を尊重した上で日本的に洗練されたスタイルとも言えるでしょうが、同時に「観光向け」「演出重視」の側面が強いのも事実です。つまり、「イギリスらしさ」を再現しようとするあまり、実際のイギリス人の生活からは少し距離のある体験となっていることもあるのです。
英国の現実:マグカップと紙コップの日常
一方で、実際のイギリス人はどう紅茶を飲んでいるのでしょうか。答えは実にシンプル。多くのイギリス人にとって、紅茶は「日常の飲み物」。特別な存在というよりも、日本でいうお茶やコーヒーのように、日々の生活に溶け込んだ存在です。
ロンドン在住の30代の会社員男性はこう語ります。
「職場では紙コップだし、家ではマグカップ。高級なティーセットなんて持ってない。紅茶がちゃんとおいしければ、それでいい」
つまり、紅茶は「どう飲むか」よりも「何を飲むか」の方が圧倒的に重要。ティーバッグをマグカップに放り込んで熱湯を注ぎ、牛乳を入れて飲む——そんなスタイルが一般的なのです。
イギリス人にとって重要なのは「味」
実際、イギリス人の紅茶へのこだわりは「味」に集中しています。たとえば以下のようなブランドは、どこのスーパーでも見かける国民的紅茶です。
- Yorkshire Tea(ヨークシャーティー):濃厚な味と深いコクで、北部を中心に絶大な人気を誇る。
- PG Tips:老舗ブランドで、ピラミッド型ティーバッグが特徴。
- TetleyやTwiningsも定番中の定番。
- 最近ではオーガニックティーやアールグレイ、ハーブティーにも人気が拡大中。
彼らにとって、紅茶とは「濃くてしっかりした味」が命。器がどんなものであろうと、「中身がちゃんとしていればOK」というのが英国的な合理主義です。
「高級アフタヌーンティー」は本当に英国の伝統か?
確かに「アフタヌーンティー」という言葉自体は19世紀のイギリス貴族の間で生まれた文化です。当時、夕食までの空腹を満たすため、上流階級の婦人たちが午後4時頃に紅茶と軽食を楽しんでいたのが始まりとされています。
しかし現代のイギリスでは、こうした格式高いアフタヌーンティーは「特別なイベント」として認識されており、日常的に行う人はほとんどいません。高級ホテルや観光地で体験するアフタヌーンティーは、むしろ「伝統を味わう非日常」であり、「日常の紅茶文化」とは明確に区別されています。
ある英国文化研究者はこう指摘します。
「エリザベス女王の紅茶の儀式と、庶民が仕事中に飲む紅茶はまったく別物。後者の方が圧倒的にリアルなイギリスです」
紙コップに込められた“実用性”と“環境配慮”
大阪万博という巨大国際イベントの場において、紙コップが選ばれたのは合理的な理由があるでしょう。衛生面、安全性、効率、そしてサステナビリティ。これらすべてを満たすには、使い捨て可能でリサイクル素材の紙コップが適しています。
さらに、イギリス社会では近年、環境意識の高まりもあって、プラスチック廃止やリユース推進が活発です。生分解性の素材や再生紙を使ったカップが推奨されるなど、「エコであること」もまた新しい英国らしさの一部となっています。
つまり、紙コップで紅茶を提供するという行為は、今のイギリスの価値観——「実用性」「合理性」「環境配慮」——にぴったり合致しているのです。
誰が「英国らしくない」と言っているのか?
最も本質的な問いはここかもしれません。
大阪万博の英国パビリオンで紙コップが使われることを「英国らしくない」と批判する声の多くは、日本人から上がったものでした。実際のイギリス人たちがそのことに何の違和感も抱いていないのに対し、外側から“理想の英国像”を投影してしまっていたのは私たち自身だったのかもしれません。
文化を尊重することと、文化を固定化してしまうことは、時に紙一重です。過去のイメージに囚われず、変化する文化のリアルな姿に目を向けることも、国際イベントを通じて得られる大切な学びの一つではないでしょうか。
紅茶の本質は、味とともにある
紙コップで出された紅茶が「英国らしくない」と感じるのは、実は日本人が持つ理想像が作り出した幻影かもしれません。
英国の紅茶文化が教えてくれるのは、「大事なのは外見ではなく中身」「形式よりも実質」というシンプルな価値観。そしてその合理性と柔軟さは、日々の生活に追われる私たちにも、小さなヒントを与えてくれるように思えます。
大阪万博で味わう一杯の紅茶。その器が紙コップであっても、それが濃く、香り高く、心をほっとさせるものであれば、そこには確かに“英国の精神”が宿っているのです。






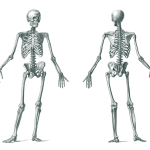



Comments