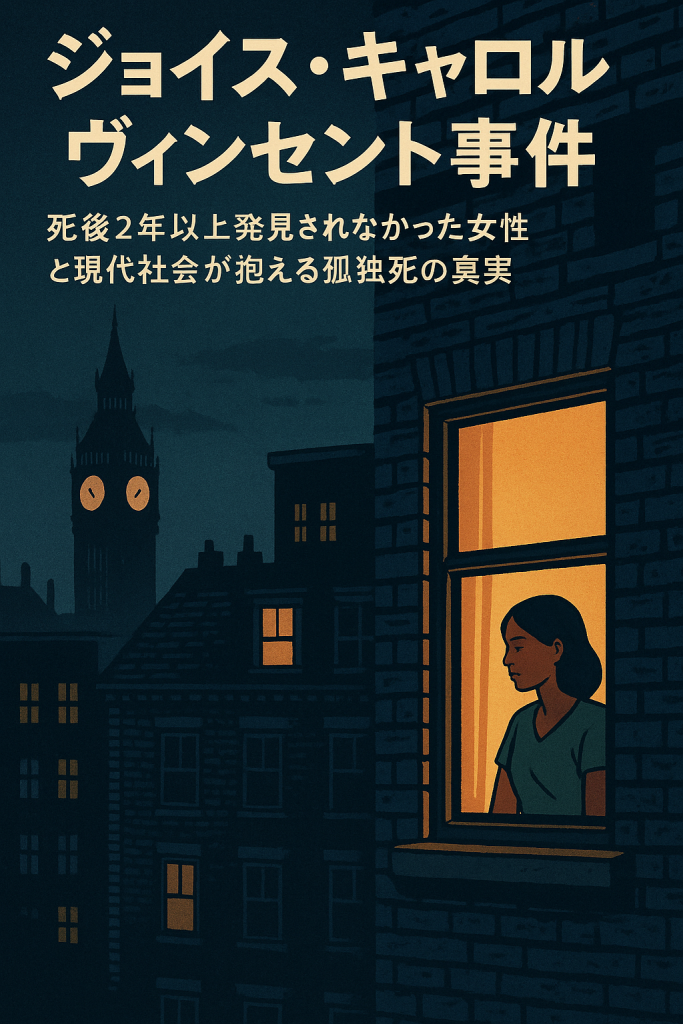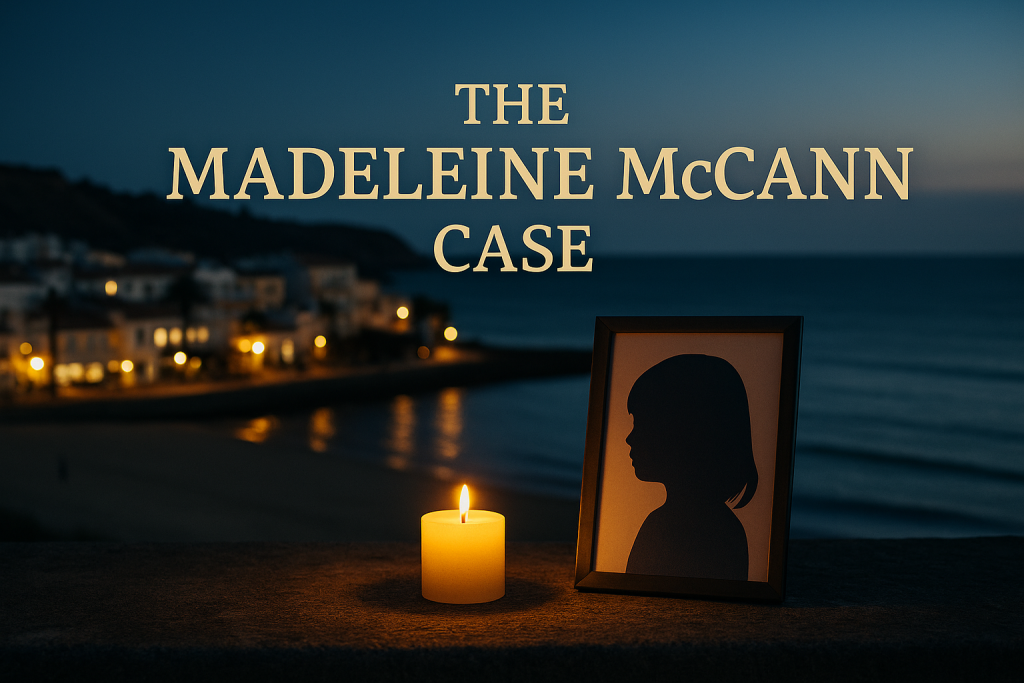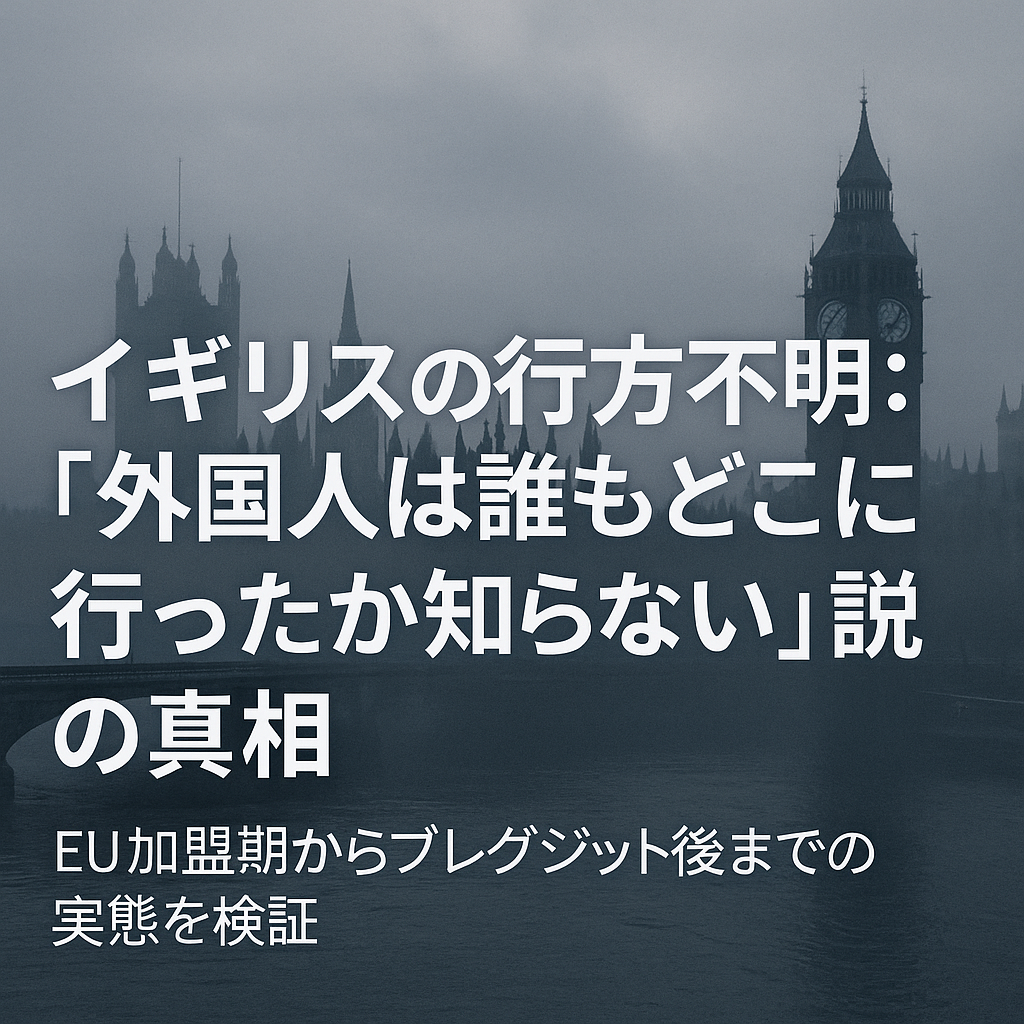…
Author:admin
ジョイス・キャロル・ヴィンセント事件|死後2年以上発見されなかった女性と現代社会が抱える孤独死の真実
…
イギリスで犯罪者が英雄化された事件史|ガイ・フォークスから現代SNSまで徹底解説
…
イスラエル・ガザ停戦後、英国に及ぶ経済的負担と移民受け入れへの影響を中立的に整理
…
英国スターマー政権のガザ停戦対応を時系列で整理|声明・人道支援・輸出停止の実績まとめ
…
スターマー英首相、「停戦スピーチは完璧、実行は行方不明」──イスラエルとガザに響かない平和の言葉
…
イギリスのボーガン殺人事件まとめ|BBCジョン・ハント氏家族3人殺害の全容と犯人カイル・クリフォードの終身刑
…
マデリン・マッキャン事件の全貌|容疑者ブリュックナーの出所と最新裁判の動き【2025年版】
…
イギリスの行方不明:「外国人は誰もどこに行ったか知らない」説の真相を徹底検証
…
スターマー英首相、移民政策を転換へ――インド人ビザ発給は厳格化の方向か?
…