
はじめに:「政治」の話があまりにも日常的すぎる国、イギリス
「最近、イギリスの若者と話したことはありますか?」
もしそう尋ねられて、「はい」と答える人がいたとしたら、きっとその人はこう付け加えるでしょう。
「政治の話ばっかりだったよ」と。
実際、イギリスの若者、特に20代から30代前半の世代は、やたらと政治に詳しく、そしてよく語ります。しかも、堅苦しい場面ではなく、パブやカフェ、あるいはZoom飲み会のようなカジュアルな場でも、「保守党はどうだ」「労働党は信用できるか」「Brexitは結局何だったのか」といった話題が頻繁に飛び交います。
日本に暮らしていると、政治の話は「避けるべき」「面倒なことに巻き込まれる」といった印象がつきまとい、日常会話で話題にするにはハードルが高いものです。ではなぜ、イギリスではここまで政治が身近な話題となり、しかも不満や怒りを伴うことが多いのでしょうか?
本稿では、「イギリス人は常にイギリスという国に不満を持っている」という仮説をもとに、その文化的背景、社会構造、歴史的要因を紐解いていきたいと思います。
1. 「政治」はイギリス人にとって怒りの表現手段
まず押さえておきたいのは、イギリスでは「政治を語ること=不満を語ること」という構図が極めて明確だという点です。日本では「ポリティクス=難しい」「専門的」「騒がしい」といった印象が強いのに対して、イギリスではむしろそれが「自分の怒りを言語化するためのツール」として機能しているのです。
たとえば、ロンドンの大学生に「今の政権についてどう思う?」と聞けば、おそらく10人中9人は眉をひそめ、こう返してくるでしょう。
「まったく信じられない。税金は上がるばかりだし、公共サービスはボロボロだよ」
このような反応が出てくる背景には、「国が自分の生活を直接左右している」というリアルな実感があります。イギリスでは、大学の授業料問題、NHS(国民保健サービス)の崩壊、住宅難、公共交通の遅延やストライキなど、「政治の失敗」が日常の不便や不満に直結しているのです。
つまり、イギリスにおいて政治とは、抽象的な理念や理想を語る場ではなく、「俺たちの生活をメチャクチャにしている元凶」そのものであり、だからこそ若者たちも黙っていられないのです。
2. 「グランジ・ナショナリズム」の国、イギリス
イギリスには、独特の「自虐的愛国心」があります。皮肉屋でブラックジョーク好き、という国民性はよく知られていますが、その根底にあるのは「自分の国のダメさを誰よりもよく知っているのは俺たちだ」というスタンスです。
これを、私は「グランジ・ナショナリズム」と呼んでいます。つまり、「国を愛しているが、同時に全力でディスる」。90年代のブリットポップやグランジカルチャーにも見られるように、イギリス人の多くは、自国に対するロマンチックな幻想を持たず、むしろ「期待しない」という諦めからくる愛着を抱いているようにも見えます。
「イギリスはもう終わってる」
「でもここで生まれ育ったから、仕方なく住んでる」
「出て行きたいけど、他も大して良くないしな」
このような曖昧で皮肉めいた愛国心は、アメリカやフランスのような「誇り高きナショナリズム」とは一線を画します。イギリス人は、自国を誇りに思っていると同時に、その愚かさや不条理さにも敏感で、それを皮肉と不満として語ることで、自分の立ち位置を再確認しているのです。
3. Brexitが生んだ「永遠の分断」
イギリス人の「不満体質」を象徴する出来事として、やはりBrexit(EU離脱)は外せません。2016年の国民投票を機に、イギリス社会は「離脱派」と「残留派」に真っ二つに割れました。この分断は今なお尾を引き、多くの若者にとっては「上の世代がやらかした最大の愚行」として語り継がれています。
ある若者はこう言います。
「僕たちが子供の頃から言われてたのは、グローバルであれ、世界に開かれた視点を持て、ってこと。でも大人たちはそれをぶち壊したんだ」
Brexitは、単なる政策変更以上の意味を持っていました。それは、「国の未来をめぐる価値観の衝突」であり、「誰がこの国を代表するのか」というアイデンティティの争いでもあったのです。
その結果、多くの若者が「この国にはもう期待できない」という感情を抱くようになりました。実際、Brexit以降、EU加盟国に移住を希望する若者が急増しており、「パスポートを捨てたい」という声さえ聞かれます。
4. イギリスにおける「政治的会話」の日常化
こうした背景を踏まえると、イギリスにおける「政治の話が日常的に出てくる」現象も合点がいきます。皮肉屋で批判精神の強いイギリス人にとって、政治は最も手っ取り早く、そして共感を得やすい不満の共有手段なのです。
たとえば、パブで初対面の人と話すとき、「今のインフレ率ひどくない?」とか「電車がまた遅れてさ」といった軽いボヤキから始まり、それが自然と「政府の無策ぶり」や「過去の政権との比較」などに発展していきます。
ここで面白いのは、そうした会話が必ずしも激論や喧嘩につながるわけではなく、「ああ、やっぱりお前もそう思ってたか」という一種の安心感につながる点です。イギリスでは、不満を共有することで関係が深まる、という独特の文化があるのです。
5. それでも出ていかないのはなぜか?
ここまで読むと、「じゃあ、そんなに不満があるなら出て行けばいいじゃないか」と思うかもしれません。
しかし、多くのイギリス人は、文句を言いながらも出ていこうとはしません。これもまた興味深い現象です。
理由のひとつは、「他の国もどうせ似たようなもんだ」という諦観です。日本人にも「どこも景気悪いし」というような言い訳がありますが、イギリス人のそれはさらに達観しており、「国なんて完璧なわけがない。むしろ不完全なほうが面白いじゃないか」とさえ言う人もいます。
もうひとつの理由は、やはり文化への深い帰属意識でしょう。皮肉や自虐、ブラックジョークを共有できる社会は、世界でもそう多くありません。つまり、イギリス人にとって「文句を言いながらもここにいる」というのは、彼らなりの「帰属の形」なのです。
結論:「不満を言う」ことこそ、イギリス人の愛国心
結局のところ、イギリス人が政治についてよく語るのは、「この国をよくしたい」という理想よりも、「この国に失望している」という感情のほうが強いからです。そして、その失望を言語化し、共有することで、「自分たちが何者か」を確かめ合っているのです。
「イギリスにはイギリスに不満を持っている人しかいない」
そう言うと極端に聞こえるかもしれませんが、現実にはそれがこの国のリアルです。そして皮肉なことに、その不満こそが、イギリスという国をかろうじて繋ぎ止めている最後の糸でもあるのです。
文句を言う。皮肉る。笑い飛ばす。
それが、イギリス人なりの「生き方」なのです。







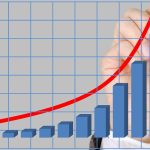


Comments