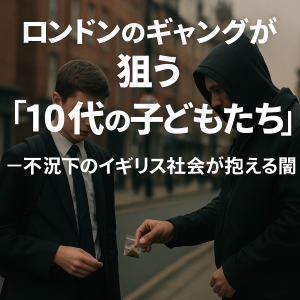
ロンドンの街角で、制服姿の子どもたちが小声で囁き合い、放課後に人目を避けて袋を手渡す。中身は菓子やゲームではない。違法薬物、大麻だ。
「子どもが薬物を売る」――これは犯罪映画の世界だけの話ではなく、現在のイギリス社会が直面している現実である。
経済が長期的に停滞し、生活費が高騰するなか、かつてのように大人のギャングたちが容易に稼げる時代は終わった。そこで彼らが目をつけたのが、最も安く、最も従順で、そして社会的制裁から比較的守られている存在――10代の子どもたちだ。
以下では、なぜイギリスで子どもたちがギャングに取り込まれるのか、その背後にある経済・社会構造、そして学校や地域社会の対応について掘り下げていきたい。
「カウンティ・ラインズ」現象と子どもの巻き込み
イギリスでよく使われる言葉に 「County Lines(カウンティ・ラインズ)」 がある。これは都市のギャングが地方へと薬物の流通網を拡大する仕組みを指す用語で、しばしば未成年がその運び屋や売人として利用される。
若者が狙われる理由は明快だ。
- 刑罰の軽さ:未成年は逮捕されても比較的軽い処分で済む。
- 警察の目を逃れやすい:制服姿の学生が電車に乗っていても、不自然に思われにくい。
- 経済的弱さ:家庭が貧困に苦しんでいれば、現金収入の誘惑は大きい。
ギャングは時に「兄貴分」として近づき、子どもたちにブランド品や少額の現金を与えて信頼を築く。次第に「ちょっとした手伝い」として薬物の運搬や販売を依頼し、その報酬でさらに子どもを縛りつける。拒めば暴力や脅迫が待っている。
景気悪化が生む「格差」と犯罪の温床
ブレグジット(EU離脱)、パンデミック、そしてエネルギー価格の高騰――イギリス経済はこの10年で幾重もの打撃を受けた。物価上昇率はかつてない水準に達し、食料品や家賃、光熱費に苦しむ家庭が増加している。
貧困は犯罪と直結する。特に都市部の貧困地域では、親が複数の仕事を掛け持ちしても生活は安定せず、家庭内での子どものケアが不十分になりがちだ。孤立した子どもは、学校外でギャングの「コミュニティ」に取り込まれやすい。
さらに、伝統的な製造業やサービス業の雇用機会が減少した結果、「将来への希望」が持てない若者が増えた。自分の親世代が失業や低賃金に苦しむ姿を見ている子どもにとって、「短期的にでも大金が手に入る」薬物取引は、歪んだ形でのキャリアパスに映ってしまう。
日本との比較:「大麻観」の違い
日本でも近年、芸能人や留学生による大麻使用のニュースが注目を集めた。多くの場合、「海外で勧められて断れなかった」という言い訳がついて回る。アメリカやカナダのように合法化が進む国では、大麻が「タバコに近い嗜好品」として扱われるため、社会的なハードルが低い。
イギリスは完全合法化こそしていないが、日本と比べれば格段に寛容である。中高生が大麻を所持・使用していても、多くは 停学処分 で済み、刑事事件として重く扱われることは少ない。
この「寛容さ」は一見、リベラルで人権を尊重しているように見える。しかし裏を返せば、学校も警察も「厳格に取り締まれば生徒がいなくなる」という現実に直面しているのだ。もし全員を逮捕していたら、ある地域のセカンダリースクールは半分以上が空席になってしまう――そんな冗談のような状況も、決して誇張ではない。
教育現場のジレンマ
イギリスのセカンダリースクール(日本の中高に相当)では、薬物問題は「珍しい事件」ではなく「日常的な懸念事項」である。
教師たちは次のようなジレンマを抱える:
- 薬物使用を発覚させれば学校の評判が下がり、地域からの信頼を失う。
- 厳罰で生徒を排除すれば、問題を抱えた子どもをさらに社会から孤立させることになる。
- しかし放置すれば、薬物文化が生徒間で「当たり前」になってしまう。
実際、多くの学校では 「発覚したら一時的な停学、カウンセリング受講、再登校」 という形を取っている。これは「更生のチャンスを与える」という理想に基づいているが、裏を返せば「根本的な解決策がない」ことの証左でもある。
家庭・地域社会の対応
親たちにとっても、子どもが薬物に関わるか否かは深刻な不安要素だ。だが現実には、子どもが秘密裏にギャングと接触するケースが多く、家庭内で気づけることは少ない。スマートフォンを通じた連絡手段や、学校の帰り道での短時間の受け渡しなど、親の監視が及ばないところで取引が行われるからだ。
一部の地域では、教会や非営利団体が 「セーフ・スペース」 を提供し、放課後の子どもたちに学習支援やスポーツ活動を行っている。だが資金不足と人員不足で、すべての子どもをカバーできるわけではない。
政治と社会が問われているもの
イギリス政府は薬物犯罪に対して繰り返し「強硬な姿勢」を打ち出してきたが、実態は警察の人員不足、刑務所の過密化、そして社会的コストの高さから、徹底した取締りは不可能に近い。
むしろ近年では、大麻の部分的な合法化や規制緩和を議論する声すらある。理由は「市場を地下から表に引き上げ、税収につなげるべきだ」という経済的なものだ。しかし、それが本当に子どもたちをギャングから解放する道になるのかは疑問が残る。
未来への問いかけ
ロンドンの街角で、制服のポケットに大麻を忍ばせる15歳の少年。
彼は犯罪者なのか、それとも社会から見捨てられた被害者なのか。
イギリス社会は今、この問いに答えを出さなければならない時期に来ている。ギャングの「魔の手」から子どもたちを守ることは、単なる治安維持の問題ではない。教育、福祉、雇用、そして社会的な希望の再建といった広範な課題に直結している。
もしもこの問題に正面から向き合わず、「子どもが薬物を売るのは仕方のないことだ」と諦めれば、次世代のイギリスは犯罪と絶望に支配されるだろう。
結びに
不況下のイギリスで、ギャングたちが子どもを利用する現実は、遠い世界の話ではない。日本でも経済格差が拡大し、若者の孤立が問題視されるなか、同じ構図が生まれる可能性はゼロではない。
「薬物を売る子ども」を非難するだけでは何も変わらない。彼らをそうした道へ追いやっている社会構造そのものに目を向け、教育や地域の支援、そして未来への希望を再構築する必要がある。
ロンドンの街で今日も起きている現実は、私たちにそのことを強烈に突きつけている。






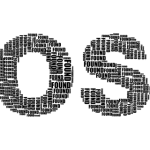



Comments