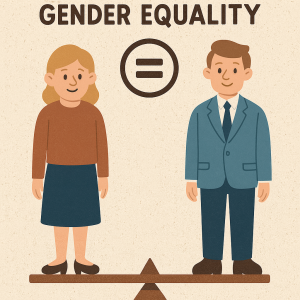
ユニセックス空間から見える、理念と現実の乖離
平等をめぐる議論の現在地
イギリスにおいて「男女平等」という言葉は、日常会話の中で驚くほど自然に使われるようになった。法律上の権利は整備され、教育や職業選択の自由も保障されている。パブリックな場では「性別による差別はあってはならない」という理念が前提となっているため、多くの人々は「私たちはすでに平等を手にしている」と感じやすい。しかし、その一方で「本当にそうだろうか?」と問い直す声も根強い。
とりわけ注目されるのは、ユニセックス空間の広がりである。トイレ、美容室、更衣室。かつて明確に線引きされていた男女の境界が、公共空間から少しずつ消えつつある。こうした変化は「平等が前進している証拠」と語られることが多いが、果たしてそれだけで十分なのだろうか。
ユニセックス空間の象徴性
まず、ユニセックス・トイレの導入は議論の的になってきた。教育機関や新設の公共施設では、性別に関わらず誰もが利用できるトイレを設ける動きが進んでいる。利用する側からすれば「不便が減る」「トランスジェンダーの人々を含めて安心できる」という肯定的な意見がある。一方で「女性が安心できない」「性的ハラスメントの温床になるのでは」といった懸念も無視できない。
同様に、美容室やジムの更衣室におけるユニセックス化も、平等の名の下で進められている。男女の垣根をなくし、あらゆる人に開かれた空間を作ろうとする意図は理解できる。しかし、実際の利用者の感覚としては「本当に落ち着けるのか」という疑問が残る。つまり、ユニセックス空間は「理念としての平等」と「身体的な安心感」の板挟みを象徴する存在になっているのだ。
表面的な変化:服装や職業選択の自由
90年代と比べれば、女性がスカートを履かなくても不自然に見られることはなくなり、男性が看護師や保育士を選んでも偏見は少なくなった。サッカーやラグビーといった「男性の競技」に女性が参加することも広く認められ、メディアも積極的に取り上げるようになった。
このような変化は確かに喜ばしい。かつてのように「女性はこうあるべき」「男性はこうでなければならない」といった社会的圧力は大幅に弱まった。形式的に見れば、イギリスは「誰もが自由に選択できる社会」へと近づいたように思える。
根強い格差:収入と昇進機会
しかし、その内実をよく見てみると、1990年代から劇的に変化したとは言いがたい。たとえば収入格差。統計的には男女間の賃金格差は縮小しているとはいえ、依然として男性が優位に立つ傾向がある。特に管理職や専門職においては顕著であり、同じ仕事をしていても昇進のスピードに差が出るケースは少なくない。
さらに、女性が出産や育児によってキャリアを中断せざるを得ない現実は依然として存在する。制度上は育児休暇や柔軟な働き方が整っているにもかかわらず、実際には「長く職場を離れるのはマイナス評価につながる」という暗黙の了解が残っている。こうした意識の壁は法律や制度だけでは解消されない。
歴史的視点:1990年代との比較
90年代を振り返ると、当時もすでに「平等は重要だ」という認識は社会にあった。しかし、女性がパンツスーツを着て職場に立つと注目を浴びたり、男性が育児に積極的に関わると「珍しい」と言われたりした。30年が経った今、表面的な違和感はかなり減った。
だが、収入や昇進の差、家庭内の無償労働の偏りなど、「見えにくい格差」は驚くほど残っている。つまり「人々の頭の中」は大きく変わっていないのではないか。イギリス社会の表層は洗練されたが、その奥底にある価値観は90年代からそう大きく進化していないように思える。
矛盾するイギリス社会
イギリスはしばしば「リベラルで先進的な国」として語られる。しかし現実には、公共空間では平等を重視しながらも、私的な領域では伝統的な性別役割が根強く残っている。この矛盾こそが、人々に違和感を与えている。
たとえば、企業のポスターには「ダイバーシティ推進」が掲げられているが、実際の役員会には依然として白人男性が多数を占める。大学ではジェンダー研究が盛んに行われる一方で、家庭の中では「母親が家事を担う」構造が温存されている。こうした乖離が、人々に「平等は本当に進んでいるのか?」という問いを投げかけるのである。
本当の平等に向けて
では、どうすればこの矛盾を克服できるのか。鍵となるのは「制度」だけではなく「意識」の変革だろう。法律を整備することは必要だが、それ以上に「人が無意識に抱く前提」を問い直さなければならない。
ユニセックス空間が象徴するのは、まさにその課題である。形式的には平等を実現していても、安心感や心理的安全性が欠けていれば意味がない。逆に言えば、物理的な垣根を取り払った後に「人々がどのように感じ、行動するか」が本当の試金石になる。
結論:垣根の消滅が意味する未来
イギリスで語られる男女平等は、確かに大きな前進を遂げた。しかし、それはまだ表面的な部分にとどまっている。スカートを履くか履かないか、男性がどのスポーツをするかといった自由は広がったが、収入や昇進の格差、家庭内労働の不均衡、無意識の偏見は残り続けている。
「男女の垣根が消えた世界」は理想的に見えるが、それは単なる制度や空間の話ではなく、人の心の奥底にある価値観の変容を伴わなければならない。もしそれが伴わなければ、ユニセックス・トイレのように「見た目は平等でも、実際には不安や不満を増幅させるだけ」という逆効果に陥る危険すらある。
結局のところ、1990年代から現在に至るまで、私たちは「平等を実現するために必要な最後の一歩」をまだ踏み出せていないのではないか。制度と表層を整えることから、無意識の価値観を変えることへ。その転換こそが、イギリスがこれから真に直面すべき課題なのである。










Comments