
はじめに
2025年現在、イギリスのインフレ率は依然として主要先進国の中で高い水準にあります。ユーロ圏やアメリカの2〜3%台に比べ、英国は3.8%と突出しており、食料品やエネルギー、サービス価格の高騰が家計を直撃しています。
なぜイギリスだけが「高インフレ」から抜け出せないのか。その答えの一端は、経済的に合理的であったはずの「他国との共存」という選択を自ら放棄したことにあるのではないでしょうか。
インフレを押し上げる英国特有の要因
1. エネルギー依存とポンド安
イギリスは天然ガス輸入への依存度が高く、地政学リスクや国際価格変動の影響を直撃します。さらにBrexit以降、通貨ポンドは不安定さを増し、輸入コストが膨らみやすい構造になっています。
2. 食料品価格の高騰
EU離脱後、関税・通関コストが増加し、輸入農産物の価格は上昇。加えて物流効率の低下が食料インフレを強めました。これはユーロ圏諸国が共有市場の恩恵で抑制できた部分と対照的です。
3. 労働市場の逼迫
BrexitによりEUからの移民労働者が減少。農業、建設、介護、医療といった分野では深刻な人手不足が発生し、賃金上昇圧力となって価格を押し上げています。
とりわけNHS(国民保健サービス)は外国人医師・看護師なしでは機能しないほど外国人労働に依存しており、現場では「人手不足が医療コストを膨張させる」という悪循環が生まれています。
「外国人が仕事を奪う」という幻想
世論の中では「移民がイギリス人の仕事を奪っている」というイメージが根強いですが、学術研究はこれを裏付けていません。
- 移民の流入は、イギリス人全体の失業率や就業率に統計的に大きな悪影響を与えていない。
- 影響があるとしても、ごく一部の低技能・特定地域に限られる。
- むしろ、移民は人手不足を補い、サービス供給を維持する役割を果たしてきた。
それにもかかわらず「移民が奪っている」という物語が広まるのは、政治・メディアによるスケープゴート化、ゼロサム思考、外集団バイアスといった心理的要因が大きいと考えられます。
現実:外国人を雇うのはイギリス人経営者
さらに重要なのは、イギリス国内企業の大半(9割以上)はイギリス人が所有・経営しているという事実です。
つまり「誰が外国人を雇っているのか?」と問えば、それはイギリス人経営者自身なのです。
経営者が外国人を選好するのは、
- 人手不足の補填、
- 労働意欲や柔軟さへの高評価、
- 人件費コストの抑制、
といった理由によります。
つまり外国人労働者は「仕事を奪った」のではなく、「イギリス経済を回すためにイギリス人経営者が必要として雇った」のです。
共存を拒んだ結果としての高インフレ
こうした現実を踏まえると、イギリスの高インフレは単なる経済ショックではなく、「共存を拒んだ結果」だと見ることができます。
- EUから離脱し、統合市場という最大の安定装置を放棄した。
- 外国人労働力を縮小させ、供給制約とコスト上昇を自ら招いた。
- 自国優先・移民排斥を選んだことで、輸入コストと労働コストが跳ね上がり、価格高騰を長期化させている。
「外国人が仕事を奪っている」と信じることで安心を得ても、実際には外国人がいなければ医療も農業も物流も立ち行かない。そして経済全体が縮小する中で、もっと大きな形でイギリス国民が自らの生活コストという形で「奪われて」いるのです。
結論
イギリスのインフレ率が高いのは、国際協調と共存という経済成長の王道を拒み、自国中心主義を優先した結果だといえます。
もし真に生活コストを抑え、豊かさを取り戻したいのであれば、イギリスは再び「他国とともに生きる」という選択肢に目を向ける必要があります。
インフレの高さは、孤立主義の経済的代償の表れにほかなりません。
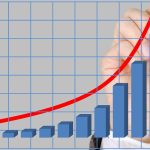









Comments