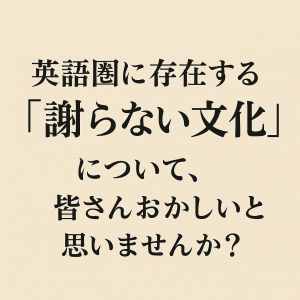
「謝罪」という行為は、人間社会において極めて重要な潤滑油であるはずです。誰かがミスをしたとき、誰かを不快にさせてしまったとき、あるいは結果的に相手に迷惑をかけてしまったとき。そんな場面でまず口をついて出るのが「ごめんなさい」や「申し訳ありません」ではないでしょうか。ところが英語圏に暮らしてみると、どうもこの当たり前の反応が存在しない、もしくは極端に軽い形でしか存在していないことに気づかされます。
皆さんはどう思いますか?これって文化の違いで済む話でしょうか。それとも、サービスや人間関係の根本に関わる大きな問題なのでしょうか。
1. 「Sorry」で終わる軽すぎる謝罪
イギリス人を観察していると、たしかに日常生活の中で「Sorry」という言葉を耳にすることはあります。たとえば、道で人とぶつかったとき、バスの中で通路を塞いでしまったとき。そういう場面で、反射的に「Sorry」と口にする光景は見かけます。
しかし、ここで重要なのはその「Sorry」が、日本人の「すみません」や「ごめんなさい」と同じ感覚ではない、という点です。あくまで形式的で、まるで「Excuse me」と同じくらいの軽さで発せられている。そこには反省の色も、責任を引き受ける姿勢もほとんど見られません。
もっと不思議なのは、本当に深刻なミスやトラブルが起きた場面では、この「Sorry」すら聞こえてこないことです。その代わりに登場するのが、「言い訳」です。
2. 理屈になっていない言い訳の乱発
イギリスで生活していて驚かされるのは、問題が起きたときの「言い訳文化」です。
例えば商品が届かない、手続きにミスがあった、あるいは誰かが明らかに約束を破った。そんな場面でまず聞かされるのは「申し訳ありません」ではなく、「いや、それは〇〇だから仕方なかったんだ」という説明です。
しかも、その説明を冷静に聞いてみると、ほとんど理にかなっていない。筋道が通っていないのに、とにかく「自分は悪くない」という主張を前面に出してくる。おそらく本人は「理由を提示した」ことで満足しているのでしょう。まるで「言い訳をすれば、もう責任を果たした」とでも思っているかのように。
その姿勢を見ていると、謝罪を重んじる文化で育った日本人からすると大きな違和感を覚えます。なぜ一言「自分の落ち度だった」と認められないのか。その方がずっと簡単で、相手との関係もスムーズに修復できるはずなのに。
3. カスタマーサービスで体験した「謝らない文化」
この「謝らない文化」は、日常会話の場面だけでなく、ビジネスの現場、特にカスタマーサービスにおいても顕著に現れます。最近私が体験したのは、オンラインショッピングでの出来事です。
私はある商品をインターネットで注文しました。しかし、待てど暮らせど商品が届かない。不審に思って問い合わせてみると、配送業者から「配達完了の証拠写真」が送られてきました。ところが、その写真に写っている住所は、私の住所とはまったく別物。明らかに誤配達です。
この時点でまず期待したのは「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」というひと言でした。しかし、カスタマーサービスに電話して最初に言われたのは驚くべきことに――「その住所に取りに行きましたか?」だったのです。
いやいや、どうして私が見知らぬ家に行って商品を回収しなければならないのでしょうか?しかもこちらが被害を受けている立場なのに、最初に投げかけられる言葉が謝罪ではなく、責任転嫁のような質問。唖然とせざるを得ませんでした。
もちろん、配送の手違いそのものはカスタマーサービスの担当者の直接のミスではないかもしれません。しかし、顧客対応において最初にやるべきことは何か。それは事実確認の前に、まず「謝罪」ではないでしょうか。「お困りの状況を理解しました、申し訳ございません。その上で次のステップを一緒に考えましょう」と言われれば、どれだけ安心できたことでしょう。
4. 謝罪の力と消費者心理
実際、あるアンケート調査(これは日本で行われたものではありません)では、クレーム対応において顧客が最も許せる対応は「誠意ある謝罪」だという結果が出ています。人間は誰しも完璧ではありません。ミスは起こる。重要なのはその後の対応です。
謝罪を受けたとき、人は「この人(この会社)は自分の不快や損害を理解し、責任を取ろうとしている」と感じます。その感覚が信頼をつなぎとめ、再びサービスを利用しようという気持ちにつながるのです。
逆に、言い訳ばかりを並べ立てられるとどうでしょうか。こちらが受けた被害はそのまま放置され、しかも「自分が悪いのでは?」と疑わせるような態度を取られる。そんな経験をした顧客が、再びその会社を利用したいと思うでしょうか。答えは明らかです。火に油を注ぐようなものです。
5. 日本の「カスハラ」論との対比
日本では近年「カスタマーハラスメント(カスハラ)」という言葉が広まっています。確かに、理不尽な要求や暴言を吐く客が存在するのも事実です。しかしその議論の中で見落とされがちなのは、「顧客はそもそも被害を受けた側である」という点です。
サービス提供側のミスで迷惑を被ったのなら、最初に誠実な謝罪を受けるのは当然の権利です。暴言や過剰な要求は別として、謝罪すらない開き直った態度を取られれば、反論したくなるのは自然な心理でしょう。日本の一部で見られる「顧客が強すぎる」という議論も、実は「謝らない文化」と比較するとまだ健全に思えてしまうほどです。
6. 英国オンラインショッピングが伸び悩む理由?
このような文化的背景を考えると、イギリスのオンラインショッピング市場が日本やアジアの一部に比べてなかなか発展しない理由のひとつが見えてくる気がします。価格や品揃えの問題だけでなく、「カスタマーサービスに信頼が置けない」という根本的な心理的障壁があるのです。
せっかく便利な仕組みを整えても、最終的にトラブルが起きたときに誠実な対応がなければ、顧客は離れていきます。謝罪ひとつで繋ぎ止められる関係が、謝罪の欠如によって完全に断ち切られてしまう。これはビジネスの観点からも大きな損失です。
7. それでもオンラインショッピングをやめられない理由
とはいえ、私自身はオンラインショッピングをやめるつもりはありません。なぜなら、週末にショッピングモールへ足を運び、人ごみに揉まれるのは正直しんどいからです。家でゆっくり商品を探し、クリックひとつで届けてもらえる便利さは、一度味わうと手放せません。
だからこそ、サービス提供側にはぜひ「謝罪の文化」を身につけてもらいたい。完璧である必要はないのです。人間なのだからミスは必ず起こります。そのときに「ごめんなさい」のひと言を添えるだけで、顧客は「もう一度使ってみよう」と思えるのです。
8. 結び ― 謝罪の不在が生む違和感
結局のところ、英語圏に存在する「謝らない文化」は、単なる習慣や言語表現の違い以上の問題を孕んでいるように思います。謝罪を避け、言い訳で済ませることが常態化すれば、顧客との信頼関係は築けません。人間関係でも同じことです。
「謝ることは負けを認めること」ではありません。「謝ることは相手を尊重すること」です。そこを誤解している限り、どれだけサービスを整えても本当の意味での成長は難しいのではないでしょうか。
皆さんはどう思いますか?この「謝らない文化」、やはりおかしいと思いませんか。










Comments