
「外国人が税金を食い物にしている」——それは本当だろうか?
長年にわたって、イギリス国内では移民に対する否定的な感情が根強く存在してきました。その根底にあるのが、「自分たちが汗水流して払った税金が、何の貢献もしていない外国人に搾取されている」という不満です。特に、ユニバーサルクレジット(Universal Credit)をはじめとした生活支援制度の悪用に対する怒りは、メディアでも頻繁に取り上げられてきました。
しかし、最近公表されたデータがその固定観念に大きな揺さぶりをかけています。
実にユニバーサルクレジットの受給者のうち、83%がイギリス国籍を持つ人間だった。
つまり、生活支援を最も多く受けていたのは「昨日今日やってきた外国人」ではなく、「我々イギリス人」だったという事実が白日のもとに晒されたのです。
ユニバーサルクレジットとは何か?
まず、ユニバーサルクレジットの制度について簡単におさらいしておきましょう。これは、イギリス政府が導入した福祉制度で、従来の複数の手当(Jobseeker’s Allowance、Housing Benefit、Child Tax Creditなど)を一つに統合したものです。
目的は明確で、生活に困窮している人々を支援し、再び自立した生活を送れるようにすることです。その支給対象は、失業中の人や低収入の労働者、育児中の親、障害を持つ人などさまざまです。
支給内容は以下のような支出をカバーします:
- 家賃や住宅関連費用
- 食費
- 光熱費
- 子育て支援
- 就労支援・職業訓練費
この制度が正しく機能すれば、困っている人を助けることができます。しかし、誰がその恩恵を受けているのかという点に関しては、これまでの「認識」と「現実」に大きな乖離があったようです。
データが暴いた「現実」
イギリス政府の公式統計によると、ユニバーサルクレジットの受給者のうち、実に83%がイギリス国籍を持つ人々であることが明らかになりました。このデータは、SNS上で瞬く間に拡散され、多くの議論を巻き起こしています。
これまで多くの国民が、
「移民がイギリスに来て、生活保護目当てに制度を悪用している」
「外国人に税金を奪われて、イギリス人が苦しい生活を強いられている」
といった考えを持っていました。しかし実際には、最も多く支援金を受けていたのは「我々自身」であり、制度の受給者の大多数は純然たるイギリス人だったのです。
この事実は、「移民=搾取者」というレッテルを見直すきっかけとなるべきです。
誤ったスケープゴート:なぜ移民ばかりが責められたのか?
では、なぜこれまで移民ばかりが責められてきたのでしょうか?
理由はさまざま考えられます。
1. メディアの影響
一部の大衆紙は、移民に対するセンセーショナルな報道を繰り返してきました。「家族全員で住宅手当を受け、豪邸に住む難民」「英語も話せないのに子ども手当を受け取っている外国人母親」——こうした見出しは、真偽にかかわらず読者の感情を煽り、誤解を助長してきました。
2. 政治的な誘導
特定の政党は、選挙キャンペーンにおいて「移民による福祉制度の悪用」を争点に掲げ、有権者の不満を取り込もうとしました。これにより、「移民=社会的コスト」というイメージがさらに強固になっていったのです。
3. 経済的不安と感情の投影
不況や物価上昇、賃金の停滞といった経済的な困難に直面したとき、人は「なぜ自分が苦しいのか」という問いに答えを求めます。そのとき、目に見える「他者」に責任を転嫁してしまう心理的メカニズムが働くのです。
では、イギリス人は「怠け者」なのか?
ここで一つ注意が必要です。今回のデータをもって、「イギリス人こそ税金を食い物にしている」などと短絡的に断じるのは、また別の誤解を生むことになります。
大多数のユニバーサルクレジット受給者は、真剣に生きようと努力している人たちです。働きたくても職がない、子育てや介護でフルタイム就労ができない、健康上の理由で就業が困難——そういった「選択肢の少ない」人々なのです。
ユニバーサルクレジットは、そうした人々に再起のチャンスを与えるための制度です。そして現実として、最も多くの困難を抱えているのは、移民ではなく地元のイギリス人であるということが、今回の統計で浮き彫りになっただけなのです。
求められるのは「分断」ではなく「理解」
今回のデータは、私たちにとって不都合な真実かもしれません。しかし、真実に向き合うことこそが社会を良くする第一歩です。
「誰が得をしているのか」ではなく、**「なぜそこまで多くの人が支援を必要としているのか」**を問うべきです。
- なぜイギリス国籍者の多くが生活困窮に陥っているのか?
- 働いても生活できない社会構造に問題はないのか?
- 地域や教育、雇用政策に何が足りないのか?
移民の排斥ではなく、根本的な社会構造の改善をこそ求めるべきです。
「我々の税金」は誰のためのものか?
もう一度考えてみましょう。「自分たちの税金が使われている」と言うとき、その「自分たち」の範囲はどこまでですか?
- 同じ街に住んでいる人?
- 同じ国籍の人?
- 働いている人だけ?
- 働けない人は除外されるべき?
私たちは皆、社会の一部としてつながっています。そして、税金とは社会の中で「今、困っている人」に手を差し伸べるための共通の財源です。
もし明日、あなたが職を失い、病気になり、支援が必要になったとき、あなたは「外国人扱い」されたいですか?
それとも、「社会の一員」として助けてもらいたいですか?
最後に:敵は「移民」ではない。問題は「構造」だ
ユニバーサルクレジットを受け取っている人々の大多数がイギリス人であるという現実は、私たちに多くの問いを投げかけています。
- 貧困と格差の構造をどう変えていくのか
- 働くことの意味と報酬をどう再定義するのか
- 他者を責める前に、自らの社会の姿をどう見直すのか
そして何より、「敵を見誤ってはならない」ということです。
問題は「移民」ではなく、支援を必要とする人が増え続ける「社会の仕組み」そのものなのです。
私たちはもう、「移民のせい」とは言えません。
今こそ、本当の課題に向き合うときです。
誰もが人間らしく生きられる社会を目指して、対話と連帯を始めるべき時ではないでしょうか。



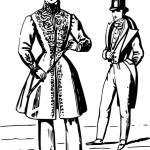






Comments