
近年、イギリスをはじめとする先進国で、子どもの自殺が深刻な社会問題となっている。10代の若者たちが未来ある命を絶ってしまうという現実は、社会全体を大きく揺るがしており、その背景には複雑な要因が絡んでいる。学校でのいじめ、学業や将来への不安、家族関係の不和など、従来から存在していた問題に加えて、SNSの影響が急速に拡大していることが大きな要因とされている。
SNSの台頭は、私たちの生活を劇的に変えた。情報の共有が瞬時に可能になり、遠く離れた人とつながることができるこのツールは、大人にとっても多大な恩恵をもたらしている。だが、その利便性の裏には、目に見えにくい危険が潜んでいる。そしてその危険に最も晒されているのが、心身ともに発達段階にある子どもたちである。
スマートフォンやタブレットは、今や家庭内において日常的な存在となった。子どもが静かにしてくれるからと、親が安易にこれらのデバイスを渡す場面は珍しくない。しかし、問題はここにある。親が子どもに与えるものは単なるガジェットではなく、時には命に関わる重大なリスクを孕んでいるのである。
かつて私たちが子どもだった頃、娯楽といえばファミコンやカードゲーム、公園での遊びが主流だった。それらは一方向的な体験であり、過剰な刺激や社会的なプレッシャーとは無縁だった。しかし、現代の子どもたちは、インターネットという無限の情報空間と、SNSという“もうひとつの社会”に日常的に触れている。そこには、匿名の誹謗中傷、過激なコンテンツ、虚構の成功例、過度な他者比較といった、子どもの心に悪影響を及ぼしかねない要素が数多く存在している。
SNSの本質は「双方向性」にある。つまり、情報を受け取るだけでなく、自らも発信し、反応を得る構造だ。この点において、SNSは単なるメディアではなく、“社会そのもの”なのである。そして、その社会は、必ずしも優しさや配慮に満ちているわけではない。子どもがSNS上で感じる孤独や劣等感、恐怖は、現実世界でのいじめや差別と同じくらい、いやそれ以上に深刻な精神的ダメージを与えることがある。
多くの親たちは、「SNSが悪い」「プラットフォームを規制すべきだ」と主張する。しかし、そうした意見だけでは本質に迫ることはできない。SNSはすでに世界的に確立した産業であり、その経済的インパクトは計り知れない。数多くの企業がSNSを基盤にビジネスを展開し、何百万人という雇用を支えている。それを「全面的に禁止すべき」とするのは、現実的ではないし、そもそも無理な話だ。
だからこそ、私たちは視点を変えなければならない。子どもを守る第一義的な責任は、家庭、すなわち親にある。SNSという“社会”に子どもを送り出すのであれば、その世界のルールや危険性を理解し、子どもと共に学び、対話を重ねながら使わせることが求められる。自転車に乗る前に交通ルールを教えるように、SNSを使わせる前に、そこに潜むリスクと付き合い方をきちんと教えるべきなのだ。
特に幼い子どもに対して、親が責任を持ってデバイスの使用を管理する必要がある。アプリの使用制限、フィルタリングの導入、使用時間の管理、そして何よりも「何を見ているのか」「誰とつながっているのか」という会話を日常的に行うことが不可欠だ。技術的な制限も重要だが、それ以上に「信頼に基づいた親子の関係性」こそが、子どもを守る最大の防御壁となる。
もちろん、親だって完璧ではない。仕事に追われ、育児に疲れ、心の余裕を失ってしまうこともある。それでもなお、親という立場は、子どもの命と心に対して最終的な責任を負っている。SNSによって命を絶つ子どもが存在する以上、「静かにしてくれるから」「自分の時間ができるから」といった理由で、無防備にデバイスを与えることの代償はあまりに大きい。
私たちは今、かつてないほどに親の在り方が問われる時代を生きている。子どもたちは、SNSという巨大な情報空間の中で迷い、苦しみながらも、誰かに助けを求めている。学校でもなく、SNSの運営企業でもなく、まず最初に寄り添うべき存在は、他ならぬ“親”なのである。
そのためには、親自身もSNSリテラシーを高める必要がある。「よく分からない世界だから」と距離を置くのではなく、「分からないからこそ学ぶ」という姿勢が求められる。子どもが見ている世界を理解し、共に悩み、共に考えること。それが、SNS社会における新しい育児の形であり、親としての最低限の責務である。
結局のところ、SNSそのものが悪いわけではない。それをどう使い、どう向き合うかが問題なのだ。親として、子どもにデバイスを与える前に、必ず自問してほしい。
「この世界を、この年齢で、本当に渡してもいいのか?」と。

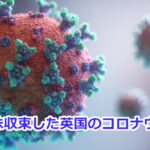








Comments